理系ライターが行く!vol.4『一人でも多くの人を病気から救いたい』#大人の社会見学

「理系ライターX」がすべての大学生に贈る、企業見学レポート連載! 持ち前の「理系知識」を駆使し、様々な企業に取材! 企業の知られざる一面や、想像もしなかった"あたらしい働き方"が見つかるかもしれないぞ。
▼INDEX
1.大日本住友製薬に取材してきたぞ
2.研究者として生きる、人を助ける研究者になる
3.アンメット・メディカル・ニーズへの対応
4.入社3年目でテーマリーダーに抜擢
5.日々、未知と向き合い、発見がある仕事
大日本住友製薬に取材してきたぞ
▶理系ライターXが行く!vol.1『人を助けるマシンをつくりたい』#大人の社会見学
大日本住友製薬の製品は薬である。といってもドラッグストアなどで売られている市販薬ではない。医療用医薬品、つまり特定の病気の治療のために医師が処方する薬だ。
新しい薬が一つできるまでには、とても長い時間がかかる。そんな新薬開発プロセスの第一ステップは、治療効果を発揮する化合物を見つけること。
この重要なテーマに取り組む本館利佳(もとだて りか)さん(大日本住友製薬リサーチディビジョン薬理研究ユニット所属)に、製薬企業における研究職の仕事への取り組み方や、そのやりがいについてお話を伺った。

研究者として生きる、人を助ける研究者になる
本館利佳さん「自分が取り組んだ研究の成果をきちんとした形、つまり論文に仕上げてから社会に出たいと思ったのです」
本館さんは北海道大学で博士号(薬科学)の 学位を取得している。学位論文の題名は『NMDA型グルタミン酸受容体の局在制御におけるX11とX11Lの役割』。X11・X11Lとは、神経細胞に発現しているアダプタータンパク質である。その研究は、アルツハイマー病のような神経変性疾患の発症機構の解明につながると評価された。
理系では修士で卒業して就職するケースが多いなか、本館さんはあえて博士課程に進んで学位を取りに行った。その理由を「自分が取り組んだ研究の成果をきちんとした形、つまり論文に仕上げてから社会に出たいと思ったから」と振り返る。
修士課程の2年間と、そこからさらに3年間の研究に取り組む博士課程では、研究の質が異なる。人類に何らかの『新たな知』をもたらしたと認められた者だけに与えられる勲章、それが博士号である。

「今や人生100年の時代ですから、そのうちの3年ぐらいは、自分のやりたいようにひたすら研究に打ち込む時期があってもいいかなと思ったのです。所属していた研究室では博士課程に進む先輩方も多かったので、ハードルが低かった点も後押しになりましたね」
学位取得後はアカデミアに残るのではなく、研究職として就職する道を選んだ。アカデミアでの基礎研究は刺激に満ちているけれども、その成果が世の中の役に立つまでに相当な時間がかかる。それより少しでも早く人のためになる成果を出したかったから、製薬企業における研究職を選んだ。本館さんが勤務するのは、同社の研究の中核拠点、大阪研究所である。
「製薬企業を数社受けましたが、初回の面接時に大日本住友製薬とは“波長が合う”と感じました。関東や関西の違いなどまったく気になりませんでした。北海道の人間にとっては、いったん津軽海峡を越えてしまえばどこへ行くのも同じですから(笑)」

アンメット・メディカル・ニーズへの対応
これまでに世界中の製薬企業が、数え切れないほど多くの薬を世の中に提供してきた。それでもアンメット・メディカル・ニーズ(未だに有効な治療方法が見つかっていない病気に対する、新たな治療薬や治療法を求める患者さんや医師からの強い要望)は解消されていない。なかでも大日本住友製薬が力を入れるのは、精神神経、がん、再生・細胞医薬の3領域である。
「私が携わっているのは、当社の3本柱の一つ、精神神経疾患を対象とする薬剤開発です。精神神経疾患は、患者さんご本人はもとより、そのご家族のQ.O.L(=Quality of Life:人生の質)まで低下させるため、治療に対する社会的ニーズが大きいです。がん領域についても新しい薬や治療法が見つかりつつあるとはいえ、多くの課題があり当社でもさまざまな取り組みを進めています」
さらに大日本住友製薬が今後の成長エンジンとして注力するのが、再生・細胞医薬分野における次世代再生医療の実現だ。この分野では京都大学iPS細胞研究所などとのオープンイノベーションに取り組み、例えばパーキンソン病に関する医師主導治験が進められている。
そんななか、本館さんが日々取り組んでいる業務は「選ばれた候補化合物の効果を評価し、薬効がありそうな化合物を探す研究(=薬理研究)」である。in vitro(=試験管内でヒトや動物の組織を使って体内と同じ環境を人工的につくって行う)実験から始め、薬効のある化合物が見つかれば、次にその化合物を使ってin vivo(=生体内)での実験で作用を確かめる。
「仮に薬効のある化合物が見つかっても、それが実際に薬として患者さんのもとに届けられるまでには、治験を繰り返して有効性/安全性を確かめるなど長い時間がかかります。だから日々の業務では、長期的な目標を頭に入れながらも、目の前の課題についての締切りを自分なりに設定して、業務を進めるよう心がけています」
大日本住友製薬は完全な裁量労働制(※)を採用している。そこで本館さんは、少し早めの毎朝8時に出社し、午前中を主に実験、午後は論文等の調べ物や会議などで過ごしている。そんな毎日を「やりたいことが多すぎて、毎日、時間の経つのがとても早く感じます」と語る。
※裁量労働制:実際に働いた時間に関係なく、労使間で定めた労働時間が働いた時間としてみなされる制度。

入社3年目でテーマリーダーに抜擢
研究職において実験と並んで重要な仕事が情報収集だ。現在取り組んでいるテーマに関連する新しい論文が発表されると、可能な限り目を通すよう心がけている。研究者にとって論文とは、ビジネスパーソンにとっての自己啓発書のようなものだという。
「論文は面白いですよ。思いも寄らなかったテーマと、今の自分のテーマがつながり、自分の中で漠然と考えていたことが、霧が晴れたようにくっきりと全体像までを見通すことができたりもしますから」
多くの論文に触れるため、短時間で論文の概要を把握できるように心がける。abstract(概要)をざっと見て、Figure(図表)に掲載されているデータを確認する。そのうえでResult(結論)を読めば、筆者の主張は大まかに理解できる。一方、気になる実験を見つけて、自分でも再現しようと試みるときなどは、深く読み込むケースもある。
そんななかである論文に記されていた内容にインスピレーションを受けて、治療につながる新たなアイデアを思いついた。そのアイデアを確かめるため本館さんは、新たな創薬テーマを立ち上げた。
「当社では入社年次に関わらず、新しいアイデアを思いついた人がテーマを立ち上げ、チームを組んで進めていきます。私は入社3年目ではありますが、発案者なのでテーマリーダーになりました。とはいえチーム運営などは初めての体験なので、経験が足りない部分は先輩方がサポートしてくれます。薬の候補選びが進むとテーマはプロジェクトと呼ばれるようになります。研究活動を活発化するために導入された”プロジェクト制”という仕組みで、プロジェクトのリーダーになると予算の執行権や人事評価などが年齢に関係なくリーダーに委ねられます。責任はあるけれどやりがいのある制度です。私のテーマもプロジェクトを目指して取り組んでいます」
自分が発案して開発された薬が、病気に苦しめられている人のところに届けられる。その結果、病状が改善され、患者さんやその家族の人たちが笑顔になる。仕事をしていて、これほどやりがいを感じることはまずないだろう。
「もちろん、そこまで到達するには、長い時間がかかるのですが、誰かを笑顔にできる仕事って、素敵だと思っています」
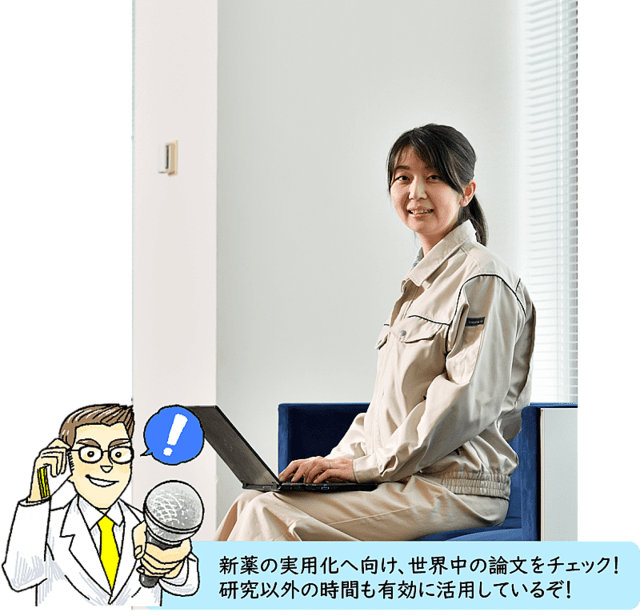
日々、未知と向き合い、発見がある仕事
「研究職の楽しさは、日々何かしら発見があること」と語る本館さんは、何か疑問があると自分でコツコツ調べるのが好きな性分だという。疑問や気づきは、同僚や上司とのなにげない会話の中から生まれることが多い。
「特定のテーマについて、チームを超えてディスカッションする場も設定されています。ここでは、普段はまったく考えていなかったアイデアと出合って刺激を受けたり、新しい情報を得ることができたり……。目の前の課題はいつも頭のどこかに置いておきながら、視野を思いっきり広げると思いもしなかったアイデアが浮かんでくることもあります。毎日が刺激に満ちていて、とても恵まれた職場ですね」
知的好奇心が刺激され、チャレンジを奨励される環境の中では、海外の学会に参加する機会も与えられる。本館さんも昨年、オーストラリアで開催された学会でポスター発表を行った。本館さんが所属する薬理研究ユニットの男女比は、ほぼ半々。職場環境はリケジョにとってとても働きやすく配慮されている。
「私は最近結婚したばかりですが、先輩方を見ていると、女性に対するいわゆる“ガラスの天井”などまったくないと感じます」
実際、薬理研究ユニットのトップは女性で、全社的に見ても取締役に女性も含まれている。男性に対する育休を推進する制度があるなど、子育てに対するサポートはしっかり整えられている。本館さんも、子どもが産まれた後も家庭と両立しながら仕事を続けたいと語る。
「仕事が趣味というと、少し誤解されるかもしれません。けれども、自分が興味を持つテーマに日々打ち込めることが研究職の魅力であり、しかも仕事の成果が、人を救う薬になる。この仕事は私にとって、まさに天職だと思っています」


大日本住友製薬株式会社 リサーチディビジョン 薬理研究ユニット 第2グループ
本館 利佳(もとだて りか)
北海道大学大学院 生命科学院 生命科学専攻 生命医薬科学コース修了、博士(薬科学)。2018年入社後、一貫して精神神経疾患の薬剤開発に取り組んでいる。
※記事内容及び社員の所属は取材当時のものです。
============
文:竹林篤実
イラスト:TOA
編集:ゆう


