「久世福商店」展開企業、長野発製造小売りの強み

「久世福商店」は直営とFC形式で展開する(撮影:梅谷秀司)
日本経済活性化の起爆剤として「中堅企業」への関心が高まっている。政府も2024年を「中堅企業元年」と銘打ち、法改正も行って支援態勢を整えた。『週刊東洋経済』11月23日号の第1特集は「すごい中堅企業100」だ。誰もが知る有名企業から意外なニッチトップ企業まで日本各地で飛躍している中堅企業の現状や、彼らを取り巻く環境の変化、注目企業ランキングなどをお届けする。
サンクゼール|上場(長野県飯綱町)
[業 種]食料品
[設 立]1982年
[代表者名]久世良太
[売上高]191億円(2024年3月期、連結)
[従業員数]265人(連結)
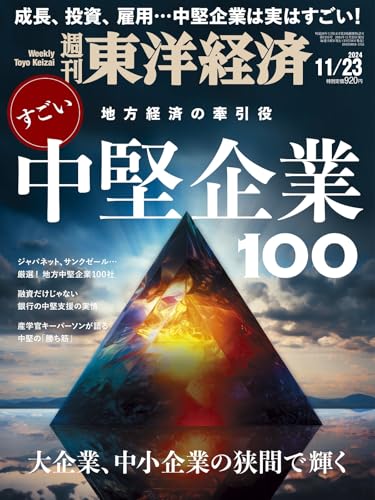
「久世福商店」のブランド名で和食材の小売店を国内に約160店展開するサンクゼール。燻製(くんせい)大根の漬物「いぶりがっこ」をあえたタルタルソースなど独自性の高い加工食品や各地の調味料が人気だ。長野県の飯綱町に本社を置く。
「自分たちで商品を作るだけでなく、売価も自分たちで決め、しっかり売れること」と久世良太社長が話すように、ビジネスの強みはこの分野には珍しいSPA(製造小売業)にある。商品の企画・開発から調達・製造までを自社と協力工場で完結できる。生産者約500社とネットワークを持ち、こだわりの食材を使った商品の開発が得意だ。
2022年12月に東京証券取引所グロース市場に上場。足元では、EC(ネット通販)や卸売りに加え、アメリカを中心に海外事業にも力を入れる。アメリカ小売り大手コストコ・ホールセール向けの売上高比率は10%を超える。
久世社長の父の良三氏(現会長)が斑尾高原で経営するペンションで宿泊客向けに出していた手作りジャムを商品化したところヒット。食品事業にシフトしたことが創業のきっかけだ。
1999年には軽井沢町に直営1号店を開き、小売り事業に乗り出す。最初のブランドは社名と同じ「サンクゼール」。祖業を引き継ぐ形でジャムやワインなど洋風の加工食品を扱い、現在は国内に13店舗を展開する。

各店舗には「商いの心得」が掲げられている(撮影:梅谷秀司)
2010年代に入り、事業の成長を模索する中で、和食の世界的なブームに商機を見いだす。和食がユネスコの無形文化遺産に登録された2013年、サンクゼールは「和のグロッサリーストア」をコンセプトに掲げ、久世福商店ブランドをスタート。今では屋台骨の事業に育った。
近年、サンクゼールを悩ませているのは製造コストの上昇だ。自社、仕入れ先ともに原材料費や人件費、エネルギー費は上がっており、コスト増を商品の価格に転嫁していかないと、仕入れ先の経営も立ち行かなくなる。
同社は2022年に商品の値上げを行ったが、2023年秋に入ると販売が低迷。2023年12月以降から値下げを進めたところ、販売は回復に転じた。仕入れや生産工程の見直しなどで原価を抑えて利益を確保する取り組みを進めていたが、その後も原材料のほか、包装資材や輸送費も高騰。今年9月から10月にかけて、久世福商店、サンクゼール両ブランドで商品の値上げ(それぞれ8%、6%)に踏み切った。
値付けの精度向上に本腰
商品価格を柔軟に変更できるのはSPAならではだが、収益確保には高精度な価格設定が要求される。同社は近年の経験を踏まえ、10月にリサーチセンターを設置。どの程度の価格であれば値上げを受容できるか、ブランドのファンコミュニティーに参加する顧客の反応も参考に値付けしている。
久世社長は「コストダウンの努力は今後も続ける。これからは商品の付加価値を顧客にいかに伝えられるか、ブランディングが重要になる」と話す。久世福商店ブランドは今年で11年目。商品の訴求の仕方にばらつきが出てきており、ブランドとして一貫したメッセージを発信する方向に整えていく考えだ。

2018年から社長を務める久世良太氏(撮影:梅谷秀司)
サンクゼールは2017年にアメリカに進出。和食材を輸出する一方、買収したオレゴン州の食品工場を使い、「ゆずみそドレッシング」など、現地に合わせた商品を開発・販売している。2023年にケチャップ、2024年にジャムを手がける食品メーカーの事業をM&Aで取得。当該商品の製造による自社工場の稼働率向上や互いの販路の活用というメリットがある。「アメリカでもこだわりの食品を作るメーカーが各地域にある。M&Aを活用しながら、ローカルの食文化を継承していきたい」(久世社長)。
上場は人材採用面でプラスになっているという。久世社長は「地方のいちばんの宝は企業。同じ志を持つ優秀な人が集まり、付加価値を生み出し続けていくことが大事」と強調し、働きやすいオープンな企業風土の醸成を目指している。

(木皮 透庸 : 東洋経済 記者)








