金属恵比須・高木大地の<青少年のためのプログレ入門> 最終回「停滞こそ我が墓碑銘」

金属恵比須・高木大地の<青少年のためのプログレ入門>
第38回/最終回 「停滞こそ我が墓碑銘」
2017年7月より続いた当連載もとうとう終わりを告げる時が来た。SPICE連載の“墓碑銘”に何を残せばいいだろう。
プログレッシヴ・ロックは1960年代後半に生まれ、1970年代に全盛期を迎えたジャンルである。その後80年代、90年代など何度かリバイバルブームがやってきたものの、「曲が長い」「難解」「複雑」という曲の特性上、“辺境の音楽”というイメージの特徴を持つ。
プログレをこよなく愛するSPICE編集の安藤氏が、このままだとプログレが滅んでしまうと危機感を覚え、30年以上プログレを愛好し演奏をしている筆者にお声がけいただき始まったのが当連載である。
筆者は1991年、小学5年の時に金属恵比須の前身バンドを結成して今まで続けている。小学校から最近まで「最年少のプログレ・バンド」と呼ばれてきた。中学の時には「ピンク・フロイドみたいなことをやってる中学生がいる」と面白がられ、NHKに出演もした(教育番組だったが)。安藤氏から初めて原稿を依頼されたのは2015年、35歳で『ハリガネムシ』リリース直後。この時も「最年少」と呼ばれていた。
それから8年。インディーズ・プログレ界は戦国時代の様相を呈し百家争鳴。金属恵比須の「万年最年少」も卒業である。メジャー・シーンに転身したバスクのスポーツ、ディスクユニオンで記録的な売上を樹立する曇ヶ原、イタリア進出のEvraak、日本語のセンスが映える百様箱など――あなたたちがここにいてほしい。胸を撫で下ろす。
ということで本連載「プログレ入門」の意義は果たしたと思うし、今後は皆様に盛り上げていただきたい。

バスクのスポーツ

曇ヶ原

Evraak

百様箱
■改めて「後退」すべきプログレ・アルバム五選
筆者にとって、今の「プログレ」とは――。
一つに、70年代のプログレ・バンドが展開したクラシックやジャズなどの他ジャンルを融合した音楽。そしてもう一つは、70年代のプログレ・バンドの音楽を基調とするものの、さらにそこに新たなエッセンスを添加して「プログレス(前進)」する音楽だと思っている。
今の「プログレ」は「後退」と「進歩」というアンビバレントな二つの要素を止揚する、ヘーゲルの弁証法のようなことを求められていると考える。
そこで、筆者が影響を受けた作品を紹介したい。
まずは「後退」部門。事実解説は省きあくまで個人的な視点を書き連ねることをご了承いただきたい。なお「後退」というネガティブな意味で捉えがちな言葉をあえて使用するのは、「いったん振り返ってみる」ということを具体的に示していると思ったからである。ポジティブな類語だと「伝統」などと表現されるが、むしろ抽象的すぎて意味を捉えきれない気がしている。あえて過去を振り返ることを直接的に表現するなら「後退」の方が具体的でわかりやすいと思っている。
ピンク・フロイド『狂気』(1973)

「プログレといえばコンセプト」という印象を与えたアルバム。鼓動・時計・レジスターなどの効果音を利用し曲間を繋げて「組曲」にする巧みな編集は、後世に多大な影響を与えた。我が金属恵比須のファースト・アルバム『箱男』でも流用している。
また「走り廻って」のシンセサイザーによる無機質な電子音リフレインも近未来的でSF的でもあり、プログレスした印象を与えた。なお、タンジェリン・ドリームが「あんなの電子音楽じゃないよ」と、我こそが電子音楽の表現者だといったというが、何よりフロイドの恐ろしい点は「電子音楽みたいなワケわかんことやってる」感を醸し出すこと。勝手にリスナーが想像し話を膨らませて「凄いかも」と思わせてしまうほどのオーラを放っていたといいうことだ。ハッタリ。プログレのバンドでは最も重要な点である。
イエス『危機』(1972)

「プログレといえば長い組曲」という印象を与えたアルバム。表題曲は「i. 着実な変革」「ii. 全体保持」「iii. 盛衰」「iv. 人の四季」という4楽章で構成されている。何かいいたげだけれどもまったく意味がわからない思わせぶりな邦題をつけた功績が大きいかもしれない。また、楽章のスタイルによって「クラシックと融合」という風評もあるが、音楽的に見れば音大出身キーボーディストのリック・ウェイクマンがクラシカルなフレーズを度々弾いているのみで、直接の影響は感じられない。
この後、フォロワーたちがこぞって組曲形式を真似て長大な曲をつくり始めるが、「危機」を超える組曲はなかなか出会えない。なぜなら、「危機」のメインメロディは3つぐらいしか出てこず非常にシンプルな構成をしているからである。20分近い長さを少ないメロディを飽きさせずに変奏で繰り返すという高度なテクニックを使っているのだ。フォロワーの多くは、曲を長くするためについつい色々なメロディを詰め込みがちで、曲が長いから余計に印象が薄まってしまう現象が起きる。が、ロックの基本は「リフレイン」(同じフレーズを繰り返すこと)。プログレもやはりロックなのだ。
エマーソン・レイク&パーマー『恐怖の頭脳改革』(1973)

「プログレといえばジャケットのインパクト」という印象を与えたアルバム。映画『エイリアン』のデザイナーとして有名なH.R.ギーガーが描いた骸骨の女性に目が奪われる。レコード発売時は変形ジャケットとして発売され、骸骨が真っ二つに割れメデューサが現れるという凝った作りだった。にもかかわらずこの絵が音楽のどの部分を意味するのか、にわかには理解しがたい。こういったケレン味も大切。プログレは音楽でのインパクトはもちろん、ビジュアルも大仰で思わせぶりなのが重要である。
ジェネシス『月影の騎士』(1973)

「プログレにはキーボード必須」という印象を与えたアルバム。「ファース・オブ・フィフス」「シネマ・ショウ」というキーボード・ソロのオンパレードがその後のプログレの方向性を決定づけた。プログレっぽい曲をつくりたい!――と思ったらとりあえずオルガンかシンセサイザーで分散和音を弾き続ければそれっぽくなる。ジェネシスは「ザ・プログレ」テンプレートをつくり上げた。また「ギター・ソロは泣きのフレーズ」というプログレのセオリーも「ファース・オブ・フィフス」で完成されたといえよう。とかくに「プログレやりたい!」と思ったらまずはこのアルバムを徹底的に真似するとすぐにそれっぽくなる。
キング・クリムゾン『太陽と戦慄』(1973)

「プログレといえば変拍子」という印象を与えたアルバム。「変拍子」とは、通常の音楽で用いられる4/4拍子や3/4拍子以外の、普段あまり使われることのない5/4拍子や7/4拍子といった特に奇数で素数が分子の拍子のことをいう。普段聞きなれないものだから容易にノることはできない。ノれないのにカッコいいロックをやってしまったのが「太陽と戦慄パートII」だ。奇数拍子と偶数拍子が入り乱れ、容易に理解することが難しい曲で、かつ不協和音の嵐。いっそう不穏にさせるこの雰囲気もプログレには欠かせない。
筆者にとってのプログレのエッセンスは、
・コンセプト
・長い組曲
・ジャケットのインパクト
・キーボード必須
・変拍子
ということになる。逆にこの5点を体現すればおのずとプログレになるのである。
奇しくもか、必然なのか、1973年の作品が多い(『危機』のみ1972年9月)。ちょうど50年前にプログレはピークを迎えた。1973年に「後退」することが、プログレ道にとってまずは第一歩になると考えている。
■「進歩」のための書籍三選
次に「進歩」のおすすめを見ていきたい。
ただし音楽ではない。
ミュージカル映画『ウェストサイド物語』の作曲者で指揮者として高名なレナード・バーンスタインは、指揮者をすればするほど作曲ができなくなるとぼやいていたらしい(TV番組「タモリの音楽は世界だ」による)。指揮者は作曲者の技法などをくまなく分析しなければならないため、やればやるほど「ああ、この手法、この作曲家やってるわ」となってしまい、自分の打つ手がなくなってしまうのだ。
また、キング・クリムゾンのベーシストのトニー・レヴィンは、聴く音楽はオーケストラの作品が多いらしい。ロック以降の音楽を聴くと似てしまうから聴かないという趣旨の発言を見たことがある。
音楽を聞いているだけではプログレスしない。ということで書籍を紹介する。金属恵比須のバンド活動に影響を与えた3冊だ。
『USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか?』(森岡毅著、2014年、角川書店)
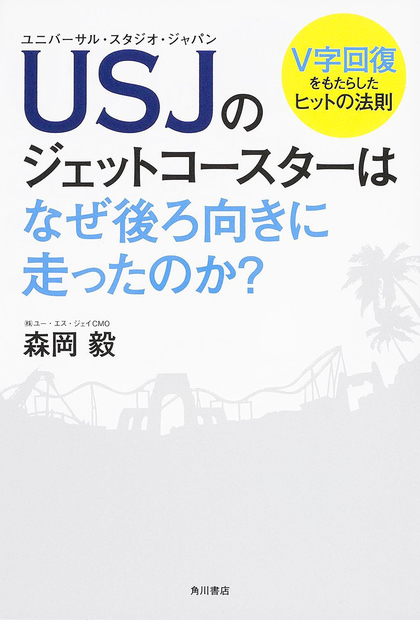
マーケティングのビジネス本。窮地に陥ったユニバーサル・スタジオ・ジャパン(USJ)をV字回復させた森岡氏の筆による。
キーワードは「方向性を間違えたこだわり」(24ページ)。アトラクション「ピーターパンのネバーランド」でハイレベルなエイジング加工していたのだが、お客様からは古くてボロいと不評だったとのことで、消費者の求めるものとのズレを感じ、消費者の求めるものは何か、求めないものは何かを考え直し、さかなければならない時間と費用を考え直した。
金属恵比須は、いかに方向性を間違えたこだわりを大事にしていたかということを悟る。筆者の例だと「ベース・ペダルのこだわり」というのがあった。イエスやジェネシスが荘厳なアレンジの時に、ベーシストがベース・ギターとは別に、ペダル型の鍵盤(足鍵盤)を用いて低音を鳴らすというシーンがある。技術が発達した今となってはあえて足鍵盤に頼らずとも他の楽器で再現できる音色だ。これをあえて再現するのはプレイヤーの自己満足でしかない。そもそもリスナーの多くは足でベースを鳴らすという行為を求めていない。求めているのはプレイヤー。
なぜ足でベースを弾かなくてはならないのか。プレイヤー目線では理由があるが、リスナーには理由はない。おまけにプレイヤーとしては作業がひとつ増えるのでプレイに影響が出てしまう。よって練習が必要だ。が、その演奏に時間を割く必要があるのか。その時間を感動する音楽をつくり出す方に回した方がいいのではないか。金属恵比須としてはこれが「方向性を間違えたこだわり」と感じたのである。
また、このようなことも書かれていた。
「差別化という美しい戦術に憧れて溺れることがあります。差別化すること自体にこだわってしまい、本来の目的を失ってしまうのです」(39ページ)
当時のUSJは「映画だけのパーク」を目指しており、そのターゲットが「不必要に狭すぎる」(37ページ)を危惧し脱却したという。プログレにおいては「プログレ」と名乗るだけで相当狭くしているにもかかわらず、内部で戦国時代だから「~~系プログレ」とさらに細分化する。ただでさえ「プログレ」でニッチなのに、それをさらに細分化しリスナーを限定するというのは、はたして正しい選択なのか。「プログレ・バンド」というだけで十分差別化されているので、金属恵比須は「プログレ・バンド」と名乗っている。
『いつかギラギラする日 角川春樹の映画革命』(角川春樹・清水節、角川春樹事務所、2016年)

角川映画を興し、映画界に革命をもたらしたメディアミックスの祖・角川春樹氏の“武勇伝”。角川最初の映画『犬神家の一族』に衝撃を受け、影響を受け続けている筆者としては読まないわけにはいかない。
薬師丸ひろ子を発掘するオーディションの時にドキュメンタリー映画『野性号の航海 翔べ 怪鳥もあのように』を同時上映した。角川氏が埴輪をもとに作った古代の舟で47日かけて朝鮮半島に渡るという内容。角川氏はこう語る。
「『野生号の航海』の興行は史上最低の入りでしたから。なんか文句あんのかって(笑)。(中略)映画は思い入れだけじゃ出来ないことを思い知る、いい経験になりました」(69ページ)
この言葉に突き動かされた。読んだのは『ハリガネムシ』発表からしばらくたち、次のフル・アルバムを構想していた頃。『ハリガネムシ』はやりたいことの思い入れを詰め込んだ作品だった。
前述の森岡氏からも学び、間違ったこだわりで突っ走ろうとしているかもしれず、次のアルバムではリスナーから見放されるかもしれないという危機感もあった。そして何より音楽至上主義に陥っている危機感があった。思い入れだけでは続けられないのだ。
「制作・宣伝・配給・興行、そのすべてが『映画』なんです」(47ページ)
続いてこの言葉にも衝撃を受けた。音楽を制作するだけがプログレではないのか。「遠足は家に帰るまでが遠足です」のように「リスナーの手に届くまでがプログレ・ミュージシャンです」ということか。プログレ・ミュージシャンとしての思い入れと自己満足は作曲の段階のみに押し留め、その後はプロデューサーに徹することを心がけるようにした。特に意識したのが「宣伝」である。といっても自主制作ゆえにCMや広告が出せるような財政状況ではない。「宣伝」と大仰な言葉でも突き詰めれば「知らせること」。SNSしか武器がない自主制作バンドがSNS以外でどうやったら知ってもらうだろうか。
そこでメディアミックスを活用するように。角川映画の最初の発想は、横溝正史の書籍を広げようとするために映画を作りレコードも作るというメディアミックスだった。同じことをバンドが出版社に声がけをして行なったら面白いのではないか。結果生まれたのが、作家・伊東潤氏と角川書店に協力いただき、2018年に発表した『武田家滅亡』である。
余談だが、角川氏が映画業界に乗り出す前からどうしても作りたいと考えていた映画は小松左京『復活の日』だったらしい。その願いは1980年に深作欣二監督の手によって実現しているものの、商業的にはうまくいかず以降は大作路線を捨てプログラム・ピクチャーの道を進み、『セーラー服と機関銃』などのヒット作を生み出していく。やりたいこと、求められていること、やらなければいけないこと、この3点がうまく有機的に結び付かなければならないのだ。
『「週刊文春」編集長の仕事術』(新谷学著、ダイヤモンド社、2017年)

新谷学氏は2012年より「週刊文春」にて数々のスクープを連発し話題をさらった編集長(現「文藝春秋」編集長)。「文春砲」が流行語となったのも新谷氏在任時だ(新谷氏が生み出した言葉ではない)。本書は新谷氏の企画発想術や交渉術、統率力が記されたビジネス本。筆者は大学時代、週刊誌の編集者を志望し就職活動をした過去もあり、本書は発売直後に購入しすぐに読み終わった記憶がある。
まずは「いい企画」に関して。
「企画の良し悪しを見極めるひとつの大きなポイントは『見出しが付くか付かないか』だ」(90ページ)
つまりインパクトがあって面白くてわかりやすいタイトルがつけられる企画は良い企画だということだ。
「タイトルは短いほうがいい」(92ページ)
ともある。バンドにおいてはアルバムもライヴもイベントも広義の「企画」だ。ということでこの頃からこれを心がけいくつかイベントを催した。2019年7月に新曲「ルシファー・ストーン」を発表した際に体験型イベントを企画。「ルシファー・ストーン」というパワーストーンのありかをTwitterを用いてリアルタイムで公開するヒントをもとに見つけ出すことを競う。題して「ルシファー・ストーンを探せ!」。1982年、角川映画『化石の荒野』で行なった「金塊探しキャンペーン」を参考にしているが、当イベントもKADOKAWAからのご協力をいただくことができた。これもメディアミックスの発想からである。

ルシファー・ストーンを探せ!
ほかにはディスクユニオン・ロックイントーキョー(渋谷)で行なった「キンゾク万博2021」。ディスクユニオンからのポップアップストア依頼に対し、どういうネーミングがいいだろうと考え抜いて思いついたのが「キンゾク万博」だった。名前が決まった瞬間、1970年の大阪万博が思い浮かび、おのずと売場のイメージも出来上がった。太陽の塔をシンボルにその周りを「歴史館」「各メンバー館」などに配置し、それにあった商品を並べていく。新谷氏のアドバイスからは少々ズレるかもしれないが、シンプルなタイトル・見出しがつくことによって内容が決まっていくのである。

キンゾク万博2021(左から佐野雄太監督、稲益宏美、筆者の同級生トリオ)
また、金属恵比須の動きで最も重要なのが次の言葉だ。
「初めて挨拶をかわした後、たいてい一度は会食をする。(中略)基本的にはサシでじっくりと付き合う」(49ページ)
2010年代より演奏者以外の方々からお声がけくださる機会が多くなった。金属恵比須のメンバーは皆、人好きで好奇心旺盛である。ライヴ会場でそのような方々と出会い、名刺交換をさせていただくのだが、バタバタしてちゃんとお話ができない。これを読んでからは興味を持っていただいた方には会食をお誘いすることに。そしてサシを心がける。サシだと本音で話し合うことができ、そこからいろいろな方を紹介いただくという好循環が生まれた。その結果、ある新聞社とレジェンドのロック・バンドを引き合わせるなど“マッチングアプリ”のようなこともしたり。直接金属恵比須が関わらなくても、音楽・文化の発展に寄与できればと進んで“マッチング”を行なっている。
「普通の人は『今度飯行きましょう』とか『また改めて』というセリフの社交儀礼として言いがちだ。しかし、私が尊敬するすごい人たちは、社交辞令で終わらせない。『やりましょう』と言ったら、すぐ『じゃあ、いつやろうか?』と日程調整に入る」(46ページ)
とも書いてあったので、すぐに会食の日を決めるようにしている。
これによって、金属恵比須を応援していただく方々と物事をすぐに決められるようになり、さまざまな分野とともに企画を立ててきた。
以上が「進歩」の部分である。こうして筆者は1973年への「後退」と未来への「進歩」を織り交ぜ、「プログレ」を培っているのである。「3歩進んで2歩下がる」ではなく「50歩下がって100歩進む」のだ。
■停滞こそ我が墓碑銘
最後にもうひとつ。近年は樋口真嗣監督の影響が最も大きい。「平成ガメラ」シリーズで昭和ガメラを復活させ(特技監督)、『シン・ゴジラ』『シン・ウルトラマン』でも昭和の特撮を新しい地平に導いた特撮映画界のレジェンドである。数々の偉業を見れば分かるとおり、「後退」と「進歩」のバランスが絶妙で、ちゃんとプログレスした世界観を作り上げている。この手法こそがこれからの金属恵比須に必要だと強く思い、図々しくお付き合いさせていただき、勝手に慕わせていただいている。樋口監督の著作を紹介したい。
『樋口真嗣特撮野帳』(樋口真嗣著、パイ インターナショナル、2022年)

樋口監督がこよなく愛するコクヨのノート「野帳」。映画の絵コンテやアイデアをメモするノートをそのままスキャンして、野帳の形に似せてそのまま本にしたものである。『シン・ウルトラマン』や『シン・ゴジラ』の制作の過程を覗き見しているようで罪深くも面白い。巻末にはインタビューがあり、樋口監督が映画・アニメに飛び込んだ経緯などが語られる。その中でアニメや特技監督をやってきた経験から『ローレライ』で監督を務めた時のエピソード。少し長いが引用する。
「今までのアニメや特撮だと、自分でコントロールしたい、絵コンテどおりにしたいってところに対して、その部分を抱え込んでしまうことが多いんですよね。ただ、そこを抱え込んでしまうと、絵コンテ以上のものにはならない。(中略)妻夫木聡さんとか話しかけてくれるんですよ。『監督が、その人の芝居が好きで呼んでるんだったら、その人の芝居を信じてあげましょうよ』(中略)そうだ、この人たちに託せるものは託したほうがいいんだな、と気づきはじめるんですよね」(625ページ)
プログレもまさに同じ。複雑な楽譜を書くことに酔いしれたり、コンピュータ上で美しいアレンジをして悦になったり、とかくに“机上の空論”になる傾向がある。でも結局はバンドで演奏する音楽だ。金属恵比須のメンバーには、人間椅子、頭脳警察、GERARDを渡り歩いた伝説的ドラマー・後藤マスヒロだっている。演奏はプレイヤーに託した方がいいに決まっている。複雑な楽譜を書くこととその再現は、まさに「方向性を間違えたこだわり」なのだ。
さて、本職の映画ばりに音楽と楽器(特にシンセサイザー)に精通する樋口監督。前号にも書いたが、金属恵比須のニュー・アルバム『虚無回廊』についてこのような感想をいただいた。
「音楽家は常に前に進まなきゃならないのに、一人(筆者)だけ引きずられて心配になっちゃう(笑)。どこが“プログレッシヴ(前進的)”なんだよって(笑)」
「こんなにモーグ・シンセサイザーを使いこなして、“あんな音、いまだに出してるんだ”って。時代が停滞しすぎていてむしろ新しい!」
本人はプログレスしているつもりなのに、映画の最先端をひた走る樋口監督にはそうは見えていなかった。思えば「メディアミックス」「会食」なども、よく考えれば「進歩」した方法ではない。結局はプログレスしていないのかもしれない。
停滞こそ我が墓碑銘。
6年間、まことにありがとうございました。
高木大地(金属恵比須)







