「文芸のプロ」が"第169回芥川賞"を独自採点・予想
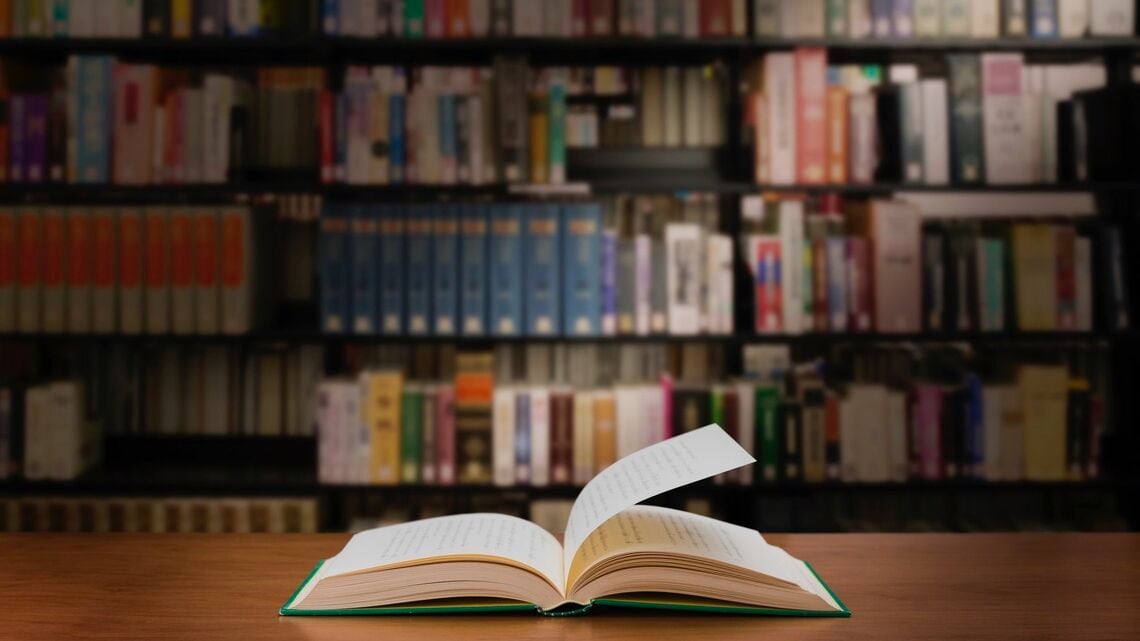
「第169回芥川賞」候補作5作品を、「文芸のプロ」が独自に採点、解説します(写真:kuro3/PIXTA)
「第169回芥川賞」の発表が、いよいよ7月19日夜に行われる。
候補作の条件は『新潮』(新潮社)、『文學界』(文藝春秋)、『群像』(講談社)、『すばる』(集英社)、『文藝』(河出書房新社)などの文芸誌に発表された単行本未収録作品が対象となるが、今回も選りすぐりの5作品が候補となった。
中上健次から江藤淳、吉本隆明、阿久悠まで、数々の評伝を綴ってきた文芸評論家の高澤秀次氏が、独自の採点と評価にもとづき、候補作5作品を解説する。
「第169回芥川賞」候補作を独自で採点予想
「第169回芥川賞」の発表が7月19日夜に行われるが、それに先立ち、独自採点と予想を行ってみた。
まず候補作の条件だが、純文学系の新人作家の短篇で、具体的には『新潮』(新潮社)、『文學界』(文藝春秋)、『群像』(講談社)、『すばる』(集英社)、『文藝』(河出書房新社)などの文芸誌に発表された単行本未収録作品が対象となる。
「純文学」というのは、今や死語になりつつあるが、年2回の芥川賞、直木賞(エンターテインメント系の単行本が対象)発表のときだけは、画然とジャンルの仕切りが際立つようになっている。
現在の選考委員は松浦寿輝、島田雅彦、奥泉光、山田詠美、川上弘美、小川洋子、吉田修一、平野啓一郎、堀江敏幸の9人。
このうち山田詠美は、生粋の純文学作家だが直木賞受賞者。理由は、受賞作『ソウル・ミュージック・ラバーズ・オンリー』が、角川書店から刊行されていたため。角川の本はあらかじめ、芥川賞の候補作の対象外(徳間書店しかり)なのだ。これが「文壇」という制度のルール。
選考委員中で非受賞者の島田雅彦は、デビュー作「優しいサヨクのための嬉遊曲」(1983年)以来、最多の6度のノミネートにもかかわらず、受賞に至らなかった。選考委員以外では、村上春樹も吉本ばななも、本賞と縁がなかった。
出版各社には、当然、営業上のかけひきや、先物買い的な売り込みもある。かつて選考委員の古井由吉は、誰のどの作品を選ぶかの基準には、「ジャッジ」(作品評価)と「スカウト」の両要素があると語っている。
さて、今年はどういう結果になるか。
筆者の事前予想を一覧表にした。

では、ひとりずつ筆者の予想を紹介する。
石田夏穂「我が手の太陽」(『群像』5月号)
1991年生まれ。2020年、「その周囲、五十八センチ」で大阪女性文芸賞受賞。2021年、「我が友、スミス」が芥川賞候補に。
2回目のノミネートの本作は、東京工業大学工学部卒のリケジョ(理系女子)である作者によるベテラン溶接工のお話。
作者は意図的に、主人公「伊東」の家族関係をはじめとする個人情報を、作品上排除している。それが高専卒、職歴20年のベテラン溶接工の自己崩壊の物語への共感を阻んでいるとも言える。つまり評者に言わせれば、一般読者は、この切れやすく、独りよがりで職人気質の主人公にシンパシーを持ちにくいのだ。
職人として、人間としての「強さ」と「弱さ」、その自己認識のズレが徐々に拡大し、浜松での溶接工事で品質管理責任者から思わぬ「不合格(フェール)」を出された伊東は、深夜のやり直し配管溶接で「安全帯」をつけずにいたのが発覚、「溶接」をはずされ、解体現場のガス「溶断」の仕事に格下げになる。
さらに職業病のヒューム肺を患った先輩の仕事の肩代わりで、密かに溶接工事の現場に戻るも、手元の狂いから重度の火傷をおってしまう。それがたんに年のせいなら、さしたる問題にはならない。上司からこの際現場を離れ、管理職に就いてはと打診されてもいたからだ。
しかし、タイトルにこめられた「わが手」への偏執を主人公はどうしても手放すことができない。そこにもまた、自己認識のズレが関わってくる。
「お前は傲慢なんだよ。自分をすごいと思うのは人の自由だが、どんな作業も馬鹿にしてはならない。そうだろう。お前は自分の仕事を馬鹿にされるのを嫌う。お前自身が、誰より馬鹿にしているというのに」
これは、他者から言われたのではなく、伊東の自己認識なのだから、読者にはちょっと痛すぎて息が詰まるのではないか。
映画なら、カメラをいったん外(職場を離れたプライベートな日常世界)に出そうよということになるのだが。
次の候補作は、市川沙央「ハンチバック」(『文學界』5月号)である。
市川沙央「ハンチバック」(『文學界』5月号)
1979年生まれ。候補作は、今年の文學界新人賞受賞作でデビュー作。
同誌の著者プロフィールには、「早稲田大学人間科学部eスクール人間環境科学科卒業。筋疾患先天性ミオパチーによる症候性側彎症および人工呼吸器使用・電動車椅子当事者」とある。
今回の候補作中、最大の問題作。
「紗花(しゃか)」のハンドルネームをもつ重度障害者「井沢釈華」は、「せむし(ハンチバック)の怪物」を自認するTL(ティーンズラブ)小説の書き手でもある。
両親から億単位の遺産と看護・介護付きグループホームを残されたヒロインの切実な願いは、望み少ない「人間になれるチャンス」をつかむこと。
彼女は「人生の真似事」として、「産むことは出来ずとも、堕ろすところまでは追い付きたかった」。〈生まれ変わったら高級娼婦になりたい〉とさえツイートするのは、「清い人生を自虐する代わりに吐いた思いつきの夢」だった。
ただ本作が「問題作」であるのは、こうした衝撃的な作品設定のためばかりではない。
語り手は、新人賞選考委員を含む全読者を呪詛するかのように、「本好き」たちの無知と傲慢を諫めているからだ。本を両手で押さえて没頭する読書は、ほかのどんな行為よりも背骨に負荷をかけるため、彼女は「紙の本」を憎み、読書文化のマチズモを憎んでいる。
新人賞選評で5人の選考委員は、一様に本作を絶賛しながら、全会一致で作品のラストの詰めの甘さを指摘している。おそらく作品の構成上の破綻、あるいは物語的な整合性のうえでの難点を指摘したもの。
受賞決定後、雑誌発表のために作者が部分的書き直しを行うことは珍しくない。ある場合には、選考委員の意向を編集者が伝え、書き直しを促すこともある。今回のケースがどうだったのかは知るよしもない。
ただし、「釈華が人間であるために殺したがった子を、いつか/いますぐ私は孕むだろう」という、最後の一節は、評者にはこれで十分と思われるのだが。
作者はこの作品で、現代文学の新しいジャンルを切り拓いた。それを率直に、言祝ごうではないか。大本命、間違いなし。
次の候補作は、児玉雨子「##NAME##」(『文藝』夏季号)である。
児玉雨子「##NAME##」(『文藝』夏季号)
1993年生まれ。アイドル歌手への作品提供で知られる作詞家でもある。単行本化された作品に『誰にも奪われたくない/凸撃』(2021年)がある。
今回が初のノミネート作品。
「雪那(せつな)」と「美砂乃(みさの)」、2人の少女のユニークな成長譚。2人は同じアイドル事務所に所属する仲良しカップル。
ヒロインの雪那は、ステージ・ママ志願の母親に背中を押されながら、気乗りのしない少女二軍タレント活動を続けつつ、辞めたバスケ部の女子らから陰湿ないじめ(「死ね」「変態」と書かれたメールを送り続けられる)を受けている。
片や美砂乃は、順調にアイドル路線を突っ走る。
「せつなはゆきなっぽいから」「ゆきって呼ぶね」と美砂乃(「みさって呼んでね」)に言われるが、タレント活動にどこか集中できない雪那は、「ゆき/みさ」の愛称にもなじめず、ある日、「学校のこと考えたり、心配する暇がないの」という売れっ子の美砂乃に、「本気じゃないなら話が合わないから」「辞めて、全部」と突き放される。
事務所を辞め大学に進学、BL研究会に入り二次創作に打ち込む雪那は、ジュニア・アイドル時代の写真が、児童ポルノであったことを知る。しかもそれは研究会のメンバーも知っていたことで、ネット上で拡散、家庭教師の口さえ失った彼女は、就活を控え親にも相談せずに「改名」を思いつき実行する。
そして、「私はすべてを捨てて生まれ変わったわけでも生まれ直したわけでもなく、既に私でいたことに気づく」のだ。
ここでようやく彼女は、「ゆき/みさ」という、かつてなじめなかった「私たちだけの言語」を受け入れる。
傷つきやすい少女のNAMEの揺れ(本名・石田雪那、芸名・石田せつな、改名後・石田ゆき)をめぐる知的な小説と言うべきで、山田詠美、川上弘美、小川洋子の3人の女性選考委員がどう評価するかがポイントになりそうだ。
『文藝』からの受賞作となれば、2020年の宇佐美りん「推し、燃ゆ」以来となる。
次の候補作は、千葉雅也「エレクトリック」(『新潮』2月号)である。
千葉雅也「エレクトリック」(『新潮』2月号)
1978年生まれ。2019年『デッドライン』で野間文芸新人賞。2021年「マジックミラー」で川端康成文学賞。芥川賞ノミネートは本作が3回目。
本職の哲学者としてもキャリア十分で、業界内では、作家としても希望の星。
ただ、これだけリーダブルでノイズのない小説は、評者としては逆に物足りない。透明な語りに反した、障碍としての最良のノイズ(スムーズな「物語」展開への干渉)こそが「小説」の生命なのではないか。
「未来を拓く父と子の英雄譚」といううたい文句だが、膠着状態にある1995年の地方都市・宇都宮での家族の「現在」に対してのコミットが不十分。時代を象徴するオウム真理教の影も、どこか取って付けたようだ。
そのため「スタジオ」から宇宙へ──という作品の超現実の飛躍的オチは、どうしても唐突で苦し紛れの父子の逃避行(=異次元世界への逃走)にしか見えない。
「父が一人で寐るようになったのはいつだろう?」と書くのなら、美人の妻の顔色を窺いながら「スタジオ」にひきこもり、オーディオ機器をいじる父と、「一人で寐るようになった」母の性に、息子の達也(高2)は、しっかりと正対しなくてはならない。
そこに何とか「同性に興味があるという同世代の男の顔を、初めて見た」達也の性のときめき(それが、作者が「哲学」に甘んじられない根拠なのだろう)を、アンチ・マザコン的に重ねられなかったか。
『パンとサーカス』でアナクロがかった前世代を「量子コンピューターの時代の真空管」と評した選考委員の島田雅彦は、この真空管レトロ・エレクトリックな小説をどう評価するか。「現代思想」にも通じた選考委員・松浦寿輝の評価とともに興味深い。
本作で三島由紀夫賞受賞はならなかったが、リベンジなるか。
最後の候補作は、乗代雄介「それは誠」(『文學界』6月号)である。
乗代雄介「それは誠」(『文學界』6月号)
1986年生まれ。2015年「十七八より」で群像新人文学賞。2018年『本物の読書家』で野間文芸新人賞。
本作が、候補者中最多の4回目のノミネート。
作中「牛の涎」(これは自然主義文学をからかった二葉亭四迷の『平凡』の冒頭にある言葉)と自己言及する饒舌体で、最後まで読ませる。
東京での修学旅行の自由行動日に、生き別れ状態の「おじさん」に会いに行く、祖父母と暮らす「ぼっち」高校生と、彼の行動に付きそう男子、この予定表にない行動を隠蔽するために口裏を合わせる女子たちとの友愛を描く。
彼が「ぼっち」でなくなる後半の盛り上がりは感動的だが、そのきっかけに宮沢賢治をもってきたのは、いかにもあざとい(「日野」−「新撰組」−「誠」の関連づけはさらにイージー)。
キャラクターの書き分け(とくに主役と脇役のメリハリ)は見事だが、女子・小川楓が、「ぼっち」佐田誠のどこに惹かれたのかについての、物語的伏線があってもよかった。そうなると当然、誠に拮抗する楓の「家族物語」を語り起こさねばならないが……。
ただ、会えなそうで会えた「おじさん」との再会を、ぎりぎりまで引き延ばす作家のテクニックはただものではない。しかも直接それを、「誠」と「おじさん」の感動的再会シーンではなく、付き添い男子の言葉で再現する心憎さ。
この作家は、間違いなくうまいことはうまい(スマホの使い方まで)のだが……。消去法で有力3作には残りそう。
さて『パパイヤ・ママイヤ』に続く作者渾身の青春小説、四度目の正直となるかどうか。
松浦寿輝、島田雅彦、奥泉光、山田詠美、川上弘美、小川洋子、吉田修一、平野啓一郎、堀江敏幸の9人の選考委員による「第169回芥川賞」の発表は、7月19日夜に行われる。
(高澤 秀次 : 文芸評論家)








