伝え下手な人がハマりがち、話し方の「落とし穴」

自分が「伝えたいこと」と、相手が「伝えられたいこと」は違います(写真:jessie/PIXTA)
何かを伝えるとき、長文メールになって「結局、何が言いたいかわからない」と言われる。話していても、いろいろ情報を詰め込みすぎて、うまく伝わらない。場面に応じて、「伝え方」を工夫しているのにうまくいかない。
それは「伝わる」メカニズムを知らないだけです。
多くの人が誤解しているコミュニケーションの仕組みを理解すれば、結果は大きく変わります。そのような「伝え方の原則」をまとめたのが、松永光弘氏の新刊『伝え方--伝えたいことを、伝えてはいけない。』です。
著者の編集家である松永氏は、これまでクリエイティブディレクターの水野学氏、放送作家の小山薫堂氏など、日本を代表するクリエイターたちの書籍を企画・編集。その後企業ブランディングなど、さまざまなコミュニケーションをサポートしており、顧問編集者の先駆的存在として知られています。
その経験から松永氏が気づいたのは、文章もお話もデザインも「伝え方の原則」は同じということでした。本記事では、同書から抜粋し、意外と知られていないコミュニケーションの仕組みについて解説します。
世間では「自分が伝えたいことを伝えるべきだ」とよくいわれます。
でも、本当にそれでいいのか。それで通用するのか……。
結論からいうと、残念ながら、そういつもうまくことが運ぶわけではありません。実際のコミュニケーションでは、「伝えたいこと」を伝えても相手に伝わらないのです。
子どもへの説教が伝わらない訳
いちばんわかりやすい例のひとつは説教でしょう。
たとえば、親が子どもに「勉強しないと、ろくなおとなになれない」と伝えたいとする。もしくは「自分は勉強しなかったことを後悔している」と伝えたい。そのまま伝えたところで、子どもが納得したり、共感したりすることはまずありません。
「伝えたいこと」を伝えても、伝わらない。
なぜでしょうか。最大の原因は、じつは伝えるコミュニケーションの構造そのものにあります。そもそも、伝え手の「伝えたいこと」が、受け手にすんなりとは受け入れられづらい構造のなかで、私たちはコミュニケーションをしているのです。
もっといえば、「伝えたいこと」をそのまま伝えても、納得してもらったり、共感してもらったりするどころか、受け手とのあいだに「コミュニケーションの橋」が架からない可能性すらあります。
いったい、伝えるコミュニケーションは、どんな構造になっているのでしょうか。といっても、けっして小難しい話ではなく、要は「私たちが日ごろ、どんなふうにコミュニケーションをしているか」ということなのですが……。こういわれて、多くの人たちがまず思い浮かべるのは、下のような構図でしょう。
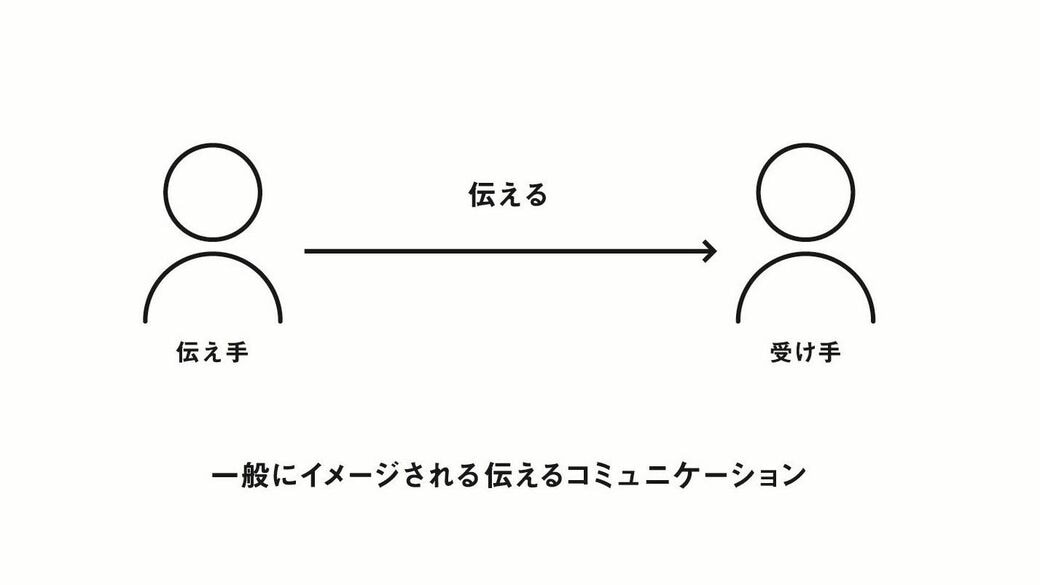
(『伝え方--伝えたいことを、伝えてはいけない。』より)
登場人物はふたり。ひとりは、なにかを伝えようとする「伝え手」。もうひとりは、それを受けとる「受け手」です。この関係のなかで、「伝え手」は「受け手」に向かってなにかを「伝えよう」と働きかけます。
その結果、うまく「受け手」が納得したり、共感したりすれば「伝わった」となる……。こうしてみると、ごくふつうのことを語っているだけで、おかしなところはなさそうに思えます。
しかし、実際の伝えるコミュニケーションは、こんなふうにおこなわれてはいません。
伝え手と受け手の間にあるもの
登場人物がふたりというのは同じです。ひとりが「伝え手」で、もうひとりが「受け手」というのも変わらない。ただ、働きかけのプロセスが少しちがっています。
「伝え手」が「受け手」に“直接”働きかけることはまずありません。「伝え手」はかならず「伝える事柄」をいったん表現します。そして「受け手」が、そこにかかわり(見たり、聞いたり、読んだりする)、そのうえで納得したり、共感したりしたときに「伝わった」となる(「受け手」が複数の場合は、このコミュニケーションが個別に複数箇所で起こる)。

(『伝え方--伝えたいことを、伝えてはいけない。』より)
これが伝えるコミュニケーションの本当の姿です。講演などでぼくがいきなりこの構図の話をすると、「いったん表現する」という部分に戸惑う人もいます。いや、自分はそんなたいそうなことはしていない、と。
でも、冷静に考えるとわかるように、人から人へ、なにかを“直接”伝達することはできません。
そんなことができるのは、テレパシーが存在するSFの世界だけです。現実の人と人とのコミュニケーションは、かならずなにかを媒介しておこなわれます。
文字によるコミュニケーションなら、紙やデジタルデバイス上などに表示された言葉や文章。話すコミュニケーションなら、声として発した言葉や話がその役割をにないます。映像にしても、デザインにしてもそうでしょう。あるいは事業などにもあてはまることかもしれません。
なにかを伝えるコミュニケーションはすべて、「伝え手」が伝える事柄をいったん表現し、「受け手」がそれを見聞きする、という2段階のプロセスを経ています。
別の言い方をすると、伝えるコミュニケーションは、「表現する」と「見聞きしてもらう(文章でいえば「読んでもらう」、お話でいえば「聞いてもらう」)」という2つの行為から成り立っているということ。
コミュニケーションの橋はひとつではなく、2つあるのです。
伝えたいことが伝わらない理由
でも、なぜこの構造だと「伝えたいこと」がすんなりと伝わらなくなるのでしょうか。いちばんのポイントは「第2の橋」にあります。
伝え手としては、伝えるからには受け手との間にコミュニケーションを成り立たせたい。にもかかわらず、この「第2の橋」を伝え手自身で架けることができないのです。
たとえば、先ほどお話しした子どもへの説教であれば、親は子どもに対して、「勉強しないと、ろくなおとなになれない」「自分は勉強しなかったことを後悔している」などと伝えたいと思っている。その考えを、思いをこめて、言葉を選んで、自分なりにきちんと「表現する」ところまでやったとしましょう(第1の橋を架けた)。
でも、その話を子どもが聞いてくれるどうか(第2の橋が架かるかどうか)は、また別の話です。
もちろん「聞いてほしい」とお願いすれば、耳を傾けてくれるかもしれませんが、それでも最後までしっかりと聞いてくれる、意識を向けて話につきあってくれるという保証はどこにもありません。
「話を聞く」という行為を伝え手が強制することはできませんし、仮に強制的に聞かせることができたとしても、真剣に聞くかどうかは受け手次第。受け手が決めることです。
受け手はその話を聞くこともできますが、聞くのをやめることも自由にできる。伝え手にとって大切な話であろうが、思いがつまっていようが、そんなことは(シビアな言い方をすれば)受け手には関係がありません。基本的には、受け手自身が聞こうと思えば聞くけれど、聞きたくなければやめてしまう。
ほとんどの伝えるコミュニケーションは、受け手がある程度の時間や労力、注意力などを割いて、読んだり、聞いたりしてくれなければ、「納得」はおろか、「理解」にもたどり着くことができません。
にもかかわらず、伝え手にできるのは、表現するところ(第1の橋)まで。受け手の関与(第2の橋)を確実なものにすることができないのです。
いわば、伝えるコミュニケーションの主導権は、伝え手ではなく受け手にあるということ。ここに伝えることの難しさ、伝えるコミュニケーションの構造的な課題があります。
受け手自身が聞こうと思えば聞くけれど、聞きたくなければやめてしまう──。伝え手の立場で考えると身勝手にも思える話ですが、なんのことはない、これはふだん私たちが誰しもやっていることです。
すべては「受け手」次第
とくにわかりやすいのは、テキストとのかかわりでしょう。
日々、スマートフォンをのぞきこみながら、私たちはニュースアプリやポータルサイト、SNSなどでたくさんの記事に出合います。あるいは企業に属している人なら、会議資料や企画書、報告書、メールなど、膨大なテキストを手にします。
振り返ってみるとわかることですが、そのすべてを読んでいる人はまずいないはずです。しっかり読むものもあれば、ななめ読みするものもあるでしょうし、少し読みかけてやめたり、タイトルだけ見て読まないものもあったりする。
先ほどの「話を聞く」と同じで、「読もうと思えば読むが、読みたくなければやめてしまう」。それをくり返しています。
そのとき私たちは受け手として、なにを思い、どう判断しているのか。

情報に出くわすたびにまず、それが自分にとって「知りたいこと」や「聞きたいこと」「読みたいこと」なのかどうかを品定めするような目で見ているはずです。そのフィルターに引っかかるようであれば、かかわってみる。そうでなければ、かかわらない。
ここからわかるのは、受け手が受け入れるのは、伝え手が「伝えたいこと」ではなく、自分が「伝えられたいこと」だということです。
そして、当然のことながら、伝え手の「伝えたいこと」と受け手の「伝えられたいこと」は、かならずしも同じではありません。「伝えたいこと」を伝えても、受け入れられない可能性が高い。
伝えるコミュニケーションの構造から考えると、「伝えたいこと」を伝えてもすんなりと伝わらないのは、当然のことなのです。
「伝わる」ようにしたいなら、ひとことで言いあらわす時点で、相手(受け手)が納得して、あわよくば共感するような「伝えられたいこと」へと、「伝えたいこと」を変換する意識が重要になります。
(松永 光弘 : 編集家)








