日本人が「外資系オフィス」に馴染みにくい理由

侮れない島型オフィスのメリット(写真:ふじよ/PIXTA)
新型コロナウイルス感染症の拡大によって多くの企業でリモートワークが導入され、ここ数年でオフィスのあり方は大きく見直された。その結果、ゆとりあるオフィスやフリーアドレス、サテライトオフィスなど、働く場所の多様化が進んだのは間違いない。
一方で、イギリスの経営学者リンダ・グラットンが新著『リデザイン・ワーク 新しい働き方』で述べているように、「オフィスで過ごす時間が減ったことを歓迎している反面、それが自分の未来にどのような影響を及ぼすのかという不安も感じている」人も多いのではないだろうか。
そうしたオフィスの多様化についてコロナ禍以前から研究してきたのが、オフィス空間のデザインを手がけているオカムラだ。前回の記事に続き、本記事では、オカムラの働き方コンサルティング事業部で所長を務める川口健太氏とチーフリサーチャーを務める池田晃一氏に、「日本人のオフィスに対する価値観」に焦点をあてながら、「これからのオフィスのあり方」について語ってもらった。
オフィスは「管理する」時代から「投資する」時代へ
――オフィスに対する企業の感覚はどのように変化していますか。
川口健太氏(以下、川口):かつて、オフィスについて私たちが依頼を受ける方たちは、企業の総務部でした。つまり、施設を管理している部署です。しかし今は、人事部や経営企画部、新規事業推進部が増えています。
オフィスを管理していた時代から、ビジネス改革の文脈で、「オフィスにどう投資するか」へと意識が変化しているのです。
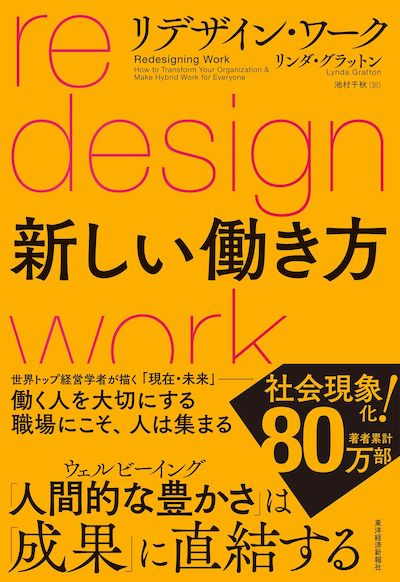
池田晃一氏(以下、池田):オフィス作りに関わる方は、本当に多様になりました。
オフィスは環境に良くなければならないという観点や、みんなが不公平感を持たずに快適に働ける空間にするにはどうするか、というダイバーシティの観点で、サステナビリティ担当の方やコンプライアンス担当の方が入るケースも増えています。
高齢の方、身体の不自由な方がオフィスにいることも増え、スロープや段差について考えるようになりましたし、外国人向けに英語のサインを考えるなど、細かく配慮して作るところが、かつてとはまったく違います。
弊社では、働く人、個人個人がその日の仕事や気分に合わせて場所を選ぶことができるABW(Activity Based Working)を推進してきましたし、働き方は人によって多様であるということを提唱してきました。コロナをきっかけとして、社会がそれに気がつき、認め合うという流れが加速したと感じます。
――管理から投資へ、デザイン面ではどのように変化していますか。
池田:昔のオフィスは、コスト重視でしたから、1つの箱の中にできる限り大人数を詰め込みたいと考え、同じ机をザーッと並べていました。
しかし、今のオフィスは全員が出社しなくなったこともあり、オフィス空間に余裕が生まれてきています。そして、家具もデスクとイスが並ぶだけではなく、ソファが導入されたり、通路なのか、何かを置くのか、用途がわかりづらいエリアがオフィス内にたくさん生まれています。
弊社では、さまざまな企業の全国のオフィスで床面積あたりの家具占有率のデータを20年以上取り続けています。
家具占有率は、40%を超えると息苦しくなるのですが、近年はそれを下回っていますから、そこにいる人は居心地よく感じられていると思います。
経営者からすれば、「なんだかわからない空間があるから削れ」と思うかもしれませんが、働いている人にとっては快適というデータがあるのです。
日本人ならではのオフィスの価値観
川口:ただし、日本人は、ゆとりの空間を使うことが苦手ではありますね。通路の真ん中に置いてあるソファスペースに座る人は、あまりいません。注目されているように感じたり、サボっているように見られる気がして困るのでしょう。
欧州では、教会前のプラザにある段差などに腰を掛けておしゃべりする日常風景がありますが、日本ではそのようなことは少ない傾向にあります。
しかし、これからは、「あんなふうに座っていいんだ」「私は私で、違った使い方をしていいんだ」と思えるようなキーワードがでてきて、変わっていくのではないかと期待はしています。
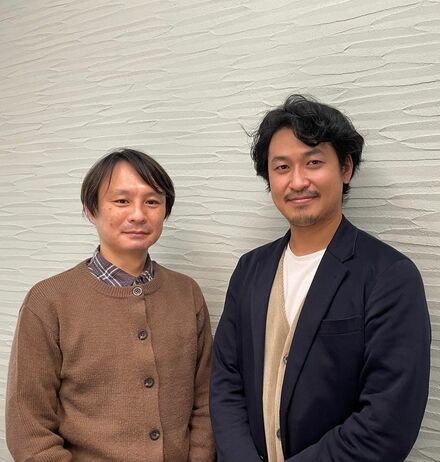
オカムラ池田晃一氏(写真左)、川口健太氏(写真右)(写真:筆者提供)
池田:日本的なオフィスにも価値はあると思います。心理学用語で「支援行為」と言いますが、日本人は他の人を助けようという感覚で、仕事を成り立たせる傾向があります。リンダ・グラットンは著書の中で、集合型オフィスには「協力」を引き出すという優位性があると述べていますが、日本人の価値観ともマッチしていますね。
欧米では、「アドバイスはマネージャーの仕事だ」と考えられていますが、日本人は、マネージャーに限らず支援行為の国民性がありますから、「困っている人がいるなら、アドバイスするのは当然のことだ」と考えます。
そうした価値観を失わないためにも、ある一定の頻度でオフィスに出てきて、顔を合わせる必要があると考えられます。
テレワークがデメリットになりうるケース
池田:私は2015年からテレワークの研究をしていますが、組織に入って間もない人や、スキルが追いつかない人、転職したばかりの人は、テレワークを控えたほうがよいのではないかという視点もあります。
リンダ・グラットンも言うように、オフィスの最大の役割は、「ほかの人たちとつながること」です。やはり、周りに人がいて、すぐ支援行為を受けられる環境でないと、会社のカルチャーもわかりません。困っていても、チャットやテレビ会議の画面からだけでは、その度合いが伝わらないところもあります。
ですから、その人に応じて、例えば「週4日出社して、先輩から仕事を習いましょう」というようなルールがあってもいいかもしれません。
また、コロナ禍の長期化が私たちに与える影響を調査した弊社のデータからは、コロナによって、40代後半〜50代の中高年が心身ともにダメージを受けていることもわかっています。
誰にも弱音が言えない世代で、以前は飲みに行ったり、ゴルフに行ったりしてストレスを解消していましたが、コロナでそれもできなくなり、自分の中にため込んでしまうのです。
――通勤がなくなって、運動不足になっているという問題もありますね。
池田:それはテレワークが原因というよりは、コロナの拡大が原因です。本来のテレワークは、運動不足にはなりませんし、体に悪いものでもありません。
テレワークとは、自宅、会社、それからコワーキングスペースやサテライトオフィス、図書館などを移動しながら働くということで、自宅というのは、あくまでも選択肢の1つでしかありません。
ところが今は、コロナが原因で、在宅を強制されるようなテレワークになっています。弊社が定点観測的に行っている調査では「自宅は働きにくい」と感じている人が3割程度います。
家族もいますし、特に子供がいると仕事になりません。また、1人暮らしの狭い部屋では働きづらいという悩みもあります。
弊社は、そういった人たちに配慮して、シェアオフィスを都内でいくつか契約していますが、現状、テレワークをしている人の2割ほどが利用するにとどまっています。
しかし、今後、いよいよ本当のテレワークが始まれば、シェアオフィスの利用も普通のことになり、働きたい場所で働けることで気持ちはラクになり、心身ともにメリットが出てくるでしょう。
「オフィス」と「シェアオフィス」の市場競争
池田:今、「オフィスvsシェアオフィス」という観点も出てきています。シェアオフィスは、お茶やお菓子があり、インテリアも良くて、コンシェルジュがいたりもして快適なんですね。それで、オフィスに来なくなるわけです(苦笑)。
そこで経営者が、シェアオフィスに負けないオフィスにして、社員が「自分はもてなされている」と感じるようにしようと考え、より上質な空間になるという流れがあります。
川口:ホスピタリティ、企業らしさ、そして、コミュニティ。それが、オフィスデザインのキーワードですね。自社オフィスを、シェアオフィスと同じぐらい居心地のいい場所にすれば、そこにしかないコミュニティができて、人が集まる。これは大きな差になります。
一方、シェアオフィスには、そこにしかない社外のコミュニティがあるかもしれません。そして、自宅周辺の地域コミュニティの存在もあります。それぞれにちょっとずつ属しながら働くというのは、副業やサバティカルにつながる話ですし、人材の多様性にもつながりますね。
キャリアも考え方も多様になれば、イノベーションにつながります。そういう大きなストーリーの中で、いま「働く」ということが考えられており、決して、1社の取り組みだけでできる話ではないことは明らかだと思います。
まだまだ変革期です。フレキシブルに変わっていける組織や、ルール作りが今後の主題になるでしょう。
(構成 泉美木蘭)
(川口 健太 : オカムラ働き方コンサルティングセンター所長)
(池田 晃一 : オカムラワークデザイン研究所チーフリサーチャー)



