成城石井の上場計画がこれほどまで話題になる訳

意外と知られていない「独特なスーパー」の本当の強さとは?(撮影:今井 康一)
ビッグニュースが飛び込んできた。成長著しいスーパー・成城石井の新規株式上場が検討されているというのだ。早ければ2023年2月期中に東京証券取引所に申請、2024年2月期のプライム市場上場を目指すという。時価総額は2000億円を超える可能性がある。
その成長力を考えれば、十分に考えられることだろう。新型コロナウイルスの感染拡大で大きな影響を受けた日本経済だったが、巣ごもり需要などでスーパーマーケットには大きな追い風が吹いた。とりわけ成城石井は大きく業績を伸ばした。
コロナ禍で成長を加速し、売り上げは10年前の2倍
2020年2月期の売上高は931億円だったが、2021年2月期には前年比10.7%増と2ケタ成長を達成し、売上高が1000億円の大台を突破。2022年2月期には1086億円を売り上げている。実は2013年度の売上高は500億円超だった。つまり、10年ほどで売上高を2倍以上に伸ばしたことになる。店舗数もほぼ倍増して今や193店舗だ。
なぜ、これほどまでに成城石井は支持されているのか。筆者には成城石井について『成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか?』『成城石井 世界の果てまで、買い付けに。』の2冊の著書があるが、その答えのひとつは、何よりその品揃えの独特さということになるだろう。
輸入商材、隠れた名品、地方の名産品をはじめ、独自商材が極めて多いのだ。ワイン、チーズ、生ハム、紅茶、コーヒー、オリーブオイル、ジャム、味噌、牛乳、納豆、昆布、鰹節、ダシ、チーズケーキなどなど、有名なメーカーのものも置いてあるが、成城石井でしかお目にかかれない商品も多い。買うときの選択肢が極めて幅広いのである。
例えば、チーズにしても、ウォッシュチーズ、白カビチーズ、フレッシュチーズ、ハードチーズなど、世界のチーズが入っている。紅茶の棚には天井近いところから下のほうまで、これでもかというほどに国内外の逸品が並んでいる。ジャム、醤油、だしなども同様だ。
直輸入品が多いのは、成城石井が貿易会社を持っていることが大きい。まだ1店舗だった時代から、商社などに任せず、バイヤーが直に世界の商品を探し出し、買い付けてきたのだ。これは、国内も同様である。
野菜や果物の売り場が違うのは、大部分が生産者から直接仕入れる産地直送だからかもしれない。国内でとれたばかりの瑞々しい野菜に加えて、アスパラなど海外から空輸されてきた旬のものもある。
足を伸ばして豆腐、納豆、キムチなどの売り場に行ってみると、さりげなく成城石井の名前が入っていたりする。「オリジナル商品」と呼ばれている、成城石井が信頼できるメーカーと共同で作った、一般的にプライベートブランドと呼ばれる商品だ。これも、バイヤーが手がける。
ただ輸入したものを並べるだけでない細やかさ
お菓子のコーナーでも海外製のものは多い。ただ輸入したものを店頭に並べるだけではない。輸入品はワンパックの量が多く、包装は日本のクオリティのほうが高いため、小分けして自社で包装し直しているものもある。そんな細やかさも支持されている。
実は和菓子もラインナップが豊富だ。お菓子コーナーには地方の隠れた銘品がずらり。ここにもオリジナル商品がたくさん含まれていたりする。輸入もののイメージが強い成城石井だが、実は和のものも人気なのだ。
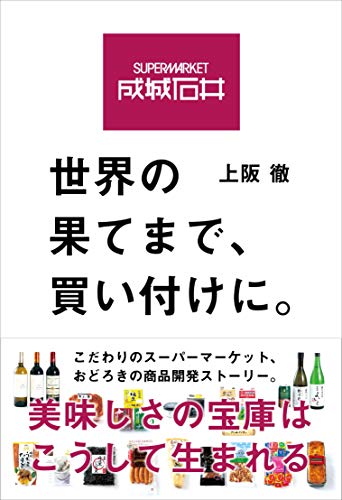
さらに成城石井で評価が高いのが、セントラルキッチンと呼ばれる自社工場で製造された自家製惣菜だ。一般的なスーパーやコンビニとは品揃えはまるで違う。和食、洋食、中華だけでなく、大ヒット商品「フォー・ガー」など、なんとエスニック料理まである。
一般的なスーパーは数百坪の敷地面積があり、バックヤードを持っていて、そこで惣菜の準備が行われることが多い。製造は基本的に外注され、バックヤードで簡単に加工し、店頭に出しやすい商品開発が行われている。開封して盛りつけるだけ、冷凍品をレンジであたためるだけ、揚げるだけ、が基本メニューだ。
だが、成城石井の店舗は、一部の大型店を除き、基本的にバックヤードで調理や加工はしない。まだ6店しかなかった時代に、惣菜を作る食品工場「セントラルキッチン」を自社で立ち上げたのだ。
このセントラルキッチンが、成城石井で展開される惣菜やスイーツのほとんどすべてを作っている。外注ではなく、自社製造なのだ。しかも、惣菜開発の中心を担うのは、元有名ホテルや有名レストラン、有名スイーツ店のプロフェッショナルたち。
いってみれば、一流の料理人がスーパーの惣菜を作っているのである。ほとんどが手作りで準備され、パッケージされ、各地の店頭に並ぶのだ。
実はこれこそが成城石井の店舗エリアが限られている理由でもある。配送できないエリアでは、惣菜が展開できないのである。だが、逆に新たなセントラルキッチンができれば、店舗拡大のポテンシャルは大きいということになる。
大人気の本場ドイツの製法を今も守る自家製ソーセージや成城石井の看板商品ともいわれ、年間120万本以上売れるというプレミアムチーズケーキをはじめ、人気のスイーツもセントラルキッチンで作られている。
食品しかり惣菜しかり、置いてある商品がまったく違うのが、成城石井なのだ。しかも一流のものが揃っていながら、実はお手頃な値段設定になっている。だから、わかっている人は、こういうことになる。
「これだけいいものなら、この値段は決して高くない」
「高級スーパー」という呼び名が好ましくない理由
テレビなどでは高級スーパーと紹介されることも多い成城石井だが、実はこの言葉は好まない。なぜなら、高級スーパーを作ろうとしてきたわけではまったくないからだ。筆者は成城石井にまつわる書籍の制作にあたって、原昭彦社長にも取材を重ねたが、興味深い言葉を耳にしている。
「成城石井というお店は、成城のお客さまに育てていただいたんです」
成城石井のルーツは、1927年2月に誕生した果物、缶詰、菓子を行う食品店だった。創業の地は東京・世田谷区成城。後に、都内屈指の高級住宅地となる。
「時代の最先端を切り拓いてこられた経営者や文化人も多い。早くから海外を経験されている方もたくさんいらっしゃいました。そこで商売をするとは、どういうことか。世界でいいモノを見てこられた目の肥えた方々の視線に、常にさらされ続けたということです」
本物志向で妥協しない人たちに対して、いいものをいかにお値打ちで出せるか。商売としては、これが問われ続けたのだ。高級なものを扱おうとしたのではない。
「お客さまが求めるものに、お客さまの期待に、どうやって応えることができるか。それをずっと考え続けてきたのが、成城石井でした。本当においしいものをお客さまに提供するためにできることをとことん突き詰めることこそ、成城石井のDNAなんです。そこで妥協は許されない。それでは成城のお客さまには、認めていただけないからです」
変遷を経て今はローソンが親会社に
そしてこのDNAをそのままに、少しずつ店舗が拡大していった。成城石井ブランドが広く知られるようになれば、幅広い顧客から期待が高まる。成城石井を作り出したのは、実は顧客だったのだ。顧客が求めるものを追求してきたら、今の成城石井になったというのである。
今回の上場のニュースで、成城石井の親会社がローソンだったことに驚いた人も少なくなかったようだ。実は2004年、スーパー成城石井の礎を築き、繁盛店に仕立てあげたオーナーが、成城石井の株式をベンチャー企業に売却した。
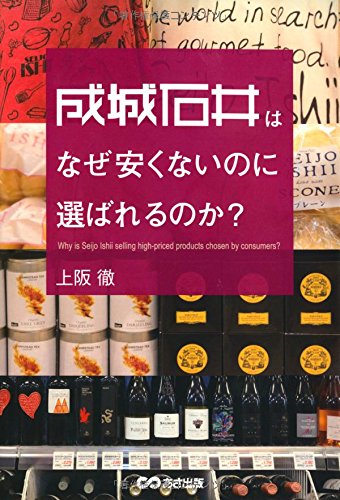
だが、親会社とのシナジーは生み出せなかった。何より親会社の持っている食のイメージと、成城石井のイメージが合致しなかった。その後、親会社はファンドのアドバンテッジパートナーズ、さらには三菱系のファンド丸の内キャピタルが設立した新会社へと変わる。さらに2014年、三菱商事グループのローソンが親会社となった。
ローソンは子会社化した直後から、成城石井の経営体制を変更しないことを宣言していたが、その通りの関係が続いている。成城石井ブランドなどの事業基盤を重視しながら、成城石井と協業関係を築いてきた。成城石井の近年の躍進の背景には、親会社との良好な関係も大きいだろう。
かつて親会社を持たなかった時代、その高収益、高成長ぶりからIPOがたびたび噂されてきたのが、成城石井だった。スーパー業界における超注目株となることは、まず間違いない。
(上阪 徹 : ブックライター)



