竹中流ベーシックインカムはどこが問題なのか

ベーシックインカムにはさまざまな議論があるが(イラスト:tiquitaca / PIXTA)
ベーシックインカムの議論が盛り上がっている。きっかけは、2001年からの小泉純一郎内閣で経済財政政策担当大臣・金融担当大臣に就任、日本の金融システム建て直しに力を振るったとされる竹中平蔵氏の最近の発言にあるようだ。まずは氏の発言を伝えるインタビュー記事を読んでみよう。
「これまでの現金給付は、消費刺激効果がなかったと言われるが間違いだ。これは景気刺激策ではなく、生活救済策だ。10万円の給付はうれしいが、1回では将来への不安も残るだろう。例えば、月に5万円を国民全員に差し上げたらどうか。その代わりマイナンバー取得を義務付け、所得が一定以上の人には後で返してもらう。これはベーシックインカム(最低所得保障)といえる。実現すれば、生活保護や年金給付が必要なくなる。年金を今まで積み立てた人はどうなるのかという問題が残るが、後で考えればいい」(週刊エコノミスト誌6月2日号『コロナ危機の経済学』より)
追記しておくと、この発言のうち「月に5万円」の部分は、9月のテレビ番組(BS-TBS)出演では「月に7万円」に増額されているようだが、さすがに元経済財政政策担当大臣の発言である。彼の一声で、これまではやや理念的に議論されてきただけの感があったベーシックインカム論、にわかにコロナ後の社会におけるセーフティネットのあり方として舞台中央に進出してきた感もある。
ちなみに「月に7万円」とはずいぶん塩辛い数字だが、日本の生活保護の平均月額支給額約15万円の半分は医療費支給という現状などから見ると、この金額辺りが「生活」というよりは「生存」のための最低ラインとは言えるかもしれない。
どうだろう、読者は竹中提案に賛成だろうか。
コロナ禍で注目されたベーシックインカム
まずは、ベーシックインカムそのものについて簡単に解説しておこう。すべての国民あるいは市民や住民に一定の金額を、他の条件とかかわりなく、つまりお金持ちにも貧乏人にも、元気に働ける人にもそうでない人にも、政府が一定の金額を一律に給付する、というものだ。
この考え方の歴史は古い。ものの本によると、発想の源は米国独立戦争当時の思想家トマス・ペインにまでさかのぼるとされている。近年は、グローバリズムがもたらした格差拡大や経済成長の陰での貧困深刻化に対する問題意識もあって注目度が高まっている。2017年には、フィンランドやカナダのオンタリオ州で、一種の「社会実験」としてではあるが、一定地域に一律の現金支給を行うなどの試みなどがあった。
それを加速させたのが今回のコロナ禍である。本年5月のスペインでは、ベーシックインカムの名の下に、200万人を超える生活困窮者を対象とする現金支給政策が開始されている。スペインの政策には受給に生活困窮などの条件が付いているので、こんなものはベーシックインカムでないという批判もあるようだ。それはさておき、たとえばドイツやスコットランドなどでも導入を求める動きが起こっている。日本の全国民一律10万円給付も、ベーシックインカムという旗印こそ掲げていないが、実質的にはスペインの例よりはベーシックインカムに近いといえる。
とはいえ、「毎月7万円をベーシックインカムとして全国民に支給」などと言われると、心配になる向きも少なくあるまい。心配の種は、こうした政策が「働かないこと」への報奨になるのではないかという点、そして「財源」をどうするのかという点、大きくはこの2点だろう。
もっとも、前者つまりベーシックインカムが働かないことへの報奨になるという点については、そうでもないはずという議論もできる。
「効率的な生活支援策」とはいえる
理屈が好きな経済学者の間でこそ通用するような話なのだが、「人頭税の効率性」とでも呼べそうな命題がある。個々の人の資産や所得の状況にかかわりなく一律同額の税金を取り立てるのが人頭税だが、そうした税金のほうが、たとえば労働することで得られる報酬の多寡に応じて課税する所得税より、労働市場での取引に対する介入の度合いが小さく、したがって市場メカニズムの効率性が最大限発揮されるなどと論ずるのである。
ところで、この議論とパラレルに考えると、ベーシックインカム推進派の主張もあながちナンセンスではなくなる面がある。なぜなら、人頭税が最も効率的な税ならば、マイナスの人頭税とも言えるベーシックインカムは最も効率的な生活支援策ということになるからだ。この辺り、その資産効果は、というようなことまで考え始めるとあまり単純でない面もありそうなのだが、その種の面倒な話はほどほどにしよう。
海外で行われた「ベーシックインカム実験」の結果などをみると、一律現金支給で人々が働かなくなるという現象は、少なくとも短期的には観察されていないようだ。だから、今のコロナ禍という現実に対してベーシックインカムに答を見いだそうとすること、それ自体はナンセンスではない。
では、竹中提案に問題はないのか。そんなことはない。その第1は、彼の提案がそもそもベーシックインカムにすらなっていないところにある。
もう一度、彼の発言を伝える記事を読んでみよう。彼は、自身の提案をベーシックインカムだと言いながら、他方で「所得が一定以上の人には後で返してもらう」と付け加えている。しかし、いったん給付しながら後で返してもらうというのでは、政府による生活資金貸付と同じことだ。単純な貸付と違うのは「所得が一定以上の人には」という条件が付いていることだが、そんな条件を付けても、彼の提案がベーシックインカムになっていないことに変わりはない。
住宅資金を借りて後で返済する住宅ローン(モーゲージ)の順番を逆にして、住宅を担保に生活資金を借りて後で住宅を売って返済するローン商品を、「リバースモーゲージ」と呼ぶ。その用語法を借りれば、竹中提案は要するに「リバース年金保険」であって、ベーシックインカムなどではないことになる。彼の提案の本質は、ベーシックインカムつまり全国民対象の無償現金給付ではなく、全国民を網に掛ける強制的国営金融プランの一種なのである。
「後で返してもらう」ことの問題点
そして、ベーシックインカムを金融プランにすり替えてしまうことは別の問題を生む。それが金融関係者ならおなじみの「モラルハザード問題」である。ベーシックインカムで給付を得た人が「所得が一定以上なら返してもらう」などと言われたらどうだろう。カネをもらうのはうれしいが、もらったカネを返すのは嫌だ、だから、後で働くのはほどほどにしておこうという気分も生じそうだ。
これがモラルハザードでなくて何だろうか。もちろん、かつての金融危機でモラルハザード問題と格闘した実績のある竹中元大臣のことだ。きっとここには深い考えがあるのだろう。できたら、それを聞かせていただきたいものである。
そして、もう1つ。ここでの竹中氏、給付の財源についてどう考えているのだろうか。そこもわからない点である。必要になる資金は軽く見過ごせるような規模ではない。日本の人口は1億2000万人超だから、生活ではなく生存ぎりぎりラインのはずの1人当たり月額7万円給付でも、総費用は何と年額100兆円を超える。これは現在の一般会計規模にも匹敵する大きさである。それを論じないままで「全国民に一律定額給付」などと言ってほしくない。
この点、竹中氏へのインタビュー記事には生活保護と年金をまとめて縮小あるいは廃止して財源とすることを考えているような節がある。だが、これまた気になる点である。生活保護をベーシックインカムに吸収するという話なら聞いたことがあるが、年金保険をベーシックインカムに吸収などというのはありえない筋と言うほかはない。
厚生年金であれ国民年金であれ、そこに積み立てられている資産は年金制度に参加していた人々が過去に積み立てた汗の結晶であり、国家が人々に贈与を行うための準備資産などではない。生活保護と年金は別のものなのだ。それを混同して「年金を今まで積み立てた人はどうなるのかという問題が残るが、後で考えればいい」などと片付けてしまっては、日本という「国のかたち」が変わってしまう。
ベーシックインカムを政策メニューに入れるのなら、私自身の前回寄稿『菅義偉は安倍晋三のような悪代官になれるのか』(9月30日付)でも書いたように、消費税と法人税あるいは個人所得税との関係整理など、税制全体の全面的な再デザインが必要になるはずなのである。
財源と税制改革の議論なしに語れない
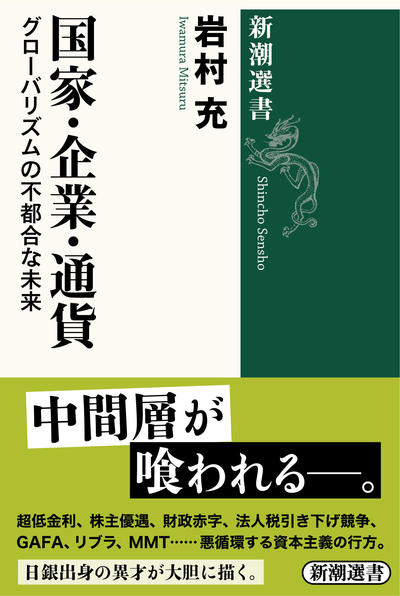
私がベーシックインカムに関する議論を聞くときいつも思うのは、それを唱えるのなら、財源つまり税の問題とセットで議論すべきだということである。
ベーシックインカムとは直接的対価なき政府による給付であり、税とは直接的対価なき政府による賦課である。ベーシックインカムと税とは、どちらも政府と家計との間での市場外における経済価値の強制移転であり、向きが反対になっているだけのコインの表裏なのだ。
繰り返しになるが、ベーシックインカムを唱えるのなら、提唱者が財源をどう確保しようと思っているのか、年金をいじるのではなく税制全体をどう変えようと思っているのか、それを明らかにして世に問うてほしいものである。
ベーシックインカムにおけるさまざまな問題については、私も拙著『国家・企業・通貨』(2020年2月・新潮選書)で今後の国家のあり方とも絡めてやや懐疑的な見方から、他の観点も含めて議論をしているので、ご関心のある方は読んでいただきたい。



