なぜ「掃除・片づけ」が人生に関わるのか-1-
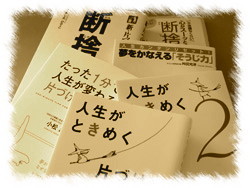
■TOPIC-1 片づけ本はベストセラーの常連
ここ3、4年のベストセラーランキングをみると、「片づけ」に関する書籍が毎年ランクインしていることに気がつきます。
「かたづけ士」小松易さんの『たった1分で人生が変わる片づけの習慣』、片づけコンサルタント・近藤麻理恵さんの『人生がときめく片づけの魔法』および同書2巻、クラター・コンサルタントのやましたひでこさんによる『新・片づけ術 断捨離』と『不思議なくらい心がスーッとする断捨離』がそれです。書店に行けば、彼(女)らの他の著作、別の書き手による片づけ本、あるいは掃除本をいくつかみつけることができます。
掃除や片づけで人生が変わる、心がスーッとする。分かるような、分からないような気がしますよね。確かに掃除や片づけをすれば物がすっきりし、心もスーッとするという話は何となく分かる。しかし、人生が変わるというのは、どういうことなのか。今週は今挙げた著作を紐解いて、掃除や片づけで人生が変わる、という論理の構造を考えてみたいと思います。
あらかじめ述べておくと、以下で主に述べていくのは、掃除や片づけの具体的な方法ではありません。方法をつぶさにみていくとあまりに煩雑になるということもありますが、社会学を学ぶ私が考えてみたいのは、(1)掃除や片づけという事象にどのような意味が込められているか、(2)それはかつてと今で違うのか、(3)違うとしたらそれはいつ頃どのように変わったのか、ということだからです。このような意図があるため、以下では著者が持つ、掃除や片づけについての「哲学」のような部分に注目していくこととします。
■「そんなまさか」→「事実なのです」という常套手段
論点を1つ足してから、話を進めていきたいと思います。前回テーマ「手帳術」と同様に、掃除や片づけでも「夢がかなう」ということがしばしばいわれます。この「夢」という言葉にもう少しこだわってみたいので、今週の対象書籍として、書籍タイトル上に夢と掃除を初めて同時に用いた著作を加えることにします。その著作とは、2005年の「そうじ研究会代表」舛田光洋さんによる、『夢をかなえる「そうじ力」』です。刊行年が最も早いので、この著作からまずみていくこととします。
舛田さんは同書の冒頭で次のように述べます。「そうじには“力"があります。その力を使ってそうじをすると、確実に効果があらわれます。その効果とは、人生におけるさまざまな悩みや問題の好転、事業の繁栄、幸せな家庭、夢の実現……。『えーっ!? そんなまさかー』と思われるでしょうが、事実なのです。この力を『そうじ力』と私は名付けました」(1p)。「誰でもできる簡単な『そうじ』で、人生が変わるのです」(2p)。
えーっ!? そんなまさかー……でも事実なのです、というロジックは自己啓発書の常套手段ですが、まずは舛田さんの主張にもう少し寄り添ってみましょう。その主張は非常にシンプルで、「あなたの住む部屋が、あなた自身である」「あなたの心の状態、そして人生までもを、あなたの部屋があらわしている」(15p)、だから部屋をきれいにすることが心をきれいにすることにつながる、心がきれいになれば人生は好転する、というものが基本線です。
この主張の補助線となるのが、「磁場」や「エネルギー」についての主張です。まず磁場についてはこうです。「あなたの心の反映であるあなたの部屋に、一定の『磁場』ができ上がり、あなたが発しているエネルギーと同質のものを引き寄せる」ため、「部屋のキレイな人はさらに幸せが倍増し、部屋が汚い人は不幸な出来事をさらに増幅させている」(19p)。エネルギーについては、「そうじ力」の2つの側面とともに次のように述べられます。「積極的に汚れを取り除くことによって、マイナスのエネルギーを取り除き、問題を解決する『マイナスを取り除くそうじ力』」と、それを土台として「さらに積極的に目的を持ったプラスエネルギーを加えることで、強力に善きものを引き寄せるのが『プラスを引き寄せるそうじ力』」(39-40p)。
このような観点から、マイナスのエネルギーになるものを捨てよう、心から感謝の気持ちを込めて掃除をすることで「宇宙の繁栄のエネルギー」(100p)を得よう(プラスのエネルギーを得よう)といったハウ・トゥと、掃除を重視する組織がいかに成功しているか(ディズニーランド等)という事例が示される、というのが舛田さんの著作です。
さて、舛田さんの主張について、共感する方、途中までは何となくわかるけれど磁場やエネルギーの話あたりからはついていけないと思った方、まったくついていけないと思った方、それぞれいると思います。しかしここではひとまず、近年のベストセラーの概観を続けていくこととします。
■「片づけで人生が変わる」ロジック
冒頭で示した、ベストセラーとなった片づけ本では、宇宙の繁栄云々というような、人智を超えたいわば「スピリチュアル」なことがらへの言及はほとんど見られなくなります(やましたさんの著作に、ほんの少しだけ出てきますが)。
まず小松さんの『たった1分で人生が変わる片づけの習慣』をみていきます。小松さんは、「片づけるということは、過去に経験したことや体験したことに『かたをつける』」ことだと述べます。ただの「整理整頓」ではすぐに元通りになってしまうため、この「かたをつける片づけ」をしなければならないというのです。そして小松さんはこの「片づけ」によって、「現在の自分が変わり、『自分の思い描いている未来』を手に入れることができるように」なると述べます(15-17、31p)。
自分が変わるという点について、もう少し具体的に解説します。小松さんによると、片づけを始めるとぶつかる壁の一つが「『何を捨てて、何を残すか』『何が必要で何が不必要か』の線引き」だといいます。そして、この「線引きができない人は、『人生において何をしたいのか、が明確になっていない』」のだと続きます。このような意味で小松さんは、「『生きること』と『片づけ』は同じ」なのだと述べ、片づけを始めるにあたってはまず「自分は人生で何をするのか?」という「あなたのテーマ」を決める必要があるのだというのです(17、35p)。仮にテーマが見つからなくても、今述べたような線引きをしながら片づけを進めていくことで、「余計なものが排除されて、本当に大切なもの」が浮かび上がり、「埋もれていた『本当にやりたいこと』」が見つかるとも小松さんは述べます(36-37p)。
また、小松さんが述べる「出す→分ける→減らす→しまう」という「片づけの基本動作」は、仕事の流れと同様だとされます。つまり、「やってくる案件に対して、優先順位を決め、何をどうするか判断し、減らして」いくという流れと同じだというのです。このような観点から、「できる人に片づけ上手が多い」といわれるのは、片づけに限らず、また仕事に限らず、このような基本動作が「習慣化」されているためだと説明されます(45p)。また、だからこそ片づけを身につけた人とそうでない人で、人生における差が徐々に広がっていくのだとも述べられます(16p)。
次に、近藤さんの『人生がときめく片づけの魔法』について見ていきます(同書には2巻がありますが、これは第一作の発展編・応用編にあたり、近藤さんの基本的な主張は第一作でほぼ出揃っています)。同書の冒頭では、近藤さんの示す片づけ法は「一度片づけたら、絶対に元に戻らない方法」だと述べられます。「正しい手順」で、「一気に、短期に、完璧に」、「劇的に」片づけることが近藤さんの示す方法のポイントです。そして近藤さんは、劇的な片づけの結果、「その人の考え方や生き方、そして人生までが劇的に変わってしまう」ことになると述べます(1-3p)。
なぜ片づけで人生が変わるのでしょうか。近藤さんによればこうです。「ひと言でいうと、片づけをしたことで『過去に片をつけた』から。その結果、人生で何が必要で何がいらないか、何をやるべきで何をやめるべきかが、はっきりと分かるようになるのです」(4p)。
率直にいって、小松さんとまったく同じだといえますが、もう少しみていきましょう。近藤さんの示す片づけ法は、「たんなる片づけノウハウではない」といいます。というのは、片づけという行為自体は単純なものですが、片づけの成否を分けるのは、片づける習慣や意識といった精神面に原因がある——つまり「片づけはマインドが九割」だと近藤さんが考えるためです。そのため近藤さんの示す片づけ法は、「いわゆる物理的な整理収納ノウハウではなく、片づけにおける正しいマインドを身につけて、『片づけられる人』になるための方法」ということになるのです。そして近藤さんは、本当に大事なのは収納法等ではなく、「その人自身の生活に対する意識や考え方であり、『何に囲まれて生きたいか』というきわめて個人的な価値観」にこそあると述べます(6-7p)。
今述べた部分もほぼ小松さんと同様のものだといえますが、近藤さんの主張の特異性はこの先にあります。具体的には捨てる基準についての話がそれで、小松さんが述べる基準は「使う/使わない」(123p)という必要性にもとづく基準であるのに対し、近藤さんが示す基準は「モノを一つひとつ手にとり、ときめくモノは残し、ときめかないモノは捨てる」、つまり「持っていて幸せかどうか」「持っていて心がときめくかどうか」という、感情がより重視された基準となっています(62-63p)。「ときめくかどうか。心にたずねたときの、その感情を信じてください。その感情を信じて行動すると、本当に信じられないくらい、いろんなことがどんどんつながりはじめ、人生が劇的に変化していきます。まるで、人生に魔法がかかったかのように」(170p)というわけです。
また、近藤さんが片づけの結果としてイメージするゴールも、仕事ができる人を事例に持ち出す小松さんとは幾分異なるように思われます。近藤さん自身の「平穏で幸せな生活」の描写は次のようなものです。
「清らかな空気が流れる静かな空間で、あったかいハーブティーをカップに注ぎながら、今日一日を振り返る至福の時間。まわりを見渡すと、壁には海外で買ったお気に入りの絵がかかっていて、部屋の隅にはかわいいお花が生けてあります。そんなに広くはなくてもときめくモノしか置かれていない部屋で過ごす生活は、私をとっても幸せな気持ちにしてくれます」(49-50p)。
必要なものではなく、好きなもの(ときめくもの)に囲まれ、幸せな気持ちになれる生活——。ところで、なぜ好きなものに囲まれた生活が推奨されるのでしょうか。近藤さんは「部屋着」に関する箇所で次のように述べています。「誰に見られるわけでもない、だからこそ、最高に自分がときめく部屋着に着替えて、自分のセルフイメージが高まるようにするべきだと思いませんか」(98p)。近藤さん自身、著作の執筆時点で、自分自身に自信がないと述べています。しかし、自分の環境、つまり「本当に大好きで愛おしくて大切で、素晴らしいものに囲まれて生きている」ことには自信があり、「自分がときめくモノたちや人たちに支えられている。だからこそ、自分はだいじょうぶ」だと考えられるとも述べています(236p)。つまり、片づけの効用として、自己肯定する、自分を好きになることがあるというわけです。このような観点は小松さんには見られないものでした。
■「よくある言い方」と「誰も述べていなかったこと」
最後は、やましたさんの「断捨離」です。以下ではやましたさん初の単著であり、その基本的な構想が示されている『新・片づけ術 断捨離』を見ていくこととします。やましたさんによれば、断捨離とは「『断』=入ってくる要らないモノを断つ」「『捨』=家にはびこるガラクタを捨てる」という行動と、その結果訪れる「『離』=モノへの執着から離れ、ゆとりある“自在"の空間にいる私」という状態を組み合わせて作られた言葉です(6p)。そして断捨離は全体として、次のように定義されます。
「モノの片づけを通して自分を知り、心の混沌を整理して人生を快適にする行動技術」(5p)
つまり、モノの取捨選択を通して自らの価値観をはっきりさせるという、これまでに見てきた片づけ観が、やましたさんにおいても中核的な発想とされています。他にも、以下のような言及があります。
「いかに自分が、モノに時間と空間そして維持・管理するエネルギーを与えてしまっていたか。(中略)断捨離ではそれを取り戻そうと言っています」(31p)
「『もったいない』『使えるか』『使えないか』などのモノを軸とした考え方ではなく、『このモノは自分にふさわしいか』という問いかけ、つまり主役は『モノ』ではなく『自分』」(6p)
「断捨離することで『本当の自分を知ることができ、好きになれる』感覚が得られることが最大のメリットです」(25p)
「『清々しい場=聖なる空間』をキープする」(8p)
エネルギーという比喩を用いている点は舛田さん、自己分析を重視する点は小松さん、自らの感覚を重視し、自己肯定を目的の一つとし、自らを囲う自分だけの空間というイメージをもつ(モノが溜まった状態はヘドロの溜まった池や腐敗というイメージで語られ、片づけが行き届いた状態はアユの住む清流に例えられます)といった点は近藤さんと、それぞれ重複するものだといえます。ここまでで、近年の掃除・片づけ本の主張は大体つかんでいただけたかと思います。
しかしやましたさんの主張も多くの点で、これまでの著作にはみられない特徴をもっています。まず、断捨離の着想は、やましたさんが高野山の宿坊に行った際に考えたことや、ヨガ道場で学んだ「断行」「捨行」「離行」という執着から離れるための行法哲学に端を発するものです。つまり明確に、修行というイメージで断捨離という片づけ法は構想されているのです。
また、「自分とモノとの関係性」を結び直すという観点を打ち出し、「モノの奴隷状態」から「モノをコントロールできる」状態へ移行させようとする態度もまた、やましたさんの主張の一つの特異性だと考えられます(39p)。ただ減らすのではなく、モノに対するコントロール能力、モノに対する主体性を確立しようとするのが断捨離なのです。だからこそ断捨離は、ただモノを捨て、節約を謳うばかりではなく、主体的に「どんどん旬のモノを取り入れて」いくことも推奨するのです。これは、旬のモノを楽しんで食べ、あるいは身につけることは「エネルギーの強い」ものを自らの内に積極的に取り入れるためだと説明されています(174p)。
さて、ここまでざっと近年の代表的な掃除・片づけ本について見てきました。掃除(きれいにすること)と片づけ(捨てること)でその主眼は異なりますが、いずれの著作でも、些細な日常の行動が人生と自分を変えられるのだとする点では共通しています。
まずいっておきたいのは、このような掃除・片づけの効用は、20年ほど遡ると、ほとんど誰も述べていなかったということです。掃除・片づけが人生を変える、夢をかなえる、自己分析や自己肯定に役立つといった主張は、今聞くと何となくそうかもしれないと思うかもしれませんが、ごく近年になってみられるようになったものなのです。
では、こうした近年の主張は、紹介してきたような著者の独創性によるものなのでしょうか。率直にいえば、答えはノーです。たとえば舛田さんが述べた、磁場やエネルギーについての話は、特に舛田さんばかりがしている話ではありません。これまであまりとりあげてはこなかったのですが、こうした人智を超えた何ものかとのつながり、いわば「スピリチュアル」な領域への言及は、自己啓発書を読んでいくと、しばしば出合うものです。
ベストセラー上でその系譜をたどれば、1995年に410万部を売り上げた大ベストセラー、医師・春山茂雄さんによる『脳内革命』も「創造主の意志」(30p)に言及していました。春山さんは経営コンサルタント・船井幸雄さんから影響を受けたと述べており(3p)、こうした系譜はさらに遡ることができます。
近藤さんややましたさんに見られる、自分だけの空間を作るという発想も、2004年のベストセラーである原田真裕美さんの『自分のまわりにいいことがいっぱい起こる本』にみることができます。「バリヤのようなエネルギーに守られた『清浄な自分の空間』」で自らを守ろうという発想です(34p)。
また、日常生活を自己啓発の素材にしていこうとする点では、今までの連載で幾度も述べてきた「日常生活の『自己のテクノロジー』化」という観点が、各著作にもそのまま当てはまるといえます。また、近藤さんややましたさんの著作が、「自分らしさ」や「自分を好きになること」に志向している点でも、第7テーマの女性向け自己啓発書と重複するような向きがあります。
しかし、こう述べてきたからといって、今回紹介した著作が、すべて誰かの著作の焼き直しだというつもりはありません。私は第6テーマ「セルフブランディング」の最後で、自己啓発書とは「差別化に差別化が重ねられていき、それを俯瞰して見ると、あるいは時を置いてみると自動運動しているように見える」メディアだと述べました。掃除・片づけ本についても考えていることは同様です。
このような考え方から掃除・片づけ本に関して取り組んでみたいのは、非常に単純なことです。これらのベストセラーの、何が新しいのか。何が先行する言論から引き継がれ、何が新たに生み出されたのか。これは、第8テーマ「手帳術」の最後で示した「どのように」のアプローチ(http://president.jp/articles/-/9111)を、さまざまな隣接ジャンルの観察を伴いながら実際に試してみるということでもあります。
具体的なチェックポイントを示しておきましょう。(1)掃除や片づけを自己啓発に結びつける着想のルーツはどこか(TOPIC-2)。(2)人生を変える、夢をかなえる、自分らしさを実現するといった個別の着想はいつ頃、誰によって、どのように示されたのか(TOPIC-3)。(3)掃除・片づけ本と隣接するジャンルの動向は影響しているのか(TOPIC-4)。次週から、これらの消化に入りたいと思います。
----------
『人生カンタンリセット! 夢をかなえる「そうじ力」』
舛田 光洋/総合法令出版/2005年
『たった1分で人生が変わる 片づけの習慣』
小松 易/中経出版/2009年
『新・片づけ術 断捨離』
やました ひでこ/マガジンハウス/2009年
『人生がときめく片づけの魔法』
近藤 麻理恵/サンマーク出版/2010年
『人生がときめく片づけの魔法2』
近藤 麻理恵/サンマーク出版/2012年
『不思議なくらい心がスーッとする断捨離』
やました ひでこ/三笠書房/2011年
----------
(牧野 智和=文)


