池澤春菜に父・池澤夏樹が語りかける「生れて間もないおまえはまだおぼえている」


「詩」の部で、池澤夏樹は41人の作者を選んだ。池澤さんは小説家のイメージが強いけど、まず翻訳家、ついで詩人としてのデビューのほうが早い。
近代詩「定番」のコンピレーション

まずは〈まだあげ初〔そ〕めし前髪の〉で始まる島崎藤村(1872-1943)の『若菜集』(1897)所収「初恋」に始まって、生年順に西脇順三郎、三好達治、石垣りん、田村隆一らを経て荒川洋治の(1949-)の『ヒロイン』(1986)所収「空」まで、38人の作者の、ひとり1〜5篇、計72タイトルが、2段組で収録されている。近代詩のサンプラーだ。

「解説」で選者自身が下記のように述べるとおり、このセレクトの特色は2点。
・〈多くは広く知られたアンソロジー・ピースである〉
・〈選んだ後で振り返ってみれば、堀口大學や佐藤春夫などのウィットに富んで軽いいわゆるライト・ヴァースが多くなった〉

僕のような門外漢から見ると、近代・現代詩を「詩人という特殊な個人のひとりごと」だとどうしても感じてしまうところがある。
でもそういう側面だけ見るのはきっと偏見というもので、この巻を読んでわかったのは、詩人は言葉の「共同体の共有物」としての性格を、各自の方法でしっかり活かそうとしているのだ。

意外に知ってるフレーズがある
日本の近代文学には130年程度の、しかもかなり無理のある歴史しかないとはいうものの、それでも愛誦性のある詩のワンフレーズワンフレーズが、けっこう蓄積してきている。さっきの〈まだあげ初めし前髪の〉を筆頭に、
・小諸なる古城のほとり/雲白く遊子悲しむ(藤村『落梅集』[1901]より「小諸なる古城のほとり」)
・しづかにきしれ四輪馬車、(萩原朔太郎『月に吠える』[1917]より「天景」)
・さんま苦いか塩〔しよ〕つぱいか。(佐藤春夫『我が一九二二年』[1923]より「秋刀魚の歌」)
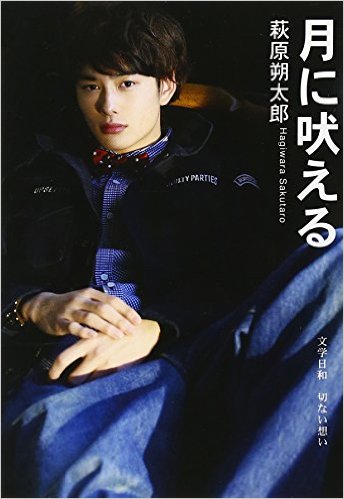
・てふてふが一匹韃靼海峡を渡つて行つた。(安西冬衛『軍艦茉莉』[1929]より「春」)
・汚れつちまつた悲しみに/今日も小雪の降りかかる(中原中也『山羊の歌』[1934]より「汚れつちまつた悲しみに……」)
・辛よ さようなら/金よ さようなら(中野重治『中野重治詩集』[1935]より「雨の降る品川駅」)

・ハナニアラシノタトヘモアルゾ/「サヨナラ」ダケガ人生ダ(于武陵(810-?)「勧酒」井伏鱒二訳、『厄除け詩集』[1937]所収)
・わたしが一番きれいだったとき/わたしはとてもふしあわせ(茨木のり子『見えない配達夫』[1958]より「わたしが一番きれいだったとき」)
・四人の僧侶/庭園をそぞろ歩き/ときに黒い布を巻き上げる(吉岡実『僧侶』[1958]より「僧侶」)
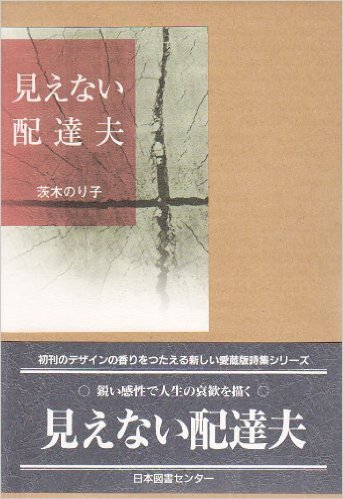
「詩、ぜんぜん知らないしなあ」
と思っていたけど、それでもこういったワンフレーズは、僕のような凡夫でも(しばしば、作者や題名を忘れた形で)、
「そういえばなんとなく聞いたことがあるかも……」
と思ってしまうのだ。
家族のことが詩になるケース
だから奇を衒わず、敷居を低く下げてくれたチョイスがありがたい。
いや、〈広く知られたアンソロジー・ピース〉を敢えて拾うこと自体は、ひょっとしたら「奇」なことかもしれないけど。
(とはいえ池澤セレクトには変わったところもあって、哲学者・批評家の鶴見俊輔の詩も選ばれている)
あとおもしろかったのが、67頁から70頁にかけて、
・あこよ あこよ/大きな声じゃ言えないが/とりよりにだけは気を許すな(『岩田宏詩集』[1968]所収「吾子〔あこ〕に免許皆伝」
・なくときは/くちあいて/はんかちもって/なきなさい(辻征夫『かぜのひきかた』[1987]所収「桃の節句に次女に訓示」)
・生れて間もないおまえはまだおぼえている/ついこのあいだまでいた世界の匂いとざわめきを。(池澤夏樹『最も長い河に関する省察』[1982]所収「午後の歌 娘に」)

と、親が子どもに向けて語りかける詩が4頁連続で掲載されていること。
〈生れて間もない〉池澤春菜さんが、〈ついこのあいだまでいた〉(=胎内の? 前世の?)〈世界の匂いとざわめきを〉〈まだおぼえている〉。なんかいいなあ。
詩(集)3冊まるごと収録
38人のコンピレーションのあとに、以下の3冊(3作)がまるごと収録された。
・谷川俊太郎『タラマイカ偽書残闕〔ざんけつ〕』(1978)
・高橋睦郎『姉の島 宗宗像神話による家族史の試み』(1995)
・入沢康夫『わが出雲・わが鎮魂』(1968)

『姉の島』は12篇(章?)、『わが出雲・わが鎮魂』は13篇(章?)から成る長詩で、いずれも自分のファミリーヒストリーや島根旅行といった私的な題材に『古事記』や『風土記』といった古代の神話・地誌が上書きされていく。どちらにも天照(あまてらす)と素戔嗚(すさのを)の姉弟関係が出てくる。
どちらも、作者自身の自註がついている。『わが出雲・わが鎮魂』なんて、註のほうが「本体」の何倍もの字数がある。

こういうのは本来、読者(とくに後世の学者)がやってきた作業。古典だったりすると、註釈こみでこそおもしろく読めるということが多い。
本全集の編集方針で第2巻の和歌や第12巻の連句、第11巻のいとうせいこう訳『通言総籬〔つうげんそうまがき〕』など、註や鑑賞文(つまり批評)ごと作品にアプローチしてもらう設計になっているのは、敷居が下がって大いに助かる。
でもT・S・エリオットの『荒地』以来、現代詩では自註というのもひとつの大きな「方法」であるらしい。

この自註はなかなかうるさくもある。「このフレーズは『古事記』のアレを踏まえて書いている」とか、「このフレーズはだれそれのなんとかいう詩のパロディ」とか。
下手すると衒学的なしたり顔に見えたり、虚仮威しに見えたりしかねない。敷居が下がるとは単純には言えない。
これはこう読め、ここに感心しろ、とこちらの読みを規定してくるので息苦しい。
最初の38人コンピレーションが楽しくて、いい気になってこれから現代詩に入門しようかという気になっていた僕には、読むのは少したいへんだった。
それでもこれは、作者が詩を読者に手渡す苦肉の策のひとつなのだ。
あの註がなかったらもう、当方の教養の程度と連想力のなさでは、読解はそこでお手上げになってしまう。だから、この註はやっぱり親切なのだ。
よくわかった。現代詩ってだいへんだったのだ。
この、ニコニコ動画のアップロード主(うp主)がひとりでコメントまで全部やっているような寂しさに恐れをなして、僕を含む多くの一般人は現代詩を手に取らない。
けど今回読んでみて、この寂しさ、読者を暑苦しく引っ張っていこうとする熱気も含めて、たしかに強い魅力、引力があることを感じた。
「それはなにもわかってない!」と言われてもこれではしょうがないですね……。
架空翻訳という設定
11篇の詩と無題の序文からなる『タラマイカ偽書残闕』も自註がついているが、この自註はまったく意味が違う。
これは他のふたつの詩集と違って、僕ら一般読者にも馴染のある手法だった。
この詩集はある民族に伝わる歌を集めて翻訳したという体裁をとっている。つまり偽書だ。だから註も序文もフィクションなのだ。
架空の作者による長詩と、架空の註釈者による厖大な註・序文・索引から成るヴラジーミル・ナボコフの小説『青白い炎』は、『タラマイカ偽書残闕』刊行時には未訳だったが、構造はほぼ同じだ。

このように露骨にフィクションの手続きを取ってくれたら、こちらも緊張が解ける。
日本人が日本人の名で発表する文学作品には、文壇・詩壇という世間からの圧力をつねに受けている。
そこに不自由さ息苦しさを感じる作者が、翻訳を遊戯的に擬態する。架空翻訳という設定は、いとうせいこうの『存在しない小説』でもよく効いていた。
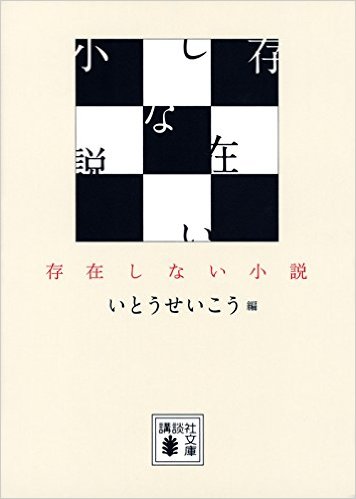
本巻は近代詩の敷居をグッと下げてくれたので、詩への苦手意識がようやく解消しつつある。嬉しいアンソロジーでした。
七五調と日本人
気になったことがある。
本稿で抜き書きした近代詩ワンフレーズのなかの、七五調・五七調率が高いのだ。
日本語の拍節では、メロディのない言葉だけの詩のばあい、七五調以外の詩は愛誦性を持ちにくい。
第2次大戦後、「短歌的叙情」なるものが戦争と結びついてしまったことを、日本人は知ってしまった。七五調である程度の長さを持つと、軍歌っぽくなってしまう。
そのせいか詩の世界では、大正時代から続いてきた「七五調離れ」が、戦後に一気に加速した感がある。
それでも演歌や校歌や交通標語の多くは近年まで七五調を手放さなかったし、さらにむかしは童謡やアニソン(「ゆけゆけ飛雄馬」など)まで七五調優勢だった。昭和末期の小学生は「どんぐりころころ」と「あゝ人生に涙あり」(どちらも七五調のヴァリエーションである八五調)の歌詞を入れ替えて歌ったものだった。

時代遅れのように見なされながら圧倒的な強さを持つ(だからこそ危険でダサくもある)そんな七五調の近代については、本巻の「短歌」「俳句」に収録された500の歌句でスキャンすることができる。これについては稿を改めるべきだろう。
(千野帽子)







