即興小説からオウムの村井評伝まで。初の大阪文学フリマレポ
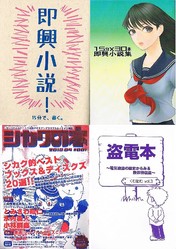
これに続き、今度の日曜、4月28日には千葉市の幕張メッセでのイベント「ニコニコ超会議2」の一環として「超文学フリマ」が開催予定だ。私としては2002年の第1回以来、ほぼ欠かさず文フリに出店してきただけに、両方とも参加したいのはやまやまだったが、交通費などを考えると立て続けに出店するのはちょっと難しいなあ……と悩んだ末、結局、住んでいる愛知から近いうえ、大阪でも南部にはまだ行ったことがないとの個人的な理由から、「文学フリマin大阪」のほうに参加することに決めた。
文フリが始まった当初は、参加サークルのうち評論系に対し創作系が若干優勢だったが、最近では両者はだいたい半々で、会場を二分していた。それが今回は、評論系よりも創作系がちょっと多いかなという印象。規模からいっても、今回の文学フリマは初期の頃を思い出させて、ちょっと懐かしかった。
さてエキレビでは今回もまた、恒例の文学フリマで見つけたおすすめ本の紹介をお届けしたい。いつもはライターがおのおの選んだ本を紹介しているが、今回の大阪には、エキレビからは私(近藤)だけの参加となった。したがって、以下にとりあげるのは、すべて私が単独で選んだものである。なお、各紹介の冒頭には本のタイトルとともに、カッコ内にその本を販売していたサークル名を示した。
■『即興小説! 15分で、書く。』(八月科)、『15分×30本 即興小説集』(方程式が解けない)
文学フリマでは毎回、どうしても評論系のサークルをメインに回ってしまう自分。それは創作系、とくに小説は、立ち読みだけでは正直買おうかどうか躊躇してしまうところがあるからなのだが、そこへ来て今回、小説サークルにある傾向というか、新たなムーブメントが起きつつあることに気づいた。それは「即興小説」だ。私が見つけたかぎりでは、2つのサークルがそれぞれ『即興小説!』と『15分×30本 即興小説集』という本を販売していた。
そのそもそもの発信源は「即興小説トレーニング」というサイトらしい。参加者はそこで出されるお題に沿って、制限時間内(自分で選ぶことができる)に即興で小説を書くというルールだ。上記2冊も、同サイトに参加した個人が、自分で書いた小説をまとめたものであった。
小説というのは、作品それ自体で完結してしまいがちで、外に向ってストレートに訴えかけることがなかなか難しい表現ジャンルだと思う。それも一発芸的な即興小説なら、作品として未完成なところがある分、読者が「自分ならこう書くかも」などとツッコミを入れたり、働きかける余地が生まれる。さらにネットを飛び出し、文学フリマという場と結びつくことで、新たな化学反応も期待できそうだ。
■『シカクの本』(シカク出版)
大阪・中津にて自費出版物を扱っている「シカク」というお店の本。今回の文フリにあわせて刊行された#001では、「特集 この作家はおもしろい!」や「シカク的ベストブックス&ディスクズ20選!!」といった企画を通して、シカクで扱っている本・CDや、そのつくり手たちが紹介されている。「ベストブックス」のなかには、『めぐりコンプリート』『鬼畜ヤリマン道場!』と、これまでエキレビでもとりあげてきた本もあるけれど、知らなかったものも多々あり。全国各地の市営施設を探訪するという『しのそのへ』というミニコミとかすごく気になる!
特集のインタビューには、エキレビでもおなじみのとみさわ昭仁さんが、古書店「マニタ書房」店主・人喰い映画研究家として登場(エキレビライターではこのほか香山哲さんも編集に協力していたりする)。いずれの記事からも、この商品を、この人をプッシュしたい! という熱意がビンビン伝わってくる。
■『盗電本〜電気窃盗の歴史からみる無体物窃盗〜』(くむ組む)
タイトルからは、アングラなマニュアル本を想像するかもしれないが、さにあらず。その内容は、電気という形のないものを盗むことがなぜ犯罪とされるのか、その法的根拠を探るというもの。さらに、電気以外のエネルギー(たとえば、他人のストーブを勝手に使って洗濯物を乾かしたら、熱を盗んだことになるのか?)や、いわゆる「デジタル万引き」のような情報の窃盗に関しても話はおよぶ。そもそも著者のクムさんがこの冊子をまとめたのは、情報窃盗を考えるためにも、同じ無体物である電気窃盗についてまとめておくことは有意義だろうと考えたからだとか。法律の条文や過去の判例を引っ張り出して、細かく検証しているところに「文学」を感じる。
■『YUTORI TIMES いまから、数の話をしよう。』(TNBG)
文学フリマは、どっちかというと……いや、あきらかに文系寄りのイベントなのだが、そのなかにあって目を惹いたのが、数学についていろんな人たちがエッセイを寄せたこの本。執筆者は、数学を仕事などで使ってきた人、数学が大嫌いで二度とかかわりたくない人などさまざまだ。とくに面白かったのは、数学が苦手なはずなのに、なぜか塾で教えているという高村暦さんの「詐欺師のための数学指導入門」という一編。「苦手だけど、数学の奥に隠された秘密には興味がある」との一文には、共感を覚える文系人間も案外多いのでは?
■『余所見』0号(出版取次 大浜屋)
ウェブサイト「余所見」と連動した紙の雑誌を創刊するにあたり、その準備号として配布されたタブロイド判のフリーペーパー。なかでも「チケットパーティー」という企画が面白かった。これは、参加メンバーがそれぞれ手元に残していたチケットを持ち寄り、それにまつわる思い出を語るというもの。見開き2ページにわたり並べられたチケットは、ミュージアムや展覧会の入場券、あるいは航空券や鉄道の切符などじつに多種多様だ。友人知人とこんなふうにチケット自慢ができたら面白いかもしれない。
■『おかまノート―対話編』(おかま研究会(仮))
男性のライトさんと、「おかま」のポチのすけさんによる対話集。「おかま」というと普通、女性の心を持った男性を想像してしまうが、ポチのすけさんは逆で、女性の身体を持って生まれながら、男性の心を持つ。この本では「対話編」とあるとおり、ライトさんの質問や考えに対し、ポチのすけさんが自分自身を顧みながらそれに答えていくという形をとっている。
それによると、ポチのすけさんは、性同一性障害の診断を受けているという。だが、意外というべきか、むしろ性同一性障害という言葉を知ったからこそ、自分の性別について悩みを抱くようになったかもしれないとも語る。性同一性障害やトランスジェンダーといった言葉は社会的にかなり浸透したが、そう呼ばれる人たちには(当然といえば当然だが)けっして十把一絡げにできない、それぞれ異なる事情も存在するということだろう。
なお、この本では、本人がそう名乗っていることを理由に「おかま」という語が使われているが、人によっては差別的なニュアンスで使われたり受けとめられたりもするので、注意が必要だ。
■『滅亡SF』(大阪大学SF研究会)
地元、阪大のSF研究会の評論集。マヤ暦で地球滅亡が予言されていた2012年の発行ということで、地球や人類が滅亡するSF作品についてレビューを収録している。さらに注目したいのは、ハルマゲドンからの救済を教義に掲げたオウム真理教について、同教団のナンバー2であり、一連のオウム事件のさなかに刺殺された村井秀夫の軌跡をたどった評伝だ。じつは村井は阪大の理学部物理学科出身で、この評伝の執筆者の松村さんは彼の後輩にあたる。評伝は主に新聞や雑誌に掲載された関係者の証言で構成されているのだが、ときおり松村さん自身の経験を踏まえつつ、物理学を学んだ村井がなぜオウムという妄想に取りつかれていったのか推測しているのが興味深い。
以上、8冊を紹介した。これ以外にも面白い本はたくさんあったのだが、スペースの都合から紹介しきれなかったのが残念である。
今回の「文学フリマin大阪」には、じつに約1600人の入場者があったという。ブースのなかから見ていてもたしかに、開場中ずっと人波が絶えず、盛況ぶりを実感できた。今回の開催に際しては東京の文学フリマ事務局とは別に、文学フリマ大阪事務局が開設され、今後はそちらを中心にして大阪開催が続けられていく予定だとか。今回の熱気が一回にとどまらず、今後も継続されるよう、当エキレビでも陰ながら応援していければと思う。(近藤正高)


