日テレ巨人戦中継、絶滅の危機|野球報道
巨人ファンだったことは一度もないが、小さいころからずっとナイター中継を見て育った。つまり巨人戦の中継を見ながら大きくなったのだ。
昨日のサンスポ
2014年度のプロ野球巨人戦中継について日本テレビは27日、地上波で放送する巨人主催試合のデーゲーム14試合のうち全国ネットは2試合にとどまり、12試合を関東ローカルで放送すると発表した。
13年度に地上波で放送したデーゲーム16試合は全国ネットだった。同局は「各地方の球団の試合放送がかなり爆発力を持っており、配慮した」と説明している。
地上波のナイター6試合は全国ネット、BS日テレは61試合を放送予定で、放送する試合数は13年度並みという。(共同)
要するに東京ドームでの巨人戦は、地上波では昼夜併せて8試合しか全国ネットをしないということだ。昨年は22試合だったから激減した。
視聴率が10%を割り込む中、スポンサーもつかない。系列局も巨人戦では数字が取れない。だから地上波での巨人戦中継は、開幕戦や優勝決定の試合など人気が出そうな試合を除いてやめにする、ということだ。
全盛期の巨人戦ナイターは平均でも20%以上の視聴率を誇る、日テレグループの看板番組だった。
全65試合の中継のみならず、甲子園での阪神巨人戦さえ中継した。「巨人戦の放映権」をちらつかせて、他局の間に割り込んだのだ。
9連覇の頃は、メインの解説者は佐々木信也だった。野球選手上がりとは思えない滑らかなしゃべり、当意即妙の返し。
アナウンサーの実況中継も華やかで、いかにも「一流」と言う感じがしたものだ。
よく言われるように、巨人は、「放映権料」を盾にとって他球団ににらみを利かせた。
セの5球団は、本拠地での「巨人戦の放映権料」で食っていたのだ。他球団のオーナーの中には「うちは2位でいい」という人さえ現れたものだ。
日本テレビ以外の民放も「巨人戦」こそがスポーツ系の最大の収入源だった。各局には専属の解説者がいたが、プロ野球解説とは「巨人戦の解説者」に他ならなかった。まさに「巨人にあらずんばプロ野球にあらず」という時代が長く続いたのだ。
この体制に風穴を開けたのは「プロ野球ニュース」だったと思うが、ここではそれには触れない。
巨人V9開始年以降の巨人戦の平均視聴率を見て行こう。
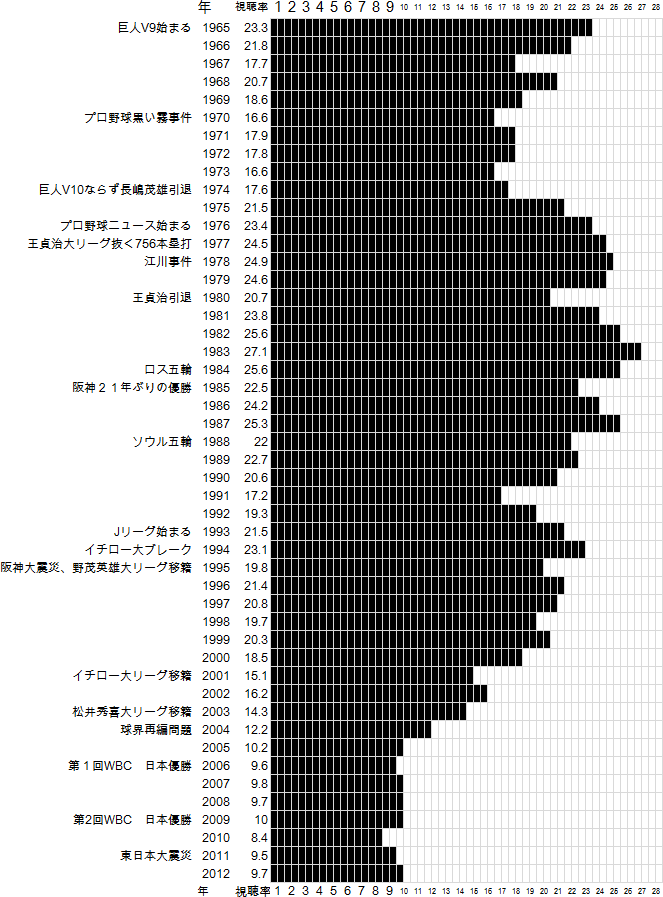
視聴率は1982年をピークに下降傾向となっている。この間、Jリーグが発足、サッカーが野球とならぶ人気スポーツコンテンツとなった。
また野茂英雄、イチローのMLB挑戦によって、野球ファンはNPB以外の野球にも目を向けるようになった。
要するにコンテンツの多様化の中で、地上波のプロ野球中継は凋落の一途をたどったのだ。
すでに巨人戦は「おわコン」ではあろう。
しかし一方で、BSやCS、ケーブルテレビなどのマルチチャネルでは、プロ野球中継は重要なコンテンツだ。
無料ではなく、金を払ってプロ野球を見ようと思うお客は、確実に存在するのだ。もっとも、それは地上波とは比較にならないほどの小さな数字だが。
こうした非地上波系のテレビでは、スポーツ中継はコアなファンを満足させるために専門的になりつつある。実況アナも解説者も、テレビ技術も試合をしっかりと伝えようという方向になりつつある。
放送の回数自体が少なくなり、視聴率も取れなくなった頃から、地上波でのプロ野球実況中継は、劣化が著しくなった。
バラエティかと見まごうようなタレントが出演したり、番宣を延々と流したり。
アナウンサーの試合を“伝える”能力も劣化し、安っぽいドラマを口先で作るようになった。いったい誰に向けて放送しているのかわからない、くだらない実況中継が多くなった。
このことが視聴率の低下に拍車をかけているのは言うまでもないことだ。
しかしながら、日本テレビは「巨人戦」で飯を食ってきたはずだ。言い方を変えれば「日本のプロ野球中継」の歴史は、日テレが切り拓いてきたはずだ。
讀賣グループ中興の祖である正力松太郎は、民放、プロ野球の生みの親だ。この二つを組み合わせることで、戦後の人々のライフスタイルを決定的に変えたのだ。
正力、日本テレビ、巨人が、戦後日本人の「原風景」を作ったといっても過言ではない。
今も巨人は「球界の盟主」を標榜している。力の源泉は「人気」であり、その具体的な数字は「視聴率」だったはずだ。それがなくなった今、巨人は何を以て「盟主」を名乗っているのか。
日本テレビは「プロ野球中継」「巨人戦」への恩義を感じるべきだ。
そして、退潮ムードに唯々諾々と従うのではなく、実況中継の改良や、コンテンツとしての売り方の改善などで、もう一度「地上波のプロ野球中継」を復活させる努力をすべきだ。
プロ野球ファンのすそ野を広げるためにも、もう一度奮起すべきだ。
昨日のサンスポ
2014年度のプロ野球巨人戦中継について日本テレビは27日、地上波で放送する巨人主催試合のデーゲーム14試合のうち全国ネットは2試合にとどまり、12試合を関東ローカルで放送すると発表した。
13年度に地上波で放送したデーゲーム16試合は全国ネットだった。同局は「各地方の球団の試合放送がかなり爆発力を持っており、配慮した」と説明している。
地上波のナイター6試合は全国ネット、BS日テレは61試合を放送予定で、放送する試合数は13年度並みという。(共同)
要するに東京ドームでの巨人戦は、地上波では昼夜併せて8試合しか全国ネットをしないということだ。昨年は22試合だったから激減した。
視聴率が10%を割り込む中、スポンサーもつかない。系列局も巨人戦では数字が取れない。だから地上波での巨人戦中継は、開幕戦や優勝決定の試合など人気が出そうな試合を除いてやめにする、ということだ。
全65試合の中継のみならず、甲子園での阪神巨人戦さえ中継した。「巨人戦の放映権」をちらつかせて、他局の間に割り込んだのだ。
9連覇の頃は、メインの解説者は佐々木信也だった。野球選手上がりとは思えない滑らかなしゃべり、当意即妙の返し。
アナウンサーの実況中継も華やかで、いかにも「一流」と言う感じがしたものだ。
よく言われるように、巨人は、「放映権料」を盾にとって他球団ににらみを利かせた。
セの5球団は、本拠地での「巨人戦の放映権料」で食っていたのだ。他球団のオーナーの中には「うちは2位でいい」という人さえ現れたものだ。
日本テレビ以外の民放も「巨人戦」こそがスポーツ系の最大の収入源だった。各局には専属の解説者がいたが、プロ野球解説とは「巨人戦の解説者」に他ならなかった。まさに「巨人にあらずんばプロ野球にあらず」という時代が長く続いたのだ。
この体制に風穴を開けたのは「プロ野球ニュース」だったと思うが、ここではそれには触れない。
巨人V9開始年以降の巨人戦の平均視聴率を見て行こう。
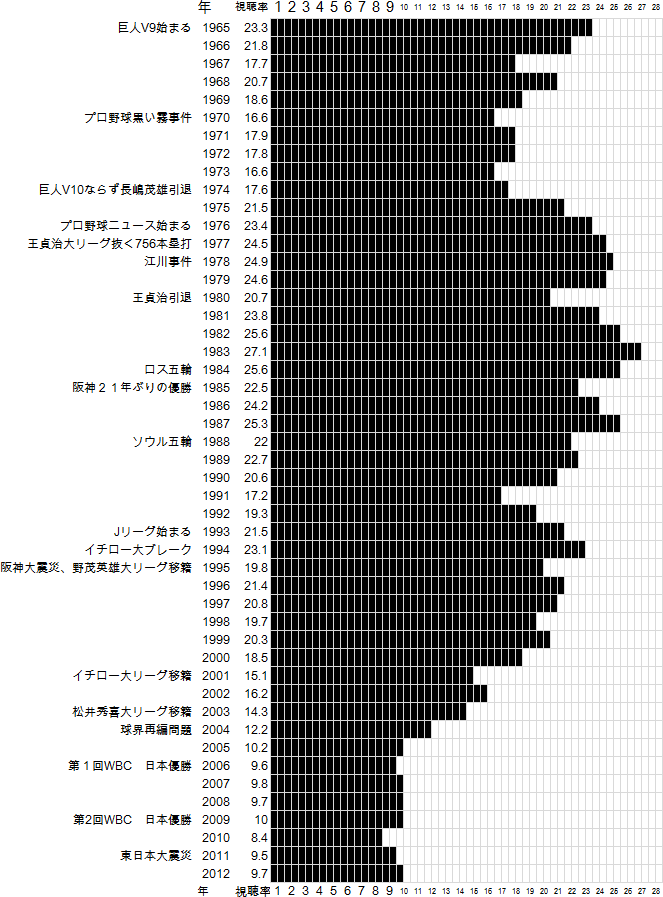
視聴率は1982年をピークに下降傾向となっている。この間、Jリーグが発足、サッカーが野球とならぶ人気スポーツコンテンツとなった。
また野茂英雄、イチローのMLB挑戦によって、野球ファンはNPB以外の野球にも目を向けるようになった。
要するにコンテンツの多様化の中で、地上波のプロ野球中継は凋落の一途をたどったのだ。
すでに巨人戦は「おわコン」ではあろう。
しかし一方で、BSやCS、ケーブルテレビなどのマルチチャネルでは、プロ野球中継は重要なコンテンツだ。
無料ではなく、金を払ってプロ野球を見ようと思うお客は、確実に存在するのだ。もっとも、それは地上波とは比較にならないほどの小さな数字だが。
こうした非地上波系のテレビでは、スポーツ中継はコアなファンを満足させるために専門的になりつつある。実況アナも解説者も、テレビ技術も試合をしっかりと伝えようという方向になりつつある。
放送の回数自体が少なくなり、視聴率も取れなくなった頃から、地上波でのプロ野球実況中継は、劣化が著しくなった。
バラエティかと見まごうようなタレントが出演したり、番宣を延々と流したり。
アナウンサーの試合を“伝える”能力も劣化し、安っぽいドラマを口先で作るようになった。いったい誰に向けて放送しているのかわからない、くだらない実況中継が多くなった。
このことが視聴率の低下に拍車をかけているのは言うまでもないことだ。
しかしながら、日本テレビは「巨人戦」で飯を食ってきたはずだ。言い方を変えれば「日本のプロ野球中継」の歴史は、日テレが切り拓いてきたはずだ。
讀賣グループ中興の祖である正力松太郎は、民放、プロ野球の生みの親だ。この二つを組み合わせることで、戦後の人々のライフスタイルを決定的に変えたのだ。
正力、日本テレビ、巨人が、戦後日本人の「原風景」を作ったといっても過言ではない。
今も巨人は「球界の盟主」を標榜している。力の源泉は「人気」であり、その具体的な数字は「視聴率」だったはずだ。それがなくなった今、巨人は何を以て「盟主」を名乗っているのか。
日本テレビは「プロ野球中継」「巨人戦」への恩義を感じるべきだ。
そして、退潮ムードに唯々諾々と従うのではなく、実況中継の改良や、コンテンツとしての売り方の改善などで、もう一度「地上波のプロ野球中継」を復活させる努力をすべきだ。
プロ野球ファンのすそ野を広げるためにも、もう一度奮起すべきだ。



