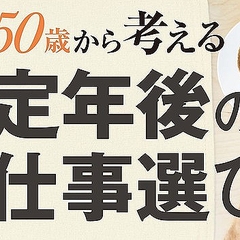定年後に稼げない人と稼げる人の決定的な差

50代を「リタイア準備の期間」にするか「生涯現役の始動期間にするか。そこで明暗が分かれるかもしれません(写真:Getty Images/ラテアート:門川 洋子)
大手広告代理店の関西支社に勤める浜田健児さん(仮名)は今年50歳。「最近、猛烈に焦りを感じている」という。「現場での自分の力量が40代をピークに落ちていっていると感じている。体力の衰えと同時に、以前なら一晩で仕上げられたことが終わらなくなっている。経験とコツと、人脈をフル活用してカバーしている」(浜田さん)。
不安の背景はそれだけではない。かつて東京に次ぐ2次経済圏だった関西だが、地元企業の東京への本社移転で地盤沈下が著しく、広告の仕事もじわじわ減っている。出世を続けるためには東京転勤が必須となる。だが、せっかく関西で築いた人脈も大事にしたい。
「定年後は地元の自治体や企業と協力して、日本観光の魅力を世界にアピールするような仕事がしたい」。そう考える浜田さんは、関西の人脈を頼って独立する道も探り始めている。ただ、今より収入が減ることを家族が認めるとは思えず、悩みは尽きない。
週刊東洋経済は9月25日発売号(9月30日号)で『50歳から考える定年後の仕事選び』を特集。従来の「リタイア準備」から「生涯現役への始動」へと50代に発想転換する、人や企業の動きを紹介している。
60歳以上で働く男性は20%
50代が不安に思う定年後の生活。実際、シニアはどのように過ごしているのか。週刊東洋経済はNTTコムリサーチの協力を得てアンケート調査を実施、60代以上の男性約600人の回答が寄せられた。

「定年を迎えたが現在も働いている」と答えたのは、60歳以上の20.7%。定年後も働き続ける理由は、「年金では足りない」「現在の生活水準を保つためには必須」など金銭面の必然性を挙げた人が5割を超えた。働き方としては、定年前と「同じ会社」「フルタイム」勤務がともに6割弱、ただし給与水準は8割以上が「下がった」と回答している。
日本で働く60歳以上の高齢者は2016年現在、1286万人に達している。2013年4月の改正高年齢者雇用安定法の施行で、企業は希望するすべての従業員に対し65歳までの雇用を確保するため、定年後再雇用、定年引き上げ、定年廃止のいずれかの措置を取らなければならなくなった。国はさらに定年の65歳以上への引き上げや定年廃止、希望者全員を66歳以上まで継続雇用する企業への補助金支給などで、「生涯現役社会」を強力に推進しようとしている。
これに対して多くの企業は慎重なスタンスを崩さない。厚生労働省の調査によれば、大企業(従業員301人以上)で定年延長や定年廃止に踏み切ったのは全体の1割に満たない。9割超が給与引き下げなど大幅な処遇見直しが可能な、定年後再雇用制度で対応している。
ある情報システム大手の人事部長は、「定年は従業員の処遇を大きく見直せる一大チャンス。このフリーハンドをみすみす手放すことはない。定年引き上げでも一定の処遇の見直しはできるが、再雇用に比べたら大きな変更は難しい」と話す。あるITサービスの人事部長も、「定年引き上げは全員一律で引き上げることへの不安は残る。やはり60歳で一度定年として、そこで再度仕切り直す機会があったほうが都合はよい」と本音を語る。
定年後の再雇用は給料大幅ダウンが一般的
ただ多くの大企業の定年後再雇用では、給与は現役時代の半額という一律の処遇で、仕事内容も現役社員の邪魔にならない程度の補助作業というのが一般的だ。50代半ばの「役職定年」で下がった待遇から、さらに大幅に引き下げられることになる。モチベーションが大幅に低下したシニアが社内に増えれば、後進の指導どころか職場に悪影響を与え、生産性にとってもマイナスでしかない。

生涯現役で働くということを想定しておかなければならない時代かもしれません(写真:naka / PIXTA)
こうした弊害を踏まえ、最近では処遇や役割を見直す動きも出始めている。大和証券の神戸支店に勤務する鶴野哲司さん(68)。1973年の入社以来、個人向け営業一筋で来た。東京・自由が丘を振り出しに、神奈川、宮崎、大阪など、支店を渡り歩いてきた。
現在の肩書は上席アドバイザー。大和証券独自の制度で、実績のあるベテラン営業員を対象に、原則転勤なしで自分の希望する支店で仕事を続けられるというものだ。60歳の定年以降、基本給は下がるが、賞与の算定基準は変わらない。証券会社の場合、基本給より賞与の額のほうが大きいので、年収はある程度の水準を確保できる。
2006年の制度導入当初、雇用延長は65歳までだったが、2013年に70歳まで引き上げられた。そして今年6月には上限年齢が撤廃された。「せっかく制度を見直してくれたのだから、70歳までは辞められない」と鶴野さんは笑う。大和証券がシニアスタッフの活用に力を入れる理由の1つが、社内の活性化だ。若手社員にとって、経験豊富なベテラン営業員は文字どおり、生きた教材。60歳以上の先輩が元気に働いていれば、若手だけでなく中堅社員にも刺激になる。
もう1つの理由が、高齢客との親和性だ。大和証券の主要顧客は60〜70代の高齢層。彼らにとっては、若手よりも自分と近いシニア営業員と話したほうが安心できる。特に相続など大きな課題が眼前に控えている場合、同じ年代だからこそ打ち明けられる悩みもある。転勤がなく、長い期間担当してくれるのも安心材料だ。
会社に頼らず、自ら新天地を開拓する選択肢もある。シニア起業や転職も活発になってきている。「サラリーマンは何かあったとき、すぐ病院に行けない」。父親が脳梗塞で倒れ要介護となったとき、当時50歳手前の橋詰登志夫さん(68)はそう思った。ヤマハでホールやスタジオの設備施工を担当し、朝6時に家を出て終電で帰る毎日だったが、父が要介護となったのをきっかけに、ホームヘルパー2級を取得。介護ビジネスの立ち上げを考えるようになった。
そこで見つけたのが介護タクシーだ。2005年に「むさしの介護タクシー」(現むさしのケアキャブ)を創業。当初は病院を回っても怪しい業者扱いされる始末だったが、今では順調に事業を拡大。依頼が多いときは同業に振り分けることほど繁盛している。

「50代で中小企業に転職すれば、60代でも管理職として働き続け、評価されれば65歳以降も重宝される」。再就職支援を行うパソナキャリアカンパニーの渡辺尚プレジデントは、シニア転職のメリットを語る。
「自分の強み」がないとシニア転職は難しい
シニアの転職で成功するのは、「自分の強みがはっきりしている人」(渡辺プレジデント)だ。証券会社の支店長で高い営業成績を上げた人、海外事業を一から立ち上げたり子会社再建に奮闘したりした人などがその典型。そのためにも「管理職となっても、現場のプレーヤー部分を少しでも残しておくことが重要」(同)とされる。
逆に転職が難しいのは「大企業の一部署にずっといたような人。変化対応力に欠けることが多い」(人材紹介のジェイエイシーリクルートメントの松園健社長)だとされる。リクルートワークス研究所の大久保幸夫所長によれば、「シニアが生き生き働く必要条件は、『無理なく』『役に立つ』こと」という。今いる会社で長く働くにせよ、起業や転職に踏み切るにせよ、覚えておきたいキーワードだ。
『週刊東洋経済』9月25日発売号(9月30日号)の特集は「50歳から考える定年後の仕事選び」です。