東大生断言「感情的な人ほど成績上がる」納得理由
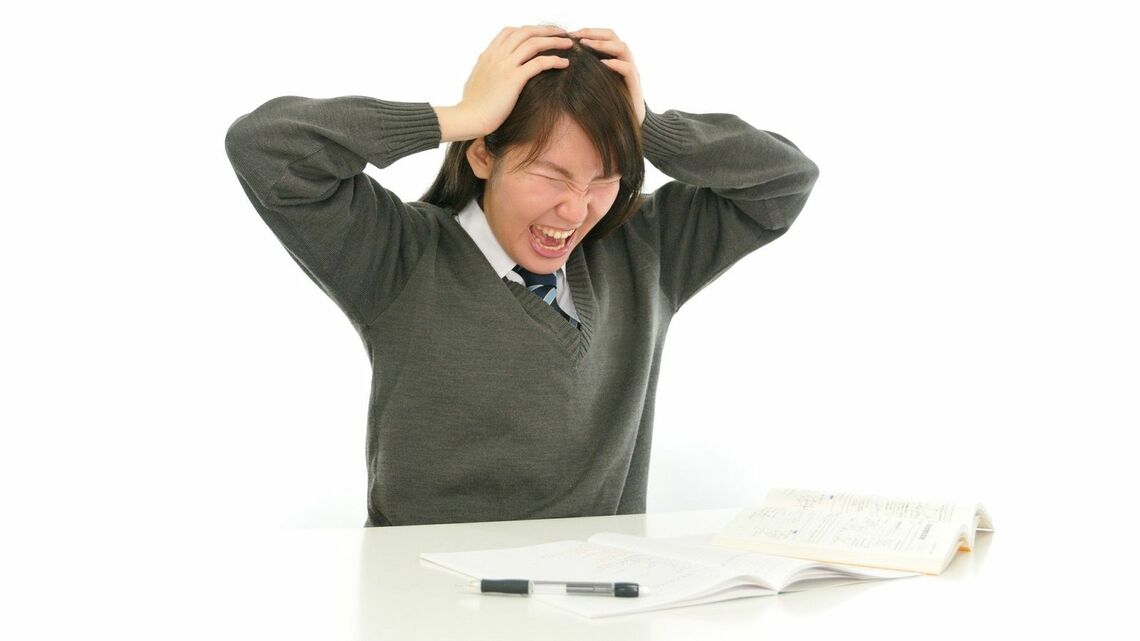
問題が解けないとき「きちんと悔しがれる人」は、成績が上がりやすいといいます(画像:tsukat/PIXTA)
覚えられない、続けられない、頑張ってもなぜか成績が上がらない――勉強が苦手で、「自分は頭が悪い」と思い込んでいる人も、実は「勉強以前の一手間」を知らないだけかもしれない。
そう話すのは、中高生に勉強法の指導をしている「チームドラゴン桜」代表の西岡壱誠さんです。
「僕も昔はこれらの工夫を知らなくて、いくら勉強しても成績が上がらない『勉強オンチ』でした。でも、『勉強以前』にある工夫をすることで、『自分に合った努力のしかた』を見つけられて、勉強が楽しくなったんです。効果は絶大で、偏差値35だった僕が東大模試で全国4位になり、東大に逆転合格できました」
西岡さんをはじめとする「逆転合格した東大生」たちがやっていた「勉強以前の一工夫」をまとめた書籍『なぜか結果を出す人が勉強以前にやっていること』が、発売すぐに3万部を突破するなど、いま話題になっています。ここでは「勉強法以前」の、「勉強のための感情コントロール法」を紹介します。
「勉強しても成績が上がらない」勉強以前の問題点
「勉強しても成績が上がらない」

「本を読んだり問題を解いたりしても、いっこうにうまくいかない」
そんなふうにお悩みの人は多いですね。頑張ってもうまくいかない状態が続くと、何かを頑張ろうとしても「何をやっても意味がないのではないか」と考えて、努力する意欲が湧かなくなってしまいます。
僕も同じ悩みでずっと苦しんだ人間です。偏差値35から2浪を経験し、何冊も参考書を使って勉強しているのに結果が出ず、苦しんだ時期が長かったからです。
そして僕は、「勉強をしても結果が出ない」という悩みを、けっこう特殊なやり方で解決しました。使用する参考書を変えるとか、勉強法を変えるとか、そういうこととは全然違うやり方で、自分の勉強を「結果の出る勉強」に変えたのです。
今回は、「勉強する前に知っておいてほしい、勉強して結果を出すためのコツ」についてお話ししたいと思います。
やり方はとてもシンプルで、特殊な工夫や準備をする必要はありません。
「感情の起伏を大きくすること」
これを実践すれば、勉強が結果に結びつきやすくなります。
感情を動かせば成績が上がりやすい
具体的にご説明しましょう。
みなさんは、問題を解いて、その問題の答えが間違っているとき、自分に対する怒りを覚えますか? それとも、「まあ、仕方がないな」と受け入れるでしょうか?
結果に結びつくのは、前者の「自分に対して怒りを持つほう」です。できなかった問題があったことに対して「どうしてできなかったんだ!」「なんでこんな単純なことに気づけなかったんだ!」と苛立ちを覚えると、その問題を忘れないようになり、「次は絶対に間違えないぞ!」と思って復習することができます。
そして逆に、問題が正解しているときにも、「やった! 解けた!」と本気で喜んでいるほうが勉強の結果につながります。その問題が脳に残りやすくなりますし、また勉強のモチベーションが上がって、勉強が継続的になっていきます。
これは、東大合格者の多い進学校のクラスでは、当たり前に目撃できる現象です。真剣に問題に対して取り組み、1つの問題に対して一喜一憂し、問題が解けなくて悔し泣きする生徒がいるのも普通です。
たかが1問に対しても、真剣に取り組み、しっかりと感情を動かしながら解いている生徒は、その努力が結果につながりやすいのです。
その理由は、「感情の起伏があるほうが、脳に残りやすいから」だと思います。記憶を司る脳の器官である海馬は、感情を司る扁桃腺から、感情に関する情報を受け取り、その情報をもとに記憶が蓄積されていくとされています。ですから、勉強の際に自分の感情が動かなかったとしたら、それはただ目を動かしているだけで、脳にまで情報を届けていないに等しいのです。
「この問題を間違えた」という情報を脳に送ったときに、ただ文字列として「この問題を間違えた」と送っていても、脳には溜まらないのです。
「この問題を間違えて悲しかった」とか「悔しかった」とか、本人の感情の起伏があったり、なんらかのストーリー・エピソードがあって、情報は初めて忘れにくくなるのです。
何も感情を動かさずに淡々と努力していても、頭には何も残りません。勉強の結果が出にくい人は、勉強以前の問題として、感情を動かすのが苦手だからうまくいかないことが多いです。
同じように、勉強しているときに「なるほど! 面白いな!」と思うことはとても重要です。
授業で先生の話を聞いている際に、先生が言うことに対して「なるほど! そうなのか!」とか「この話って、これとつながっているのか! 面白い!」と感じる瞬間を大事にして、しっかり1つひとつ丁寧に、驚いたり不思議がったりしている人は伸びやすいです。
東大の授業に参加していると、オーバーリアクション気味な東大生が多いことに驚かされます。いちいち教授の話に頷いていたり、先生がギャグを言ったときに笑ったり、面白いと思ったことが出てきたらメモを取りつつ大きく頷いてみたり、「なるほど」と口に出してみたり。
とにかく、きちんと感情を動かしながら話を聞いていることが多いのです。先ほどもお話ししましたが、感情と結びついた記憶は残りやすいです。それはどんな科目の勉強をするときであれ、問題を解いたときの対応であれ、重要なのだと思います。
逆に、僕は伸び悩んでいたときに、あまり感情を表に出していませんでした。友人に成績で負けても悔しいと思わず、先生の授業や予備校の話をただ仏頂面で聞いているだけでした。そうすると、やっぱり理解度や記憶への定着度合いが落ちてしまって、うまくいかなかったのです。
東大生がすすめる「感情コントロール法」2選
1:オーバーリアクションをとる
ここまでを総合して頭が良くなりたい人におすすめなのは、勉強している際に、オーバーリアクションをすることです。嘘でも演技でもいいので、とにかく感情の起伏が大きいように「振る舞ってみる」のです。
実際に自分が本当にそう思っているかどうかは、あまり関係ありません。とにかく、嘘でもいいので、思ったことをオーバーに表現してみるのです。例えば次のような感じです。
・問題が解けたときには、嘘でもいいから、ガッツポーズをしてみる。
・間違えたときには「チクショー!」と机を叩いてみる。
・勉強中、嘘でもいいから「面白い!」と言ってみる。
・何か理解できたところがあったら「わかった!」と口に出してみる。
とにかく、どのような形でもいいので、自分の感情を表出させていくイメージです。
さて、そうはいっても、「自分は、感情の起伏は激しくないが、頭の中で考えていることはある」「だから、わざとそれをオーバーに実践する必要はないんじゃないか」という人もいらっしゃるかもしれません。
しかし、それでも僕は、どんどん言葉や態度に表していくべきだと思います。顔や言葉に表れない感情がある人もいるかもしれませんが、やはり態度や行動を変えると、感情は増幅します。
口角を上げて笑顔の形を作ると、自然と「面白い」という感情がつくられるものです。やはり顔や言葉に感情を乗せていくべきだと思います。
東大生に「独り言が激しい人」が多いわけ
2:独り言をしゃべる
もう1つこれに関連しておすすめなのは、「独り言をしゃべる」というものです。
東大生には「独り言」が激しい人が多い印象があります。誰にも何も話していないにもかかわらず、1人で「あ、なるほどこの問題はこう解くのか。ってことは、ここをこうすればいいから〜」とか、ずっとしゃべり続けている人は多いです。
誰も聞いていないことを前提にして、自分で思い付いたことを口に出して感情を表出させていったら、感情が豊かになり、自分の感情の整理もできて、成績は上がっていくはずです。
いかがでしょうか? 勉強法や参考書を変える前に、感情の面をコントロールすることを、ぜひ実践してみてください。きっと効果が現れると思います!
(西岡 壱誠 : 現役東大生・ドラゴン桜2編集担当)








