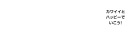いくつもの挫折を経て…山口真由がたどり着いたコメンテーターという”絶対領域”
『羽鳥慎一モーニングショー』(テレビ朝日系)の月曜コメンテーターをはじめ情報番組のコメンテーターを務める山口真由(やまぐち・まゆ)さん。
山口さんと言えば、元財務省官僚で法学博士、信州大学特任教授というキラキラした肩書きが並び、著作リストを見ると「東大首席弁護士」「エリート」「天才」と言ったこれまたキラキラしたワードが目に飛び込んできます。
そんな山口さんが5月下旬に上梓した『挫折からのキャリア論』(日経BP)では、“キラキラ”が一転。挫折や失敗談がこれでもかと明かされています。
「私たちが欲しているのは武勇伝でも成功談でもなく、挫折した話」と力を込める山口さんにお話を伺いました。前後編。
社会は「デキる人たち」で構成されているわけではない
--この本が生まれたきっかけは、「日経xwoman(クロスウーマン)」に掲載された、社会人になって山口さんが経験した失敗談に関するインタビューだったそうですね。読者からの反響も大きかったと聞いています。
山口真由さん(以下、山口):「山口さんは強く見えるのに、こんなに苦労があったんですね」という感想があって「え? 私って強く見えるんだ」とびっくりしました。「そうか、そうか、私はずっと背伸びしてきて、強く自分を見せるようにいろんな鎧(よろい)をまとってきたんだなあ」と。そしてそんなふうに見られることにどこか満足もしている。「私はできる!」みたいな……。
でも、そんな人たちだけで社会が構成されているように見えていたことが、私の当時の挫折の原因だったと気づきました。本当はものすごい傷を抱えてここにいるのに透明化されていた。当時の私が、成功して見える多くの先輩たちの中にも同じくらいに傷を抱えている人がいたとわかったら、全然違う決断ができたかもしれない。そんなことを考えながら、担当編集者さんとも話して、私の個人的な経験だけではなくて、今まさに傷を抱えて、いろいろなことに挫(くじ)けそうになっている人たちに対して、広いメッセージを伝えることはできないかと思いました。
「はじめに」でも書きましたが、私にはロールモデルがいなかったんですよね。「働く女性」として社会やメディアから提示されるロールモデルは、すべてキラキラの側面だけを取り出していて、元気で余裕がある時には「すごいなあ」と素直に耳を傾けられるけれど、傷ついている自分には全く意味がなかった。だからこそ、「自分の挫折や弱みをきちんと言葉にする、言語化することで新しいロールモデル論ができるのではないか?」と思って書いたのがこの本です。

--特に社会で活躍している人の失敗談や挫折した話を聞くと、「自分だけじゃないんだ」と励まされる気がします。「こんなにキラキラして見える人にもこんな時代があったんだな」と。
山口:そうですよね。ただ、この本を出して「山口さんも、すごくつらかったんだね」と涙ながらに言われることもあるのですが、主観的にはそこまでじゃないんですよ(笑)。
今振り返って、当時の自分に立ち戻ったとしても、やっぱり挫折はしたほうがいいとは思います。そのほうが絶対、人間として深みがあるじゃないですか。
--確かに。
山口:挫折を避けましょうという本ではないんです。でも、いきなりすごく大きなところに飛び込むのはリスクがあるから、他人の失敗を横目で見つつ「だったら自分は今は山の三合目くらいにいるな」みたいに、どこか俯瞰した目線があると気が楽になるんじゃないかなと思いました。
「他の人にとっても茨の道だった」挫折した話がもたらすもの
--「若い世代の育成に注力する人があまりいないように見える」と書かれていた部分にドキリとしました。というのも、同世代と話していても、「部下や後輩にどう接していいかわからない。私たちは昭和世代に教育されてきたけれど、今それをやってしまうとハラスメントになりかねないし、下手なことができないから悩む」という声を多く聞きます。
山口:難しいですよね。昔みたいに飲みニケーションの時代でもないし、会社の話を共有する文化もない。でも、昭和のやり方ではなくて違うやり方があるのではと思っています。相変わらず、武勇伝や成功談を語ってくる上司もいるけれど、私たちが求めているのはそれじゃない。むしろ「私はこういう挫折をしたことがある」という話なんじゃないかって。
財務省でダメダメだった私も上司や先輩から「20代でこういう挫折をして、30代でこういう転機があって、40代で今こうなってる」という全体像をどこかで話してもらえていたら、当時の私も全く違う選択をしたかもしれないと思うんです。
自分が通った道が、自分だけの茨(いばら)じゃなくて、他の人にとってもやっぱり茨(いばら)だった。自分が通った道が、落ち続けるのではなくて、どこかで浮上する芽があったんだと思えば、同じ「落ちる」にしても、もっと全然違う気持ちで落ちることができたかもしれない。それこそが、今私たちが下の世代に共有すべきものなんじゃないかなって。
--それが私たちの役割なのかもしれないですね。
山口:これまでに何冊か本を書く機会もいただいてきたのですが、私の場合は勉強で成功したという話が多くて、それが求められてると思っていました。でも、よく考えると成功談はたくさん転がっているけれど、失敗の話ってそんなにないんですよね。
学校を卒業したてで社会での振る舞い方や仕事のやり方なんて何もわからない状態のときに成功談を聞かされたら「やっぱり私はダメなんだ」と思ってしまう気がして、それよりも「見方を変えれば全然違う視点が持てるようになるよ」とか「事態は変わるよ」という話のほうが聞きたかったんだなと改めて思いました。

私の“絶対領域”は?
--受験勉強での成功体験があったり、努力すればなんとかなると思っているからこそ、自分が「できない」ことを認めるのって難しいのではと思いました。「できない」ことがあったとしても、どこかで「まだまだ努力が足りないのかも」と思ってしまう。
山口:私もできないことを認めるのはすごく苦手です。でも、ある大御所のタレントの方に言われたのが「絶対領域が一個あると思えば他は別にいいのよ」って。若い頃は自分の武器を増やそうとばかりしてたけれど、今はむしろ削っていって自分の絶対領域を持つことが大事なのかなと思うようになりました。
--「日本語の文章(教科書)を読んで記憶する能力が異常に高かった」と書かれていましたね。
山口:そうなんです、私の場合は短時間でものすごい量を詰め込んでアウトプットするのが得意なんです。
--今朝も見てきましたが、『モーニングショー』のコメンテーターの仕事なんて、まさにそれですね。
山口:そうなんですよ。短時間で資料をバーッと読んで、一気に吐き出すのが私の絶対領域なのかなって。

評価は「めっちゃ気になる」
--「評価されることが、ずっと気になってた」と書かれてましたが、今は他人からの評価は気にならないですか?
山口:いや、めっちゃ気になりますよ(笑)。でも、「気にならないといけない」というか、物差しが他人とズレてもいけないんですよ。と同時に、すべての人に評価されようと思わないほうがいいというのも確かで……。
--というのは?
山口:テレビって一つのあきらめなんです。すべての人に刺さるコメントなんてあり得ないし、仮にあったとしてもそれは何の色もついていないということだから、コメントとしては意味がないんです。事務所の人から聞いたんですが、「2割から支持されて、8割から嫌われるっていうのがスター」なんですって。でも、私はそこまで行けないし、8割から嫌われて耐えられるほど強くもない。だから、自分のちょうどいいところを探っています。あくまでも私の感覚ですが、6割から「そうかな?」って思われて、4割からは「何言ってんだ」って思われるぐらいがちょうどいい。それぞれのキャラのアクの強さにもよるんですけど、私は割と小心なんで、そんな感じで考えていますね。
--会社員で9割に嫌われてたら、結構つらいですよね……。
山口:その人は、会社を辞めてスターになれます。YouTubeに行ってもいいかもしれないですね(笑)。
(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)