教養ある大人が密かに実践する「知的な習慣」

気になった情報との一期一会は、積み上げることでネットワークのようにつながり始める(写真:LucidSurf/iStock)
知的な生活を送りたい、教養のある人になりたい――。新年、そんな目標を持つ人もいるのではないでしょうか。仕事や人生を知的に変えるヒントを紹介した『知的生活の設計―――「10年後の自分」を支える83の戦略』を書いた、研究者でブロガーの堀正岳氏に、そのコツについて語っていただきます。
私たちは日々膨大な情報に囲まれていますが、そうした情報をただ消費するだけでなく、有益な知識を蓄積し、自ら生み出すことで、知的な生活を送りたい。そう考える場合、いったいどうすればいいでしょうか。筆者はそう考えるひとりで、過去さまざまなことを試してきました。何をして「知的」というのかは人によりけりで考え方が違うと思いますが、筆者なりの考えと取り組みを今回の記事では述べてみたいと思います。
『知的生産の技術』(岩波新書)の著者である梅棹忠夫氏は、「なんらかの新しい情報が生まれること」が知的生産には必須であるとしています。
たとえば本を読めば感想が生まれます。心を動かす本を読めば、自分でも書いてみたくなるかもしれません。あなたが情報に触れた結果、以前は存在しなかった新しい言葉や表現が生まれることも、広い意味で見た場合には「新しい情報」といえます。
しかし筆者は「新しい情報」にはもう1種類あるように思います。それは、必要な情報を積み上げることで、それまで見えていなかった「つながり」が見いだせるようになるということです。
「王は死んだ! 王様万歳!」
私が大学生だった頃、とある有名サッカー選手の引退とその後について英語で書かれた記事の中に、以下のようなフレーズがありました。
The King is dead, long live the King!(「国王は死んだ。国王万歳!」)
その奇妙な定型句は、それまでも見ることがあり、興味を持った私はいろいろ調べ始めました。その中で、たとえばそれが中世フランスでの王権の移行に際して慣例的に叫ばれる言葉だということ、内戦を避けるために王が埋葬されるやいなや次の国王の長寿を祈ることで王権の連続性を保つ意味があるという歴史などです。
興味はその後も続きました。この言葉の奇妙さは私をどこかでいつも引きつけていたらしく、その後、中世における王権の扱いについて論じたカントーロヴィチの『王の二つの身体』(筑摩書房)を読みふけったり、この表現を使った記事を収集したりといったことを、気づけば15年ほぼ断続的に続けています。
たとえば2009年の第51回グラミー賞の最優秀楽曲賞に輝いたコールドプレイの「Viva la Vida」の歌詞にもこの語句は登場しましたし、人気の車がモデルチェンジしたり、新しい人気のプログラミング言語が登場したりする際に使われることもあります。
最近だと、映画『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』の中で「国王」の部分をもじった形でこの言葉が登場しているのを耳にしたときは、私は劇場の暗闇の中でニヤリとして、こっそりと手のひらにそれをメモしたのでした。
なんとなく心に訴えかけるもの
なにもこの言葉を研究するつもりで集め始めたわけではありません。響きが面白く、なんとなく心に訴えかけるものがあったので、耳にするたびにメモし、背景を少しだけ調べたうえで忘れる、そんなことを繰り返していたにすぎません。
しかし時間とともにこうした引っ掛かりが積み上げられてゆくうちに、どのようなシーンでこの言葉が使われるか、どんな背景をもった人がどんな印象を残すために使うのかといったことが、隠れたメッセージをもっているかのようにつながりをもって見えるようになってきました。
いまでは過去15年にわたるさまざまな用法やその変遷が私の手元に蓄積してありますので、いつか私はこの表現について1冊の本とまではいかずとも、エッセイの1つか小論くらいならば書けるのではないかと考えています。
このように「気になって仕方がない言葉やフレーズ」「違和感を覚えさせるなにかとの出会い」を記録し、積み上げることで、やがてそうした情報との一期一会はネットワークのようにつながり始めます。1回の読書や1回の体験をそのままで終わらせない、こうした「積み上げ」こそが、日常を「消費」で終わらせないためのカギとなるわけです。
ハイコンテクストな時代を楽しむ
私たちの周囲に情報が膨大にあるということは、まだ発見されていないつながりや、指摘されたことがない解釈が無数にあるということでもあります。
たとえば最近だと人気漫画家が有名なテレビのワンシーンや、映画ポスター、あるいは名画の構図をさりげなくパロディー化して作品に組み込み、それに気づいたファンが話題にするといったこともありました。説明されなくても作品を楽しむことはできますが、それを知れば私たちはさらに深く作品の中に入っていけます。
こうした作品とその受容をコミュニケーションとして捉えるなら、これは文化人類学者のエドワード・T・ホールが「ハイコンテクスト文化」と呼んだ状態に近いでしょう。
「ハイコンテクスト」であるとは、事実の認識や前提としている価値観といったものが、情報を発信する人と、それを受け取る人のあいだで高いレベルで共有されているために、「みなまで言わずともなにがしかの情報が伝わる」、そんな状態のことを指しています。わかりやすい言葉で表現するなら「ネタがネタであるとわかっている状態」といってもいいでしょう。
しかし世界はわかりやすい「ネタ」だけで出来上がっているわけではありません。ある場所で隠されているものは、別の場所で明かされていて、それを見つけるためには長年の経験から得た積み上げをカギにしなければいけないことがよくあるのです。
そうしたカギを集めるにはどうしたらいいでしょうか。筆者は今日から実践できる習慣として「二度出会ったらメモをする。三度出会ったものは記録しはじめる」をおすすめします。
たとえば「王は死んだ! 王様万歳!」の例で言うならば、一度目にその表現を目にして気になって辞書で引いたくらいでは、まだそれが自分にとって特別な情報だということには気づかないでしょう。「初めて出会う情報」はいくらでもあるからです。
しかし二度目に出会って、一度目と同じような違和感をもったり、興味をかき立てられたならば、その情報や違和感との出会いをメモしましょう。やがてそれが三度目になれば、それはもう積み上げの始まりです。
二度目と三度目の出会いはすぐであることもあれば、何年も間隔が開いていることもあります。しかし、私たちの「好奇心の記憶」は強く残るものだと私は考えています。そのときにもきっと「あ、これはあの時の」と興味をかき立てられるはずです。
年に一度の、情報の振り返り
コツコツと蓄積した知識が本当に有益なものになっているか、あとで利用可能なものになっているかは、年に一度くらいチェックするといいかもしれません。
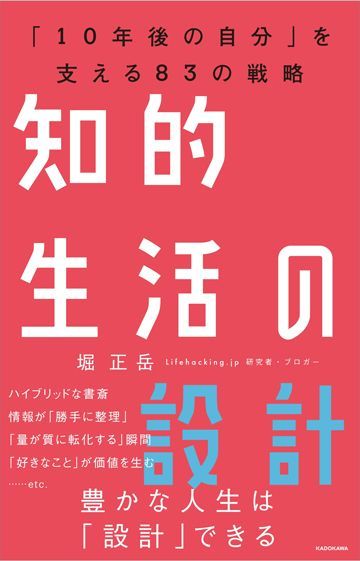
たとえば読書。ここしばらくの1冊1冊の読書が点と点になって、何か自分だけに見えるパターンを生み出しているか? 自分の興味が向かっている先はどちらなのか? こうしたセルフチェックしてみるのはおすすめです。
もう1つは「航路」の修正です。最近新しいジャンルの開拓や、新しい体験を積極的にしていないのではないか? 同じ場所で足踏みをしていないか?と振り返ってみます。
そして、それらを“私的なもの”にしておくという点も、重要ではないかと考えます。「この本を読んだ」「このようなあらすじだった」という情報の中には、あなた自身の感想や視点が入りません。これでは、読書そのものの記憶ではなく、「本についての情報」という程度で止まってしまいます。
感想、感情、そのときの状況についても、併せて保存しておきましょう。手帳や読書アプリ、Evernoteといったサービスを使うことを習慣にすれば、誰にでも簡単にできます。
そうした個性化した記録こそが、ほかのどこでも検索することができない価値を生み出してゆきます。そしてそうした個性化こそが、ほかにはない情報の蓄積として成長してゆくのです。




