「利益の最大化」だけが目的の企業が招く暗い未来
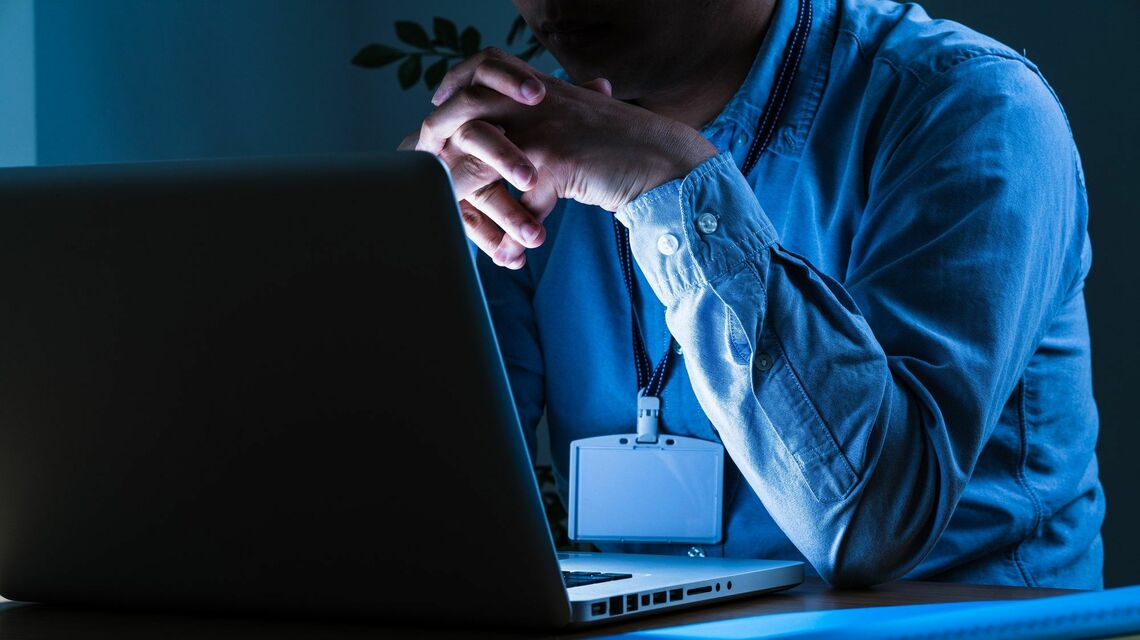
かつて、企業には「共通善の守り手」という役割がありましたが、いつしかその役割は放棄され、あらゆる犠牲を払って利益を最大化することだけが目的となってしまいました(写真:aijiro/PIXTA)
企業は世界の動向につねに多大な影響を及ぼしてきた。そして企業は、誕生した当初から、共通善(社会全体にとってよいこと)の促進を目的とする組織だった。しかし今、企業はひたすら利益だけを追い求める集団であり、人間味などとは無縁のものであると考えている人は多い。では、企業はどこで、どのように変節してしまったのか? 今回、古代ローマの「ソキエタス」から、現代の「フェイスブック」まで、8つの企業の功罪を通して世界の成り立ち知る、『世界を変えた8つの企業』より、一部抜粋、編集のうえ、お届けする。
企業の究極の目的

企業はひたすら利益だけを追い求める集団であり、人間味などとは無縁のものであると考えている人は多い。中には、利益の追求を最優先するのは、そもそも企業の義務だとまで主張する人もいる。しかしどちらも間違っている。
企業は誕生した当初から、共通善(社会全体にとってよいこと)の促進を目的とする組織だった。古代ローマでも、ルネサンス期のフィレンツェでも、エリザベス朝の英国でも、企業は社会に使われるものであり、社会の繁栄を築き、維持するための働きをしてきた。
企業は公共の目的を持った公共の機関であり、国の発展に寄与するものだと見なされているからこそ、国から特別な権利も与えられている。ときどき――あるいはしばしば――この目的から逸脱することがあるとしても、企業の存在意義が共通善を促進する能力にあることはつねに変わらない。
近代経済学の父アダム・スミスも、このことは理解していた。スミスは「見えざる手」を論じた『国富論』のある箇所で(めったに読まれない箇所だが)、万能の資本主義に重要なただし書きをつけ加えている。「見えざる手」も完全無欠ではないのだ。
「生産物の価値が最大限に高まるよう、労働を振り向けることで各人がめざしているのは、自分自身が利益を得ることだけである。このとき各人は、そのほかの多くの場合と同じように、見えざる手に導かれて、自分ではまったく意図していなかった目的の達成に貢献している。各人にそういう意図がないことは必ずしも悪いことではない。自分自身の利益を追求しているときのほうが、意図的に社会の利益を促進しようとするときよりも効果的に社会の利益を促進することが多いからだ」。
この箇所で注目すべきは、ここでいわれていないことにある。すなわち、個人の利益を追求することがいつも共通善の促進につながるとはいっていないのだ。多い、としかいっていない。
さらに重要なのは、利益という動機はあくまで手段であって、それ自体が目的ではないとスミスが考えていることだ。企業が利益を追求することで、結果的に社会に恩恵がもたらされると信じているからこそ、わたしたちは企業に利益の追求を認めているのだ。スミスの考えによれば、企業には公共の目的があり、その目的とは共通善を促進することだとされている。
利益の追求は目的ではなく「手段」だった
企業と共通善の結びつきは、かつては今よりもはるかにはっきりしていた。当初、企業は君主や政府から認可を得る必要があり、認可を得るためには、採算の取れる事業であることに加え、国のためになる事業であることも示さなくてはならなかった。
1600年、東インド会社はエリザベス1世に対し、「自社の航海の拡大をめざすと同時に、イングランド王国の名誉のために」活動することを誓った。ユニオン・パシフィック鉄道には南北戦争の最中に議会から認可がおりた。大陸横断鉄道が開通すれば、分断された国の統合を図れるというのが支持者たちの主張だった。
前世紀に、わたしたちは企業の本来の精神を見失ってしまった。もとは手段だった利益の追求が目的と化してしまった。そのような変化には、法律の影響もいくらかあった。
20世紀に入った頃には、もう君主に認可を求める必要はなく、地域の役所に書類を提出するだけで企業を設立できるようになっていた。企業が存在意義の説明を求められることはなかった。しかしそれよりも大きかったのは、政治の影響だ。共産主義の脅威と冷戦に直面した西側諸国は、資本主義の価値への信頼を強めざるを得なかった。
企業はもはやアダム・スミスが述べていたような、欠点はあるが有用なものという位置づけではなく、西側の生活を特徴づけるもの、共産圏の暗愚な市民と自分たちを区別するものと見なされた。
こうして民主主義と資本主義とが同義語になった。その結果、企業は使われるものから称えられるものに変わった。企業がわたしたちの特徴になると同時に、わたしたちは企業をもてはやすようになった。
しかし、企業の歴史の中で起こったこの変革は、危険な副作用も招いた。企業が成長し、巨大化する一方で、今や企業に公共の精神が求められることはまれだ。市場の倫理性よりも、市場の効率性が問われる。
ある企業が儲かっていれば、それは企業の効率性が高い証拠であり、効率性の高さこそ、追求するべき善である。こういう考え方が社会だけでなく、企業のリーダー自身のあいだにも浸透している。
これにより社会の大きな問題への関心が薄く、もっぱら利益を上げることに腐心するビジネスリーダーが増えた。金融資本主義も台頭し、ものの生産よりも金融工学に軸足を移した企業活動が目立つようになっている。さらに「迅速に動き、破壊せよ」というモットーに代表される、責任ある行動より急速な技術の進歩を重んじるシリコンバレー精神も広まった。
ときにビジネスリーダーが共通善の守り手としての役割を口にすることもあるが、わずかな例外を除いて、そのような発言に行動の裏づけがあることはますます減っている。
放棄されてしまった企業の本来の役割
わたしたちが今、目の当たりにしているのは、企業と大物経営者が途方もなく大きな――東インド会社の時代には想像すらできなかったであろうほどの――富と力を持つ時代だ。しかし社会の繁栄を築くための道具という、企業の本来の役割は放棄されてしまっている。
これは危険な状況だ。長い年月のあいだに企業は進化したが、同時に、制度を悪用して、他人の富を奪い取ろうとする悪徳経営者の手口も進化している。グローバル経済の将来に何が待ち受けているかは、企業の原点に立ち返れるかどうかで決まる。原点に立ち返れなければ、あらゆる犠牲を払って利益を最大化するという泥沼にはまって、二度と抜け出せなくなるだろう。
(翻訳:黒輪篤嗣)
(ウィリアム・マグヌソン : テキサスA&Mロースクール教授)



