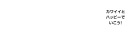「推し活」で不幸になってしまう人の特徴。 精神科医が伝える“推すために一番大切なこと”
そしてもうひとつ、「自分自身がキラキラすること」に疲れてしまったというのが大きいのではないかと思います。「推し活」が台頭してくる前はInstagramが大人気で、多くの人が自撮り棒を持って観光地に出かけるとか、そんな時代が2010年代後半にあったと記憶しています。
――ネット上にも一時期、「自分を輝かせるために」的な記事が多かったですね。
熊代:その後に「推し活」ブームがきているんです。おそらく「自分キラキラ」の限界というか。どんなに個人で「いいね」を集めようとしても限界があるし、それって結構、疲れるよねということがわかってしまった。そこに「自分キラキラ時代」の疲労感を代替する心の満たし方として「推し活」がちょうど良かったという側面もあるのではないでしょうか。
◆生きるうえで「誰かに夢を託すこと」は大切
――著書(※)では「推し活」は人を幸せにする、と定義していますね。
熊代:自分の心を満たす際に「褒めてほしい」という欲求だけでは上手くいかないのではないか、という思いが私にはありました。私はハインツ・コフートやアブラハム・マズローといった心理学者の理論を学びましたが、彼らの心理モデルから私は「自分の承認欲求を満たす、つまり“キラキラする”だけでは、そう簡単に人の心は完結しない」という考えを読みとってきました。
※『「推し」で心はみたされる? 21世紀の心理的充足のトレンド』より
自分の承認欲求を満たすだけでなく、自分以外の誰かに夢を仮託して応援するというのも、生きていく上ではとても大切なことではないか……そこにもう少し目を向けませんか? というのが著書を通して伝えたかったことです。
憧れの感情は人を引っ張って成長させます。「褒められたい」という気持ちと、「こうなりたい」と憧れる気持ち、その両方があったほうが人は伸びる。そんな時にも、「推し活」は有効ではないか、と。
――推しを憧れの対象として見上げる、「自分もああなりたい」と感じている部分は、確かにありそうです。
熊代:推しの良い部分を見習いたい気持ちが働くならば、それは「推している」「自分の心を満たしている」だけではなくて、「推し活」を通して前に進む力を分けてもらっているとも言えると思います。
◆「推し上手」は仕事でもうまく立ち回れる
――自分自身の成長の糧になる可能性もあるわけですね。
熊代:あとはもちろん、単純に「推し活」の対象の活動や創作物に触れて楽しむというのも重要な効能です。嫌なことがあったときに気分転換ができる、そういうチャンネルがあると生きていくのが少し楽になるんですよね。
――まさに「推し活」と上手く付き合うことで生活が潤うという。
熊代:「推し活」の対象は身近な人だっていいんです。たとえば、会社の先輩、同僚、後輩に推しがいれば、それぞれが自分のロールモデルになりますし、その人たちが持っているスキルやノウハウをリスペクトすることで自分にも取り込みやすくなる。それに、推す自分自身だけでなく推される側も成長しますよね。
――推される側もですか。
熊代:子供だって親が「この子はダメだ」って思っているよりは「推し甲斐がある」と思った方が伸びますし、会社の後輩や部下も同じです。「推し活」ってもともと対象者をエンパワーしていこうという活動じゃないですか。経済的なことだけではなく、ライブに集まってステージを盛り上げるというのもエンパワーする行為です。
それって実は、日常生活や職場での「推し活」的なものにも当てはまることで。後輩はもちろん先輩や上司を推すことでエンパワーもできるし、自分自身も成長できる。いいことだらけですよね。
そう考えると「推し活」は意外と、ビジネスマンにとって大事なことでもあるんです。「推し上手は仕事もできる」。読者のみなさまにはそう伝えたいですね(笑)。
<取材・文/鈴木雅展>
【熊代亨(くましろ・とおる)】
精神科医・ブロガー。ブログ「シロクマの屑籠」にて現代人の社会適合のあり方やサブカルチャーについて発信。著書に『融解するオタク・サブカル・ヤンキー』(ともに花伝社)、『何者かになりたい』(イースト・プレス)、『「推し」で心はみたされる? 21世紀の心理的充足のトレンド』(大和書房)など
【鈴木雅展】
神奈川県出身。人文科学系出版社に勤務し翻訳書籍等の編集を手掛けた後、フリーランスとしてアニメ雑誌やWEBサイトを中心に各社・各媒体で編集・ライティングを担当したほか、アニメ関連ムック、原画集等の編集に携わる