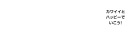毒母が多い世代は?「女は結婚して家庭に入るのが幸せだ」親に人生をコントロールされた女性が自分の子にも

『毒母は連鎖する〜子どもを「所有物扱いする」母親たち』(光文社新書)が話題の旦木瑞穂(たんぎみずほ)氏にお話をお聞きしました。
◆毒母になりやすい性格とは?
旦木:親に従順な女性、他人から影響されやすい女性、「よい子」として育った子どもが比較的多いかもしれません。先天的な性格もあると思いますが、高圧的で支配的な毒母に育てられたら、よほど特別な理由がない限り、従順に育つケースが多いと思います。
本書の第5章に出てくる宗教2世の時任さん(仮名・30代)は、毒母の連鎖を現状のところは止めています。時任さんには、家に帰ってこない夫自宅に寄り付かない(時任さんの父親)のせいで、さみしさから新興宗教に入信した毒母がいました。父親と母親2人とも、それぞれの親から愛情を注いでもらえなかったようで自己肯定感が低く、父親は家庭をネグレクトし、母親は不倫や宗教に流されました。時任さんは現在、両親を反面教師に、何よりも子どもを優先させる生活を送っています。
――毒親を反面教師にして、連鎖をストップすることはできるのですね?
旦木:はい。ただ、毒親育ちでなければ、「自分の人生は自分のもの。子どもの人生は子どものもの」として、もうちょっとリラックスして子育てに向き合えると思うのですが、時任さんの場合は、「私は母親だから、とりあえず今は子どもを優先にするべきで、自分のことは後回しにしなければ」と、毒母を反面教師にすることに囚われすぎているところがあるように感じます。もう少し肩の力を抜いて子育てに向き合えると良いように思います。
◆自分が毒親かどうかをチェックする2つの問いかけ
――本書に登場する毒母のほとんどが、しつけが厳しかったり、教育熱心だったりと、一見すればどこにでもいるの母親のように感じます。一方で、旦木さんが取材したさまざまな毒母のエピソードを読んで、誰もが毒母になり得るのだと改めて思ったのですが、自分が毒母かどうかを客観的に判断する方法はありますか?
旦木:個人的には2つあると思っています。まず、子どもを必要以上に自分の思い通りにしていないか。次に、自分が子どもに間違ったことをしたときにきちんと謝れるか、という問いかけです。
例えば、私はも自分の子どもが受験に失敗したときに、自分のことのように捉えて必要以上に落ち込んでしまったんですよね。これは、自分と娘を同一視して、境界線を曖昧にしてしまったという証拠かなと猛省しています。
また、親の権力や経済力を振りかざして、子どもをコントロールしようとする言葉を子どもに吐く親も毒親だと思います。
――私自身ちょっとドキッとしました。でも謝罪できるかどうかで、子どもを自分の所有物ではなく、対等な人間として見ているということが判断できるのですね。ちなみに、「毒母が多い世代」はあるのでしょうか?
旦木:団塊の世代が多いように思います。特に昭和の家父長制的価値観を重視する家庭で育ち、「女は結婚して家庭に入るのが幸せだ」と教えられ、社会での活躍の機会を奪われた女性が少なくないように感じますね。結局、親に人生をコントロールされてきた女性が、自分も子どもの人生をコントロールしてしまうという連鎖が起こってしまうのではないでしょうか……。
◆毒の連鎖を止めるには?
――毒の連鎖を止めるにはどうすればよいのでしょう?