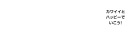揉め事や人間関係がしんどい…それでも相手と向き合うことの意味
出版社「彩図社」で編集長として働く傍ら、作家として20年以上裏社会の取材や執筆活動を行ってきた草下シンヤ(くさか・しんや)さんによる『怒られの作法〜日本一トラブルに巻き込まれる編集者の人間関係術』(筑摩書房)が、4月に発売されました。
クレームの電話や脅迫を受けることは日常茶飯事で「(おそらく)日本一トラブルに巻き込まれた経験が多い」という草下さんによる“怒り”の処し方や謝罪の仕方、炎上対策などがつづられています。
盛大に怒られたり、揉(も)めたりすると、つい自分を責めてしまったり、人と関わることが怖くなってしまうけれど−−。
後編では、草下さんに「それでも怒られるのが怖い」人に向けてのメッセージをいただきました。

問題がこじれてしまう理由は?
--私はとにかく人と揉(も)めたり、怒られたりするのがすごく怖くて……。それで今回、草下さんに取材を申し込んだのですが、『怒られの作法』をとおして、草下さんの人間に対する信頼を感じました。そういう意味では、「他人が怖い」というのは人間や世界を信頼しきれていないのかもしれないですね。
草下シンヤさん(以下、草下):「遠慮」と「素直」を、切り分けないといけないと思うんですよね。やっぱり、「素直」が大事なんですよ。「他人を怒らせたくない」「他人とトラブルになりたくない」というときに、こっちが勝手に「遠慮」しちゃって、相手に忖度(そんたく)してしまうことによって、問題が大きくなることが多いんです。
例えば、裏社会の人とか大物とか、世の中で怖がられてる人だと、周りが忖度(そんたく)し過ぎたり。その人自身は、素直な少年のまま大きくなって、いろいろな酸いも甘いも見てきただけなのに、周りがどんどん“偉い人”にしちゃうわけですよね。そうすると、本当の気持ちが分からなくなって、逆に猜疑(さいぎ)心にさいなまれるようになるんです。こっちが遠慮し過ぎることで、その人の孤独が深まることもあるんですよ。
--身近なところで言えば社長や経営者、有名人もそれに当たるかもしれないですね。
草下:だからやっぱり、「素直」な姿勢を忘れないことがすごく大事。例えば、子供が大物に対して、「おじちゃん、何でイライラしてるの?」「おじさん、なんか怖いね」って素朴な疑問を口にしたとしても、多分怒らないと思うんです。素直だから。相手に媚びを売るとか、気持ちよくなってもらうとか、そういうことではなく、素直でいることが大切だと思ってます。
--「素直」に相手と向き合うことが大切なんですね。
草下:ただ、よく怒られますよ(笑)。「草下さん、よく言いますね」みたいな。
--やっぱり怒られるんだ……。
草下:でも、自分は素直に言っているんです。確かに「お前、何だよ!」って怒られることもあるけど、思ったことを言ってるし、自分の言葉に責任は持っている。相手が不快に思ったり、怒ったりすることもあるけど、本当の感想を言っているだけなので、こっちに悪意はないんですよ。もちろん、伝え方は大事です。でも、相手をわざわざイラ立たせるような伝え方をしなければ、それは一定の価値があると思うんです。「他人からどう見られているか」という正しい評価を、相手も気にしてると思うから。
でも、先ほどもお話ししたように、遠慮したり、忖度(そんたく)したりすることによって、逆に壁を作ってしまうこともある。だからこそ、素直な気持ちを伝える。それで“素直な自分”が問題になって、相手に攻撃されることがあったとしてもそれは自分自身なので仕方ないですよね。自分そのものが言ったことが、攻撃されるのであれば、それは自分として対峙(たいじ)しなければならないし、また一つ、向き合っていくだけなので。とにかく、素直でいようということですね。

他人と向き合うようになったきっかけ
--本でも前回のお話でも、「他人と向き合う」ことをとても大事にされていますが、そうなったきっかけはあるのでしょうか?
草下:自分は昔から、すごい客観的で冷めてるんです。でも、いろいろつらいことがあって、問題を切り分け過ぎたり、自分と他人を分けたりするだけだと、気持ちがないなと感じて。「何でも解決しちゃいけないな」って思ったんですね。この本は、折り合いをつける話なんですけど、折り合いをつけたところを答えにしないほうがいいこともあるんです。
--どういうことでしょうか?
草下:人間はやっぱり、温かさとか、つらさとか、感情をゴールに持っていかないといけないんじゃないかという気がしていて。自分は客観性がすごく強かったんですけど、それだけだと「人間として全然ダメだな」「人間じゃないな」と思って、他人の気持ちと向き合うようになったのかなと思います。
--人間の複雑性をそのまま受け止めるというか。
草下:そうですね。全部、複雑なんですよ。確かに単純化したほうが分かりやすくなるし、一般化もできる。でも、一般化しちゃいけない部分もあるので。そこは、個々が悩みながら、考えていかなければいけないところですよね。それが、最終的な結論だとは思います。

あえて居心地が悪い場所に行ってみる
--「快適さ」や「分かりやすさ」、「正しさ」が求められて個々の文脈や人間の複雑さがどんどん置き去りになる時代だからこそ、このタイミングで出版される意味があると思いました。
草下:そうなんですよね。居心地が悪い場所に行ったら、痛かったり怖かったりすることもあると思うんです。現実は居心地が悪い場所や部分がたくさんある。そこを切り分けすぎていると「行かなくていい」ということになってしまうんだけれど、あえて痛みやつらさ、悲しみ、怒りという難しい場所に行ってみる。他人に怒りをぶつけられても、逃げずに向き合う。そのなかで、人間的な成長もあるじゃないですか。怒られのテクニックとは別に、人間的な「許す」感情みたいなものを育てていかないといけないと思いますね。
--特に日本では、危ない目に遭うことも少ないですよね。
草下:危なくないとダメですね。やっぱり自分も、危ないことを定期的にしたいので、“成長中毒”みたいなところがあるんですけど……(笑)。でも、成長するのは結構簡単なんですよ。生きていくためのコツはすごく簡単で、「約束したことを守る」「できない約束をしない」です。
--成長するのが簡単というのは?
草下:人間的に成長するとか、次のステージに行くには、今までできなかったことができるようになることが大事なんです。だから、少し難しい約束をして、それを実践するというのが成長のコツです。それも、新しい難しい「怒られ」が発生しそうな場所に行く。そうしたら、やっぱりトラブルが発生して、対峙(たいじ)しないといけない。トラブルに向き合って応えることで、人間的に成長していくんですね。ちょっと弁証法的な感じかもしれないですけど、それをやってほしいなと強く思ってます。

生きていくための2つのコツ
--「約束したことを守る」「できない約束をしない」というのは?
草下:「約束したことを守る」は、どうやって約束を守るかという人間の信義の部分に関わってくることで、「できない約束をしない」は、できないことへの自己理解と「断る」という決断力がつきます。この2つがあれば、全然生きていけるんですよ。
--「断る」のが苦手という声は多いです。
草下:「断る」コツは簡単です。気持ちよく断るんです。「ダメ」「無理」「できない」って、すぐに言えばいいんですよ。ペンディングすると、断りにくくなるんですよね。最初から「面倒くさいな」「嫌だな」と思っていたとして、選択を先延ばしにしてしまうと、相手が選択を迫ってくるじゃないですか。「ちょっと待って」「今は無理だから」と適当に返していると、だんだんとその言い訳は通じなくなってくる。その結果、相手がどんどん求めてくると、無理が生じるんですよ。
--ああ……。確かに答えを先延ばしにすればするほど、相手にも期待を持たせちゃいますね。
草下:そう。だから、できないことは、最初から「できない」って言えばいい。それで、理由を言えばいいんです。「そういうのは、私の性格的に向かないからごめんね」でもいいし、「今めちゃくちゃ忙しいからできないんだ」でもいいし、まずはパッと断ってみればいいんですよ。それでも相手が求めてきたとしたら、それは相手が下品ということだから。できないことを要求してくる人間は、自分の人生にいらないと思うので、付き合い方を考えればいい。だから、「断る」コツは本当に簡単で、気持ちよくすぐに「できない」ってパッと言うのが鉄則だと思います。
--難しい要求に対して、「自分にとって大事な試練なのかもしれない」と思って引き受けちゃうこともあります。
草下:それは、次の段階ですよね。断ることも成長なんですけど、断れるようになった上で、断らない。「これだったらできるかも……」くらいのちょっと難しい問題にチャレンジするのは次の段階です。
ただ、世の中には、肯定を積み重ねることでしか成り立たないコミュニティーが多いので、難しいとは思うんですけど。でも、自分は、気持ち悪い要求を重ねてくる嫌なミルフィーユみたいな社会より、きれいな理由がしっかりあって、その上でちゃんと尊重できる関係のほうが好きなので。なるべくなら、無理をしないでいいような関係になりたいですね。
相手との「約束」が大事な理由
--「分かり合えないことから始める」とも書かれていて、多様性が叫ばれる世の中で“自分にとって居心地の悪い他者”とも向き合っていくという意味でも大事なことだと思いました。
草下:他人は他人なので、分からないですよね。だから、分からないままで全然いいんですよ。でも、分かることとか、分かったかもしれないことがあるのが面白い。そもそも、人間なんて、自分のことも分からないのに、他人のことが分かるわけないじゃないですか。でも、自分と他人との間で、約束を交わす。私が約束を好きな理由は、「約束した」ことは“分かったこと”として残るんですよね。「こういう約束をしよう」となれば、それは自分と他人の間の一個の決定じゃないですか。
--自分と相手との唯一の事実ですね。自分と相手の間にかかる橋のような。
草下:そうです。だから、約束は大事なんです。自分のことも分からないし、相手のことも分からないし、約束が守られるか守られないかは分からないけど、約束が発生して、その約束を履行できれば、それは事実として残ります。その事実が、信頼につながるんですよ。その積み重ねなんです。人間はやっぱり、自分と相手の間に、関係性の本質があると思うので、それを大事にしていくことがいいのかなと思いますね。
--相手とどれだけ橋をかけるかということですね。
草下:もちろん、全然かからない場合もあるし、かからないほうがいい人もいますけど(笑)。
--橋を渡った後に「やっぱり渡らなきゃよかった」と思うこともありますよね。
草下:そうですね(笑)。でも、「橋がかからないほうがよかったな」と思った人でも、もっと踏み込んで話をしてみたら、人間的に深くてすごくいいヤツだったという場合もあるので。やっぱり、可能性は閉ざさないほうがいいですよね。他人のことは分からないけど、分からない中で見える何かがあるかもしれないから、可能性は残しておくべきだと思います。

(聞き手:ウートピ編集部・堀池沙知子)