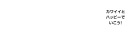扇子で切腹?江戸時代は変な時代だって、知ってた?

時代劇でおなじみの江戸時代は、武家社会と庶民文化が並行し、独自の世界を織りなしている。
人情味あふれる印象とは裏腹に刑場見物が庶民の娯楽で、子供も大勢が集まったという。潔いイメージの武家では年金詐欺や偽装切腹が当たり前というから、とてもじゃないが楽しく暮らせる時代ではなさそうだ。
■役者気取りの犯罪者
当時、犯罪者に対する処罰は、庶民の目にとまるように公開式が多かった。これは戒めの意味で「悪いことをするとこんな目に遭うぞ!」という警告だ。時代劇の判決シーンでは「市中引き回しのうえ〜」が定番だが、これは犯罪者を移送する際に、罪状が書かれた札を掲げながら「さらし者」にする儀式で、義賊として知られる鼠(ねずみ)小僧治郎吉も受けたという。
人間は、恐怖を感じるものが視野に入ると、それを凝視する傾向がある。身の安全を確保するなら、脅威を見張っておく必要があるからで、対向車のライトがまぶしいと思った時、目をそらせば良いのに無意識に見つめてしまうのは代表例だ。同様に、世間を騒がせた悪党がどんなやつだか知りたいのも当然で、スリルではなく安全を求める行動と言えよう。ただし江戸時代ではこれが当てはまらない。退屈しのぎのアミューズメントと化していたのだ。
市中引き回しがおこなわれると、多くのやじ馬で町はごった返す。罪人も注目が集まるのが快感のようで、化粧をした役者気取りや、辞世の句と言わんばかりに和歌を詠む者まで登場したというから、刑罰なのかパレードなのか分からない。
刑場に着くと罪人は処刑され、これにも多くの見物人が集まったというから困ったものだ。現代風に言えば公開処刑だからできれば見たくないはずなのに、江戸時代では子供まで見物に来たと言う。さらに、人が大勢集まるといさかいが起きるのが世の常で、刑場の外ではやじ馬同士のケンカが多々あったという。混雑するなかで「見えない」「邪魔だ」的な話が想像できるが、役人の制止を振り切ってケガ人が出る大ゲンカもあったというから、あきれてものが言えない。
観衆の暴徒化はフーリガンにほかならない。時代劇ファンのお年寄りが知ったら、きっと嘆き悲しむだろう。
■扇子で切腹?
長らく続いた平和は武士にも影響し、「潔い」「武士の精神」は薄れ、インチキな文化が発達した。年金詐欺や偽装切腹である。
武家の収入は関ヶ原の戦いにまでさかのぼり、自分の祖先が挙げた功績によって大まかに決められた。また、個人ではなく家に与えられる仕組みで、そのため何年たっても戦がなくてももらえる制度だからうらやましい。
武家にとっても大変有り難い制度だが、「当主がいる=家が存在する」が支給条件だから、ケガや病気で急死すると隠ぺい工作がおこなわれる。子が大きくなるか養子をもらって準備が整うまで、当主は「自宅療養中」ということにし、もらい続ける詐欺が多発したのだ。
潔いイメージが強い武士も残念ながらほど遠く、他力本願な「なんちゃって切腹」も登場した。
武士の自決は切腹が定番だが、腹に刃物を突き立ててもすぐにはこと切れず、強烈な痛みを味わうことになる。そこで、長く苦しまないように介錯(かいしゃく)人がとどめを刺すのだ。
ところが長らく平和の続いた江戸時代では自刃できない人も登場し、刃の代わりに扇子を使う「扇子腹(せんすばら)」が登場した。要するに、自分は扇子で切るマネをするだけで、あとはお任せの構図である。なかには泣き叫び逃げ出そうとする者もいて、介錯(かいしゃく)人が押さえつけて無理やりおこなう他力切腹もあったというから、介錯(かいしゃく)人はつらいよ。
■まとめ
武士道という言葉は、明治時代になってから作られたという。しかも語源は西欧の騎士道だから、江戸オリジナルとはとても言い難い。
事実は小説よりも奇なり。時代劇や小説だけでなく、歴史書を読んでみるのが良さそうだ。
(関口 寿/ガリレオワークス)