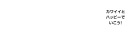インターネットが“感情の劣化”を深刻化させる 宮台真司が語る、現代社会を生き抜く術
IS(イスラム国)の拡大による戦争やテロの深刻化、対立を深める欧米とロシア、北朝鮮の脅威など国際社会の混乱は枚挙にいとまがない。また、自国に目をやれば格差の拡大や貧困率の上昇など、不穏な状況が続いている。
不穏な時代を生き抜くには、どうすればいいのか?
明るい未来を描きにくい時代の背景にある、根本的な構造の歪みとは何なのか? そして、私たちはどのようなスタンスで、これからの時代を生きていけばいいのか? 当然、答えは簡単に導き出せるものではないが、答え無き時代を生き抜くヒントを提示しているのが書籍『社会という荒野を生きる。』(KKベストセラーズ)。最近話題のニュースや事件をもとに、社会が抱える問題の本質に迫る同書。著者である社会学者の宮台真司氏のトークイベントが、ジュンク堂書店池袋本店で開催された。
『社会という荒野を生きる。』(KKベストセラーズ)
-->-->-->-->-->
「グローバル化」と「IT化」によって格差が拡大した
まず語られたのは、グローバル化と格差との関係。格差の拡大はグローバル化によって、「人」「モノ」「カネ」が国境を超えるうえで制限が緩和されたこと、そしてIT化が進んだことに起因すると宮台氏は指摘する。
「90年代に入り冷戦体制が終わり、97年の通貨危機以降、露骨なグローバル化が進みました。グローバル化では、資本移動が自由に行われるわけですから、当然ながら製造コストが安いところに人やモノが逃げていきます。すると、先進国だった国々の中間層が分解して格差が広がり、事実上、貧困層が急速に増加することになる。たとえば、アメリカでは過去20年間にIT技術者の年収が半減しました。それは、インドにいる優秀な人間たちが安い賃金で仕事を引き受けるようになったからです。それだけではなく、IT化によって中間層に属するホワイトカラーが従事していた、事務労働の低賃金化が進みました」(宮台氏、以下同)
“感情の劣化”が民主主義に危機をもたらす
また、インターネットは産業構造だけではなく、民主主義にも大きな影響を与えたという。
「インターネットの普及も一因となり起こる感情の劣化は、民主主義に危機をもたらすといわれています。たとえば、ビッグデータ処理が可能になった結果、マスに向けた広告でいえば、感情のボタンやフックを仕込めば、人がどう動くか計測できるようになったんですね。いま現在、この仕組みを政治にも応用しているんです。
社会心理学者のジョナサン・ハイトによれば、『弱者』『平等や公正』『伝統』『聖なるもの』『権威』の5つのボタンによって人間の感情が動くといわれています。このボタンをどう押すかによって、政治の動員力が変わる。そのため、つまりはどの政権でも同じことが行われている状態なんですね。我々は釣り堀の魚たちのような扱いをされていて、人間的な討論の相手として対象にならなくなったわけです」
政治が人々の「攻撃性」「排外的思想」をあおる
例として挙げられたのが、ブッシュ大統領が当選したときの選挙活動で使われた方法。それまで政治に参加しなかった南部の高卒白人をターゲットにして攻撃性や排外的思想にあおりをかけるというマーケティングで、テロとの戦いにおいて非常に有効だった。そのため、後に色々な国の指導者および指導者になりうる人たちが、こうしたメカニズムを最大限利用するようになったのだそう。
“そもそも民主主義とは何なのか”――昨年、安全保障にまつわる法整備の際に、民主主義のあり方が問われ、学生をはじめ国民的な議論に発展したことは記憶に新しい。しかし、宮台氏の見解をまとめると、現在の民主主義は、データに基づいた為政者の“釣り餌”に、民衆が食いつくか食いつかないかだけが重要であり、「議論に基づく意思形成の合意」という本質的な意味での民主主義を実行するのが難しいということになる。
また、近代化による合理化が進んだことで、「人間」の存在も変わってくるという。
社会の合理化によって、人間が「入れ替え可能」な存在になる
「合理化においては、内容よりも形式を備えていること、次のステップに進めるということが大事になります。そうすると、どうなるかというと『計算可能化』『予測可能化』が起こるんですね。これが近代化のかたちです。さまざまな決定が合理化をもとになされていきますから、呪術、宗教的な感受性が無関連なものになってきます。もちろん、信仰者は居続けるかもしれませんが、ほとんどの決定が『手続き主義的』になります。そうした世界では、人間は入れ替え可能な存在であり、権限がある人間が権限を行使すればいいということになります。
そこで、例にとることができるのが、ナチスドイツの隊員で、数百万人のユダヤ人大量虐殺の指揮をとったアドルフ・アイヒマンです。彼は後の裁判のなかで、『良心はなかったのか』と問われたとき、『良心はあったが役に立たなかった。良心を訴えても即処刑され、代わりが充てがわれるだけだ』と証言しています。合理化が進行した社会では、主体の優位性は全く問われないということを示している事例だと思います」
では、合理化による主体性の損失に対抗する手立てはあるのだろうか。
「全体主義」で社会を統合すれば、国は滅びない。しかし…
「近代社会学の創始者といわれるマックス・ウェーバーは、『人々は神の縛り、道徳から自由になった結果、誰もが損得勘定にもとづいて自発的になる』ことを踏まえ、その処方箋として『人格性を取り戻すこと』が重要だといっています。
そうした彼の処方箋を一蹴したのがカール・シュミットです。彼の議論に従えば、『社会が近代化されていくと、人は入れ替え可能な存在になる。道徳がなくなるし、社会が統合を失う。統合を失うと他国に勝てない』ということになります。そして退廃した道徳を復興するために、社会統合をしていく。どうすればいいかといえば、ねつ造であっても嘘であっても構わないが『全体主義』による社会統合を達成させる。それによって国は滅びることがないという結論にいたります」
しかし、このようにして生まれる全体主義には大きな問題点があるという。
インターネットが「攻撃性」を後押ししてしまう
「民主主義を通した全体主義化によって、『理想的な枠組みを擬似的に使って全体主義を取り戻さないと、日本やアメリカ、フランスは他国に負けてしまう』という考え方は、不穏分子を排除や攻撃の対象にするというやり方があります。敵を想定することによって、味方を味方らしくする。
民主主義の前提である『感情の質』が崩れた結果、民主主義が誤作動してしまう。すると、ポピュリズムにはしり、感情の政治がまかり通るようになります。攻撃性や排外主義を前面に押し出すことで、単純な議論が席巻するようになります。さらに、後押しするのがインターネット。いわば個人がむき出しのインターネットのなかで、自分が見たいものだけを見て、自分がコミュニケーションしたい仲間とだけコミュニケーションするので、感情の劣化が深刻化するのです」
これからは「マイクロユニット=顔が見える範囲」での活動が重要になる
情報の不完全性や非対称性によって、“これをやっつければすべてが解決する”という単純な思考に陥りがちになると宮台氏は言う。では、ミクロに生きる我々は、どのようにして生きればいいのか。そこで、重要になるのが、「マイクロユニット」の存在だという。
「家族、親族、血族、地域集団、職能集団、いろいろあるでしょうが、顔が見える範囲のなかで人々が認知されるユニットで、感情のクオリティを高めていくということが大事になるでしょう。短期的にはコミュニケーションのなかで感情の劣化した人が、イニシアチブを取れないように封鎖することも必要だと思います。顔が見える範囲で、どういう雰囲気の人がどのようなことを言っているのか判別できるようにする。勇ましいことをいって主導権を握ろうとすることを抑止することが大事になるのです」
一元的な宗教や道徳で縛ることができなくなった社会を生きていくためには、感情の質を高めることが必要だと宮台氏。それは、幼い頃の感情教育や育ち上がり方とも関わるとも指摘する。大きなうねりのなかに身を置くなかで、まずは社会のあり方に疑念を抱き、本質的な構造を理解する努力が求められているのかもしれない。
(末吉陽子)