
ネットで大人気を博した漫画をもとに作られたアニメ映画『映画大好きポンポさん』がヒット中です。本作を手がけたのは『劇場版「空の境界」第五章 矛盾螺旋』や『魔女っこ姉妹のヨヨとネネ』、『ゴッドイーター』などを作ってきた平尾隆之監督。本作の制作にどのように取り組んだのか、そして本作のテーマを支えた平尾監督の思いはどんなものだったのか、話をうかがってきました。
劇場アニメ『映画大好きポンポさん』公式サイト
https://pompo-the-cinephile.com/

原作者である杉谷庄吾さんへのインタビューも合わせて読むと「なるほど」と納得の部分があるかもしれません。
連載より単行本1冊分を一気に描くのが「得意距離」という『映画大好きポンポさん』原作者・杉谷庄吾【人間プラモ】さんにインタビュー - GIGAZINE

GIGAZINE(以下、G):
映画が公開されるのに合わせて、平尾監督はいろいろなインタビューに答えておられるので、その内容も踏まえていろいろうかがっていければと思います。まず、アニメイトタイムズに平尾監督と松尾プロデューサーのインタビューが掲載されていて、「マイノリティがマジョリティに一矢報いる」というテーマについて、「フリーランスになった時に、はっきり意識して言葉にできるようになりました。自分自身、小さい頃は周りにうまく馴染めず、映画やアニメーション、漫画に救われたと思っていたので、その恩返しというか」と話していたのですが、平尾監督を救った作品というのはどういうものだったのでしょうか?
平尾隆之監督(以下、平尾):
小学校低学年ぐらいの時に、吃音が出るようになってしまったんです。今でも緊張すると出るのですが。それと、赤面症もあり、人と話せなかった時期があるんです。話をするとどもるから、からかわれて、友だちも1人ぐらいだったかな。つまり、周囲から外れてしまったんです。そのときに、同じような境遇のキャラクターが出てくる映画などに「救われた」という経験があったんです。
G:
なるほど。
平尾:
小さいころから自覚があったわけではありませんが「社会から外れてしまった人が一矢報いる」というような作品に救われたような感じがあるんです。例を挙げると、『ヤングガン』です。当時の若手の役者さんを集めて西部劇を撮ろうっていう映画で、格式高い作品ではありませんが、ビリー・ザ・キッドが無法者として追い詰められていく中、権力者に一矢報いるストーリーに惹かれました。
平尾:
それから『ふしぎの海のナディア』も好きでした。週刊少年ジャンプのヒーローものとはちょっと違って、科学が大好きだけれど力のない少年がナディアに引っ張られてドラマに入っていく感じが良かったです。
平尾:
『機動警察パトレイバー』も好きでして、あれは作品の前提にあるのが落ちこぼれの人たちで、それが集まって「みんなで幸せになろうよ」というお話だったので(笑)、ルーツをたどるとそういうところだったんだろうなと思います。
平尾:
漫画だと『AKIRA』ですね。5歳上の兄がいて、買ってきたものを読ませてもらいました。『AKIRA』だと、金田より鉄雄なんです。
G:
(笑)
平尾:
鉄雄は仲間の中であまり認められていないけれど、力を手に入れて暴走していくという。鉄雄自身はよくない方向に転がっていってしまいましたけれど、その気持ちはすごく分かるなと。
G:
この「マイノリティがマジョリティに一矢報いる」というのは、普遍的でいいテーマだなと思いました。その一方で、『ポンポさん』作中でも触れられていますが、マジョリティに作品が刺さる必要もあります。そのあたりで、マイノリティ的な感覚とマジョリティ的な感覚は、どのようにバランスを取っていったのですか?あるいは、バランスはあえて考えずに突破していった感じでしょうか?
平尾:
「マイノリティがマジョリティに一矢報いる」というテーマが自分の中にあったとしても、作風や語り口、演出などすべてマイノリティにしてしまったら、マジョリティにはピンとこないかもしれません。なので、メタ的でもありますが「『マイノリティがマジョリティに一矢報いる話』をマジョリティにも伝わるように作る」ということは意識していました。『ポンポさん』という作品が世に広まって欲しいという気持ちもあり、同時に、夢を追うすべての人に向けた応援歌という意味も込めたので、アランくんというキャラクターは必要でしたし、広くエンタメとして見せられるものするために、ストーリーをわかりやすくするように心がけました。
G:
アランくんの部分を含めて、原作にはないオリジナルな部分がいろいろ追加されていますが、一方で、上映時間を90分にするために、鉄の意志でいろいろなシーンを削ったとうかがいました。最終的には削られたけれど盛り込んでいたオリジナル要素やエピソードは、残った部分以外にはどういったものがあったのでしょうか。
平尾:
ぱっと思い出せる部分では1つ、ジーンくんの過去を掘り下げたシーンが脚本にありました。本編でも一部残っていますが、なぜジーンくんが映画にのめり込むことになったのかを、映画版なりの解釈で2ページから3ページ分書いていました。
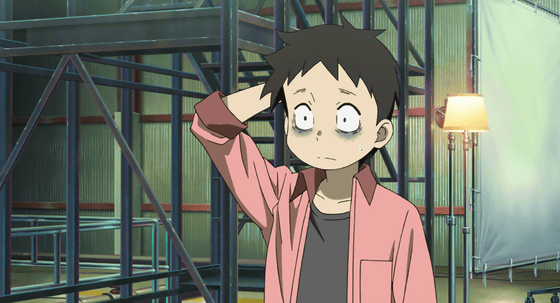
平尾:
あとは、「編集とはどういうものなのか」という部分も、本編よりももうちょっと分量がありました。本編でポンポさんやミスティアさんが話をしているダイナーに、編集に立ち会っていて自分のシーンがあまりにも切られてしまったナタリーが泣いて帰ってくるという。
G:
(笑)
平尾:
ポンポさんに泣きつくんですが、ミスティアさんやマーティンから「自分が出演したものもいっぱい切られている」「編集で切られても、役者として、作品がよくなった方が見てもらえる機会が多くなってうれしい」と言われるようなシーンがありました。

平尾:
あとは、銀行のシーンも本当はもっと長かったですね。頭取に関する部分や、全世界に発信していった過程を本編よりじっくり描いていました。たとえば、頭取は全世界に配信されていることを知って、それはもうしょうがないからうまく利用して最終的には銀行のイメージアップを図ろうとする側面もあります。本編では匂わす程度でしたが、脚本ではもうちょっと明確にしていました。そうやって、入れたいシーンはいろいろとありましたが、90分という枠に合わせて、ギリギリ分かるラインで切っていったという感じです。
G:
いま話にあった銀行で出てくる「クラウドファンディングでの資金調達」は、リアリティのある方法だなと思いましたが、何かご自身や近しい方に経験者がいたりしたのですか?
平尾:
プロットの時点では、アランくんは仕事を外されたあと、自分の仕事を探し始めるという内容になっていました。それを、バンダイナムコエンターテインメントの富澤祐介さんや、原作の編集担当の有馬聡史さんから「アランくんは自分のいる場所で咲いた方がいいんじゃないか?」とアドバイスをもらって、「だったらジーンくんを支える側に回った方がいいんじゃないか」ということになりました。「じゃあ銀行かな」となって「銀行なら資金の話だろう」と。ただ、そこを地味に伝えていくとなると、それはそれで違う話になってしまって、『ポンポさん』ではなくなってしまいます。そこで、クラウドファンディングや世界配信というものを思いついたというか……配信については「賭けだな」というのはありましたが(笑)
G:
(笑)
平尾:
ギリギリあってもおかしくないお話にしていくという形で組み上げていきました。……あれは最初から僕が考えていたんでしたっけ?
松尾亮一郎プロデューサー(以下、松尾):
そうだったんじゃないかな?「クラウドファンディングにしよう」とは言っていたと思う。
平尾:
僕いったん書いた脚本を元に、製作委員会やハリウッドで仕事をしていた方に「銀行が映画に対して融資するのはあり?」とか取材して、リアリティを詰めていった感じです。
G:
先ほどのアニメイトタイムズのインタビューで美術についての話があり、平尾監督と監督助手の三宅寛治さんが「美術監修」として、あげてもらった美術に「世界観を加えていく作業を本当に最後の最後のギリギリまでしていて」というくだりが出てきます。この「世界観を加える作業」というのは、どういったものだったのですか?
平尾:
そうですね……たとえば白い壁があってそれを描くとき、普通に考えれば光源に合わせて色は白と白から落ちるグレーのグラデーションを用いるのですが、『ポンポさん』では白を使わず緑みや青みがかったものにしたり、影に光源の色味を入れたり、グラデーションの境界線にピンクやシアンを入れているんです。上げていただいた美術はリアルならそうなるというしっかりとしたものですが、「『ポンポさん』の世界観ではこのちょっとしたピンクや緑などを入れる」という作業を、僕と三宅さんでしたという感じです。
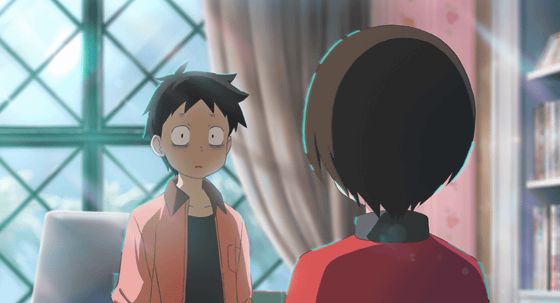
G:
最終的なブラッシュアップをしたという感じですね。同じインタビューで、平尾監督は「人によるので言い切れませんが、いま幸せな人に希望の物語は描けないんじゃないかと思うことがあります。なにかしら絶望や辛いことを経験しているからこそ、希望という渇望を描けるというか。実際、ポンポさんも『創造的精神活動』と言っていましたけど、そういった部分はあると思いますね」と語っていて、まさに『ポンポさん』作中でも描かれていることなのですが、監督自身が「創造的精神活動」に影響したと感じるような、つらいことや苦しかったことというのは、どういったものがありますか?
平尾:
正直に言えば、まず先ほども言った、子どものころに吃音でつらい目に遭ったというのが1つ。それと、今 敏監督のもとで働いていたときは、とても勉強になりましたが、何をしてもOKが出ず、自分の力のなさを痛感しました(笑)。そして、『ゴッドイーター』の評価が芳しくなかったことですね。
平尾:
『ゴッドイーター』は絵コンテから脚本から自分でやって、反省点はあるものの、自分としては面白く作ったつもりですが、なかなか評価を得られないまま、最終的にはufotableを去らなくてはいけなかったというのは自分の中では大きかったです。長年一緒にやってきたチームもありましたし。それで、世間的にこんなに大きな失敗をしたらまともな作品を作ることはできないかもしれないと思ったこともありました。でも、「なぜ自分はこの業界に入ったのか、なぜ物作りをしているのか」と考えたとき、自分の過去と深く向き合って見つめ直すことができた。そして「マイノリティがマジョリティに一矢報いたい」というテーマを自分の中でようやく言葉にできるようになったんです。もし、監督としてもう一度作品を作れるなら、マイノリティの人たちを応援するような作品を、自分が救われたように作りたいんだと自覚したというか。
G:
おお、なるほど。
平尾:
本当に次の仕事も決まらないまま、ufotableを出ることになってしまいましたから、藁にもすがる思いで『進撃の巨人』の監督だった荒木哲郎くんに「仕事をください」と電話をかけました。すると、ちょうど『甲鉄城のカバネリ』の制作中だったので、『ゴッドイーター』が終わって1週間後くらいにはWIT STUDIOさんにお世話になることになったんです。あの時は本当に助かりました。
平尾:
コンテのお手伝いなどをして、『進撃』の二期も含めると1年以上かな……? お世話になる中で、周りのみんなが輝いているのを見ながらすごく悶々としていた時期もありました。ただ、「次に作るとしたらどういったものを作っていけばいいんだろうか」とすごく考えさせられた時期でもあり、それは映画版の『ポンポさん』のコアになっていると思います。だから、今考えるとufotableを出たことも含めて、あの時期があってよかったなと。自分にとって、とても大切な時間だったと思います。
G:
電ファミニコゲーマーには平尾監督がバンダイナムコの富澤さんと一緒に受けたインタビューが掲載されていて、「『ポンポさん』の話が出たとき、ちょうど僕は小説を書いていて」とあります。これは、2019年に出た『>のけもの王子とバケモノ姫』のことでしょうか。
平尾:
悶々としていた時期に作りたいことが言葉にできたとき、チャンスがあるといろんな人に「こんなものを作りたいんです」と話をさせてもらったんです。それまでは全然言葉にしたりしなかったんですが、話をするようにして。その中で「じゃあ書いてみませんか?」と声をかけてくれた人がいて。
G:
『のけもの王子とバケモノ姫』のあとがきで百瀬祐一郎さんの名前が出てきて、「そうだったのか!」と思いました。
平尾:
百瀬くんは僕が監督をした「桜の温度」で制作進行をしてくれて、仲良くしていたんです。彼は紆余曲折を得て小説家になっていて、一緒にごはんを食べることもあったんですが、僕が「こういうものを作りたい」と話をしたら「僕も小説を書いているので、一緒に書けるなら書きましょうよ」と言ってくれて。それで、編集担当の有馬さんと引き合わせてくれたんです。
G:
アキバ総研のインタビューでは、この『のけもの王子とバケモノ姫』の執筆打ち合わせで小説の担当編集者さんが漫画編集をしていたことがわかり、『ポンポさん』をKADOKAWAから出版する話が出て、さらにアニメ化の準備につながったという話が出てきます。平尾監督の人生では、こうやって縁が縁を呼んでつながることというのは、わりとあることなのでしょうか?
平尾:
いやー、これは初めての経験でした。ufotableを出たあと「また機会があれば一緒にやりましょう」と言ってくれた方が何人かいて、その中の1人が富澤さんだったんですが、すごくありがたくて、離れていく縁は追いかけてもしょうがないけれど、つながっている縁は大事にしていこうと思ったんです。それで、百瀬くんから連絡があったときも「声をかけてくれた縁は大事にしたい」と思いました。それで、富澤さんから「『ポンポさん』を出版する出版社を探しているんだけれど」と相談されたときに「ちょうど僕、小説書いているので打ち合わせに同席しませんか」と取り持つことになって。そのころ、ご飯に行く仲だった松尾くんがちょうどCLAPを立ち上げたところで、縁が重なるようにして一気につながっていったという感じなんです。
G:
同じアキバ総研のインタビューでは、今 敏監督に「『お前は監督になりたいのか、演出になりたいのか、作家になりたいのか』と聞かれた」という話が出てきます。平尾監督はこのあと「自分は演出家だと思っていた時期もありますし、職業監督に徹してやっていくべきなのか……と、悩んだこともあります。ただ、今までキャリアを積んできて分かったことは、自分はどんな原作でもこなせるような監督には向いていない、ということです」と答えていて、原作ものを引き受けるにあたっては「自分の気持ちをちゃんと乗せられるものなのか、ズレはないか、ということをまず考えます。『ポンポさん』も引き受ける前にそこをじっくりと検討しました。原作と自分をすりあわせてちょうどいいところを探す、という感じでしょうか」と続けているのですが、本作において、「マイノリティがマジョリティに一矢報いる」という大きなテーマ以外にも、平尾監督の気持ちや考え方がダイレクトに反映されている部分はありますか?
平尾:
原作で最初に共感できたのはジーンくんでした。社会になじめなくてはじき出された人間が、最終的に映画の世界の中で輝いていくというお話にすごく感情移入できて。そこから読み進めて、どう映画化していこうかと考えたとき、この映画をみんなが持っている夢への応援歌にしたいと思うと同時に、「マジョリティに一矢報いる」と考えたとき、「夢を叶える」為には他の選択肢を捨てる覚悟も必要なんじゃないかと思ったんです。ジーンくんは社会にはじかれる前に、自分なりになじもうと努力はしたんだろうなと。でも自分の中であれはだめ、これもだめと消していって探したら、残ったのが映画だったという選択の歴史があったんだろうなと思ったんです。そして、選んできた今を肯定する映画にしたかった。じゃあそのメッセージを込められるのは実際の映画作りの工程だとどこかというと、「編集だな」と。そこにドラマとクライマックスを集約させようと。
G:
ふむふむ。
平尾:
『ポンポさん』の中で、ジーンくんが最初に認められるのは編集だったわけですよね。でも、原作はニャカデミー賞の前に「これから『MEISTER』の編集をしますよ」というところでぷつっと切れて、次は受賞会場になっているんです。これはこれできれいですが、映画にするならここだな、ここにドラマがあったはずだなと思って、そこに先ほど言ったテーマを持ってくるようにしました。

G:
同じアキバ総研のインタビューでは他にも今さんの話が出ていて、演出になること自体が目的になっていたという若き日の平尾監督に「演出っていうのは、すでにあるものをどうやって美味しい料理にするかを考える人。監督っていうのはオーナーにお店を任されたような役割で、作家というのはその人がつくったものをみんなに見たいと思ってもらえて、それで飯を食うということだと思うから、自分がどうなりたいか、どこかで決めないとね」ということを言ってくれたというエピソードが出ています。平尾監督は、今の自分自身はどうだと捉えていますか?
平尾:
そこは本当に難しいところですね。『ゴッドイーター』をやって思ったのは、もらった原作をどんなものでもその通りに処理できる人間ではないということでした。だったらもう、自分の中の作りたいものを発揮していける作品を、原作ものであればシンクロ率の高いものを、オリジナルならオリジナルでテーマを出せる人になろうと考えました。結局、そうじゃないと自分にウソをついてしまうし、原作にもご迷惑をおかけしてしまう。作ったとしても不満が残るというか、やりきれなかったものがあるというようになってしまうのではないかと。……そういう意味では、「まともな監督ではない」かもしれません(笑)。
G:
平尾監督は「自分の作品がひとつ終わるたびに『こういうことができなかった』『ここはどうすればよかったんだろうか』と反省点を洗い出すことにしている」とのこと。まだ公開中の作品ですが、本作ではなにか反省点はありますか?
平尾:
作り終わった直後だと、絵作りの点で「ここがうまくできなかったな」「きれいにしたかったな」というのが出てくるのですが、時間が経ってくると、少しずつ流れや脚本面で「ここ、もう少しこうしたらよかったな」というのが出てくるんです。もっとわかりやすくした方がよかったかな、もっと伝わる表現にできたかもしれないな、というのが見えてくる。細かいところでの一例だと、ジーンくんが編集室で倒れて病院に運ばれるくだりです。あのとき、ナタリーが来て「間に合うんですか?」と声をかけて、振り返ったジーンくんは「あと1週間ある」と言うんですが、目線の先に何があったか覚えていますか?
G:
目線の先。1週間あることをカレンダーで見たような。
平尾:
最初にジーンくんが振り返ったときに、棚に貼ったカレンダーのピンが片方はずれて、落ちかけているんです。ジーンくんは一度モニタに眼を戻し、もう一度振り返り、カレンダーを直そうとするんですが倒れてしまう……という流れなんですが、そもそもジーンくんがなんで立ち上がってなにをしようとしたのか、あまり伝わってないんじゃないかと。じゃあどうすればよかったかというと、例えばカレンダーは落ちかけておらず、ジーンくんが振り返ったときにちょうどぺろっとはがれる。それで、スケジュールを確認しようと立ち上がるようにすれば、「ジーンくんが立ち上がったのは、カレンダーのスケジュールを確認しようとしたからだ」ということが、言葉にしなくてもわかったかなと。
G:
おおー……なるほどなるほど。
編集するジーンくん

平尾:
もちろん、観てくださった方は頭の中で補完するのでまったくわからないというものではないですが、そういった細かい点の積み重ねが、見ている人のストレスを減らすことにつながるんだと思うんです。『ポンポさん』をできるだけたくさんの人に見てもらえるように、なるべく「誰が見ても分かる」ようにしていったつもりだったのですが、そういった点で、もっと伝わるようにできたところがあったんじゃないか、というのは常に考えます。
G:
アニメハックのインタビューで、過去の平尾監督について「金髪で、いわゆる若者のアイコン的な格好をしていた」と出てきます。今の平尾監督は、ごくごく普通の格好なのですが、何かファッションを変える転機みたいなものはあったのですか?
平尾:
……何があったんでしょう?
松尾:
むしろ聞きたいよ(笑)。金髪は1年ぐらいだよね。
平尾:
そうそう。マッドハウスに入社してから一年くらいは金髪で、それから白髪にしたこともあって……。一概には言えないですけれど、冷静に振り返ると、内面の弱さを隠したかったとか、自身の髪の色やファッションで自己表現していたということだったのかなと思います。演出になり、監督になり、作品で表現したいことを乗せていけるようになったから、そういった格好をしなくなっていったということかもしれません。
G:
同じくアニメハックのインタビューでは、ファーストガンダムを見てハヤトに感情移入したという平尾監督に今監督が「お前、普通はアムロだろう。お前みたいな若者は、だいたい自分がアムロだと勘違いするんだよ」「ハヤトみたいな一般人に、なぜお前は感情移入するんだ」と言ったという話が出てきます。平尾監督は映画などを見ていて、一般人に感情移入することはわりとあるのでしょうか?
平尾:
たぶん、いわゆる天才やヒーローに感情移入するタイプではないのだろうと思います。自分がそうだったからか、努力型じゃないですが、これだけ頑張っているのに報われない、もっとこの人に報われて欲しいと思う人物に感情移入していくんですよね。
G:
本作は各キャラクターに「好きな映画3本」が設定されているのが特徴的で、パンフレットではスタッフやキャストの方々も好きな映画を3本挙げられています。平尾監督は「セッション」「127時間」「グッドフェローズ」とのことですが、それぞれ、どういったポイントが好きなところですか?
平尾:
ダニー・ボイル監督はトランジションがすごく上手で、『127時間』ではストーリーにも感動しました。主人公は、行き先を告げなくても帰ってこられると調子に乗っていたことがあだとなり、それでも生きようともがき、最後には教訓があるわけですが、自分と重なる部分があります(笑)
G:
(笑)
平尾:
『グッド・フェローズ』は昔から好きな作品です。マフィアものって、一度高みに登るけれど凋落があるというのがお決まりですが、『グッド・フェローズ』はそこが秀逸で、マフィアの一味になり絶頂期を迎えるけれど、最終的には仲間を裏切ってでも生き残りたいという、ただの人間になってしまう。この業界でも、監督をやっていて成功することもあるけれど失敗だってある。そのときの考え方みたいなものを教えてくれる作品だなと思いますね。「調子に乗ったら痛い目に遭うぞ」と。
G:
またも(笑)
平尾:
『セッション』に関してもそうですね。主人公は自分に自信があってやってきたけれど、そこから叩き潰されたり、敗北を味わったりする中で、だんだんと自分が演奏する音楽だけに耳を傾けていく、という。
平尾:
そこは仕事をやっていてもあることですよね。ジーンくんが編集に向かうとき、当然、ポンポさんが「上映時間が長い映画は全部やだ」と言う理由とか、みんながお金を出しているから諦められないという気持ちは持っているけれど、夢中になっていくとどうでもよくなって、ただただ作品に向き合っていく。そういう瞬間がないと楽しめない部分があるんじゃないでしょうか。僕もそういうのはわかるなと……ただ、僕はどうしても視野が狭くなってしまって、苦しくもあり楽しくもあるのですが、終わった後に「周りの人のことを考えなければいけない」と怒られたりして、反省しています。

G:
平尾監督は、『千年女優』でひとつひとつのカットに過去の映画へのオマージュを込めた今 敏監督を見て「ここまでの多方面の知識をもっていないと監督ってできないものなのかと思いました」と振り返っています。本作もかなりそういった点は行われている感じがありましたが、演出や監督として、どういった知識や経験がある方がよいと考えますか?
平尾:
「自分が心を動かされた瞬間」みたいなものを、どれだけ自分の中にストックしておくかというのは大事だったのではないかな、と思っています。例として適切ではないかもしれないのですが、今さんが亡くなったという連絡を受けたのは夏のことで、蝉の音がすごくうるさかったのですが、メールをもらった瞬間、すっと音がなくなったのを覚えています。「ああ、ショックを受けるというのはこういうことなのか」と自らの体で感じました。
あとは、映画であれば、なぜこの作品が好きなのかを自分で明確な言葉にできるまで考え続ける、ということでしょうか。数を見るのが大事なのではなく、しっかり理解するのが大事なんだなと。なぜ今さんが映画のオマージュを自分の作品に取り入れることができたかというと、「自分はその作品の何がすごいと思ったか」を理解していたからこそだと思うんです。つまり、自分がすごい、好きだなぁと思ったものをどれだけ理解し、表現できるか、そして突き詰めていけるかなんじゃないかと。そういうところは、ある時期から自覚的に考えるようになりましたね。
G:
今回、原作者の杉谷庄吾さんは、最初の顔合わせ以降は映画にはまったく口を挟まなかったとのことでした。杉谷さんがTwitterに掲載した漫画でも「確認を取りたい案件も幾つかあったみたいですがそれも全部知らぬ存ぜぬを通した」と書かれていましたし、パンフレットでも監督から「いろいろ確認していただきたいことはあったのですが(笑)」との言及がありましたが、どういった点を確認してもらえたらと思っていたのでしょうか?
平尾:
たとえば、『MEISTER』の中でリリーが歌っている歌がアリアだというのはセリフでわかるのですが、曲はなんだろう、とか。吹き出しのドイツ語から調べてみると「マタイ受難曲」だとわかったのですが、そうなると今度は、杉谷さんがマタイ受難曲を選んだ理由がきっとあるはずなので、そういうのも想像したり。原作に書かれている情報からすべて自分なりに読み取っていったという感じです。
あと、『ポンポさん』は不思議なメディアミックス展開をしている作品で、最初の提案書を作った時点ではまだ第1巻がコミックスになっていなかった時期だったんですが、脚本を書いているうちに2のネームが上がったという話を聞いて「あっ、まだ続きがあったとは!」と(笑)。杉谷さんが描いたものが「正典」ですから、そこからズレてしまうと大変だなと思ったのですが、結局、ズレている箇所もあれば、そこまで大きな食い違いはない部分もあるという感じで。そもそもが「ポンポさんとは何者か」というのが第1巻部分でははっきりと描かれていなかったので、我々映画班でいろいろと解釈していたのですが、3で普通に学校に行く少女だったことがわかり、いい意味でドキドキでした(笑)。もともと杉谷さんは1で終わらせる予定だったそうで、その1をもとに我々は4年ぐらいかけて映画版を制作しましたが、その間に杉谷さんが2以降も描いてくださり、ポンポさんの世界を広げてくださった。1ファンとしても、新作を読むのは嬉しかったですし、とても感謝しております。
G:
今回は長時間のお話、ありがとうございました。
「映画大好きポンポさん」は好評上映中。なお、立川シネマシティで7月22日(木)14時30分上映回後、平尾監督と撮影監督・星名工さんが登壇する極上音響上映記念の舞台挨拶が行われます。記事掲載時点で、わずかに空席があるので、気になる人はぜひ足を運んでください。
劇場アニメ『映画大好きポンポさん』本予告 - YouTube
©2020 杉谷庄吾【人間プラモ】/KADOKAWA/映画大好きポンポさん製作委員会
外部リンクGIGAZINE(ギガジン)
関連情報(BiZ PAGE+)









