第二次世界大戦、日本にも響いた独ソ戦の要諦

「ニューズコム」「ワールドヒストリー」第二次世界大戦:ポーランドへのドイツ侵攻第二次世界大戦:ポーランドへのドイツ侵攻、1939年9月1日、45のドイツ師団と空中攻撃を使用。 9月20日までにワルシャワのみが開催されましたが、9月29日に最終降伏が行われました(写真:World History Archivee/ニューズコム/共同通信イメージズ)
ヨーロッパで2度目の大戦が勃発してから80年目。その帰趨を決したのが独ソ戦だ。拙著『独ソ戦 絶滅戦争の惨禍』を上梓したタイミングで、図らずも、独ソ不可侵条約、ドイツのポーランド侵攻、英仏の対独宣戦布告などの歴史的事象が、それぞれ80周年を迎え、さまざまなメディアで報じられたこともあって、考えさせられることも多々あった。
そうして再確認したのは、第二次世界大戦において、ソ連要因が果たした役割の大きさである。ソ連という巨大な岩塊は、いくたびかの決定的な時点で、第二次世界大戦の流れを転回させたのであった。
第二次世界大戦開戦前後と独ソ戦勃発直後の2つの時期における政治と戦略の展開を示しつつ、ソ連の動きをみていくこととしたい。
戦争の局地化を計るヒトラー
1939年春、ヨーロッパは戦争の予感におののいていた。アドルフ・ヒトラー率いるナチス・ドイツは、前年に同じゲルマン系の民族が主流を占めていたオーストリアを合邦していたが、さらに英仏伊と結んだミュンヘン協定を無視して、チェコスロヴァキアを解体し、自らの勢力圏に収めたのである。次なる侵略の矛先がポーランドに向けられるであろうことは、誰の目にも明らかであった。
しかし、ヒトラーは1つの壁に直面していた。これまで、第一次世界大戦後のヨーロッパ国際秩序における原則の1つであった民族自決を逆手に取り、ドイツ系少数民族の解放を大義名分として、無血で領土拡張を進めてきたのであったが、その術策も限界に達していたのだ。イギリスとフランスは、これ以上ドイツに対する宥和政策を続けることはできないと、ポーランドに保障を与え、同国が攻撃された場合には参戦・支援すると約した。つまり、ドイツがポーランドに手を出せば、それは2国間の戦争にとどまらず、欧州大戦に発展すると宣言したに等しい。
むろん、ヒトラーも対抗策を取らなかったわけではない。1938年以来、英仏の介入を防ぐために、ドイツは日本との接近をはかっていた。日独防共協定の軍事同盟への強化を目指す、いわゆる「防共協定強化交渉」である。もし日本を同盟国として獲得し、戦争勃発の際の参戦義務を課せられれば、たとえ英仏がヨーロッパの戦争に介入しようとしても、その極東植民地が日本の脅威にさらされることになるから、踏みとどまらざるをえない。それがヒトラーの計算だった。
ところが、ドイツと結ぶことは、英仏、ひいては、両国を支援するであろうアメリカとの対立につながると危惧した日本海軍ならびに外務省は、軍事同盟への反対を続け、ゆえに「防共協定強化交渉」は長引くばかりだった。すなわち、ヒトラーが望んだような、日本による英仏の牽制は期待できなくなったのである。
スターリン流の安全保障
一方、ソ連の赤い独裁者スターリンも、大戦の影に怯えていた。これまで、ソ連は、フランスやチェコスロヴァキアとともに集団安全保障態勢を構築してきた。ところが、当事者であるチェコスロヴァキアの頭越しに英仏伊がドイツと交渉したばかりか、ソ連を無視したとあっては、もはや集団安全保障に頼ることはできなかった。スターリンは、英仏がドイツにチェコスロヴァキアを譲り渡した背景には、ヒトラーをソ連にけしかける意図があると理解したのだ。
ならば、相手がヒトラーであろうとも、その好意を取りつけ、ドイツの攻撃がロシアに向かないようにしなければならない。スターリンは決断を下した。彼が発したシグナルは、慎重ではあったが、同時に明瞭なものであった。
1939年3月、第18回ソ連共産党大会においてスターリンが行った演説は、重大な変化を含んでいた。従来、スターリンは資本主義国家のすべてを激しく非難していたのに、このとき攻撃されたのは英仏だけだった。さらに、およそ2カ月後に、スターリンはリトヴィノフ外務人民委員(他国の外務大臣に当たる)を更迭、モロトフに代えた。リトヴィノフは、英仏を含めた集団安全保障を通じてドイツを封じこめる政策を進めてきた人物だったから、この人事の意味するところは明らかである。
5月20日、新任のモロトフ外務人民委員と初めて会見し、独ソ経済交渉について議論したドイツの駐ソ大使は、 同交渉は政治的基盤がつくられた際にようやく再開され得るという、含みのある言葉を告げられた。一方、ベルリンでも、ドイツ外務省の東欧局長と駐独ソ連代理大使の間で、政治面での関係改善が論じられだしている。
スターリンは、不倶戴天の敵ヒトラーと結んででも、大戦の局外にとどまることを選んだのである。一方のヒトラーにとっても、日本に代えてソ連との関係を深め、英仏の牽制に当てるというのは魅力的な策であった。
8月12日、駐独ソ連代理大使は、ソ連側は独ソ協議に関心を抱いており、会議の場所はモスクワを希望していると、ドイツ側に申し入れた。ヒトラーは、ただちにリッベントロップ外務大臣に全権を託して、ロシアに派遣すると決定した。同月23日にモスクワに到着したリッベントロップは、すぐにモロトフと交渉を開始し、24日午前2時に(条約の日付は23日)、両国の国境の不可侵ならびに、第3国と交戦に突入した場合には他の締約国は中立を守ることとした条約に調印する。有名な独ソ不可侵条約である。この条約には、秘密議定書が付属しており、東欧における独ソの勢力圏を定めていた。
こうして、スターリンはひとまず大戦に巻き込まれることを免がれ、ヒトラーもまた、ポーランド侵攻を2国間戦争に局限する前提が整ったものと信じた。言い換えれば、ソ連の動きは、第二次世界大戦初期の枠組みを定めたのである。
さらにスターリンは、東西二正面戦争というソ連にとっての悪夢が現実とならないようにするため、極東でも手を打っていた。当時、極東ソ連軍・外蒙古(がいもうこ)軍は、ノモンハンで日本の関東軍と国境紛争に陥っていたのだが、ドイツへの接近によって西方は安泰となるとみたスターリンは、ノモンハンに機甲戦力を集結させ、8月20日に攻勢を発動させたのだ。衆知のごとく、日本軍は大損害を出し、停戦交渉を余儀なくされた。
なお、冷戦終結後に機密解除された文書から、ソ連軍の消耗も激しかったことが確認されたこと、また、国境画定についても、ある程度日本側の意見が容れられたことから、日本軍はノモンハンで勝ったとする向きも出てきた。しかしながら、ソ連軍が、関東軍に打撃を加えることによって、日本陸軍を対ソ慎重論に傾かせ、戦略目的である東方の安定を達成したことを考えれば、そうした主張は観念的な空論であると判断せざるをえない。スターリンは、いわばノモンハンの戦闘をもって、日ソの大戦を回避することに成功したのである。
独ソ開戦と日本
独ソ不可侵条約締結によって、英仏の介入を押しとどめうると確信したヒトラーは、1939年9月1日、ポーランド侵攻に踏み切った。けれども、彼の情勢判断は誤っていた。2日後、英仏はポーランドとの保障条約を守って、ドイツに宣戦布告する。ヒトラーの誤断から、ドイツは2度目の欧州大戦に突入したのだ。それでも、ドイツはポーランドを征服し、翌1940年にはベネルクス3国とフランスを降伏させたが、イギリスはなお抗戦しつづけた。
こうして手詰まり状態に陥ったヒトラーは、イギリスが戦争を継続するのは、いずれソ連が味方になると期待しているからだと考えた。だとすれば、ソ連を打倒しなければ、戦争は終わらない。しかも、ソ連の植民地化は、かねてヒトラーの目指すところであり、収奪によってまかなわれているドイツの戦時経済にとっても必要不可欠である――。ヒトラーはソ連侵攻を決断した。1941年6月22日に発動された「バルバロッサ」作戦である。
交戦国であると中立国であるとを問わず、ドイツが対ソ戦に突入したことは大きな衝撃であったが、とりわけ影響を受けたのは日本であった。当時の日本は、中国での戦争やドイツとの同盟(1940年9月、日独伊三国同盟締結)を巡って、アメリカとの対立を深めつつあった。その日本に、仇敵ソ連をドイツとともに東西から挟撃するチャンスが巡ってきたのだ。
ゆえに、独ソ開戦を伝える最初の情報(1941年6月5日に、大島浩駐独大使が報告してきた)を得て以来、東京では、対ソ政策を巡って、激しい議論が交わされることになる。松岡洋右外務大臣は、4月に日ソ中立条約を締結したばかりであるにもかかわらず、即時対ソ参戦を主張した。対ソ戦に引き込まれることを警戒する海軍は、独ソ戦への介入反対を唱える。陸軍に至っては、南進論、北進論、南北準備論(対ソ、対英のいずれにも開戦することなく、南北両面に対応できるよう戦力を強化すべしとの主張)に分かれ、内部でも対立する始末であった。
しかし、陸海軍首脳部は妥協にこぎつけることができ、南北準備陣を進め、好機が到来した場合にのみ独ソ戦に介入するという「帝国国策要綱」を作成する。これは、7月2日の御前会議で裁可された。世にいう「熟柿(じゅくし)主義」、柿が熟れて落ちるのを待つのにたとえ、労せずして成果を得んとする方針である。その実は機会主義にほかならない。
北進の幻
事実、この「帝国国策要綱」は、不介入を原則としていたものの、独ソ戦が日本に有利に進んだ場合には、武力を行使して「北方問題」を解決するため、ひそかに対ソ戦力を準備すると定めていた。つまり、対独戦に兵力を引き抜かれ、極東ソ連軍が弱体化したときには、対ソ戦に突入するとの含みだ。そのための戦力を整えるべく、1941年7月5日、東條英機陸軍大臣は、「関東軍特種演習」と称される動員計画を承認した。大動員により、対ソ戦にあたる予定の関東軍を兵力70万以上に増強しようというのである。
こうして、ソ連と「満洲国」の国境には、一触即発の空気がみなぎった。陸軍のなかには、ノモンハン以来の守勢から転じて、ついに対ソ戦を断行する好機が来たとはやりたつ者も少なくなかった。その急先鋒となったのは、陸軍参謀本部作戦部長田中新一少将であり、彼の下には、作戦課長服部卓四郎中佐ならびに作戦班長辻政信中佐という名うての好戦派がいた。
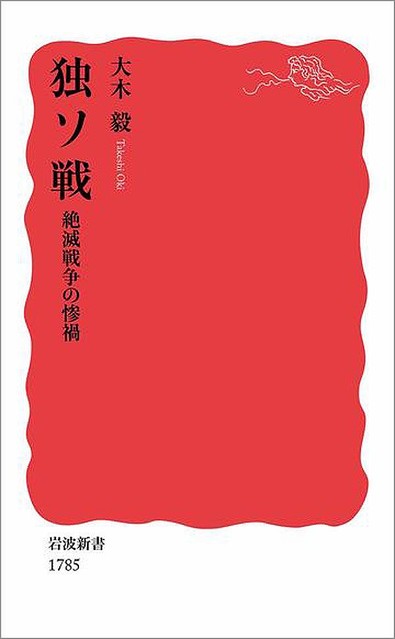
けれども、彼らの「期待」が満たされることはなかった。陸軍参謀本部が開戦の前提条件としたのは、極東ソ連軍の兵力が半減することであった。ところが、極東ソ連軍は、一向に減少する兆しを見せない。一説には、ソ連軍は、極東の精鋭部隊を対独戦に引き抜いたあとに新編部隊を補充する、あるいは、部隊としてはソ満国境にいるのだが、古参の下士官兵や装備のみを抽出し、代わりに新兵や旧式兵器を配備するといった形で、額面上の兵力を維持したといわれる。
いずれにせよ、拙著でも詳述したように、1941年7月後半にはドイツ軍の進撃は鈍り、ソ連の急速な崩壊など考えにくい情勢になってきた。また、日米関係も急激に悪化していたから、北方に剣をかざしたままでいることは、いよいよ困難である。
8月9日、陸軍参謀本部は、ついに年内は対ソ武力行使を実施しないと決定した。とはいえ、「関東軍特種演習」で準備された兵力装備は、やがて太平洋戦争初期段階の南方作戦に転用されていくことになる。1941年に日ソ戦争は起こらなかったが、そこでのソ連の行動は、極東、さらには太平洋での第二次世界大戦の展開に大きな影響を与えていたのである。



