阪神の投手酷使はいつから始まったか?|クラシックSTATS鑑賞阪神
クラシックSTATS鑑賞、阪神の最後に年別の投手起用をみていく。今回は勝ち星ではなく登板試合数で見ていきたい。長くなるので阪神優勝の85年から2000年までと、2001年から昨年までに分ける。
「阪神の投手酷使」とややきついタイトルをつけた。最初はそこまで言うつもりはなかったのだが、調べていくうちに「酷使」という言葉が決して大げさではないと思えたのだ。
85年から2000年。50試合以上登板した投手を青字、60試合以上を赤字で表した。
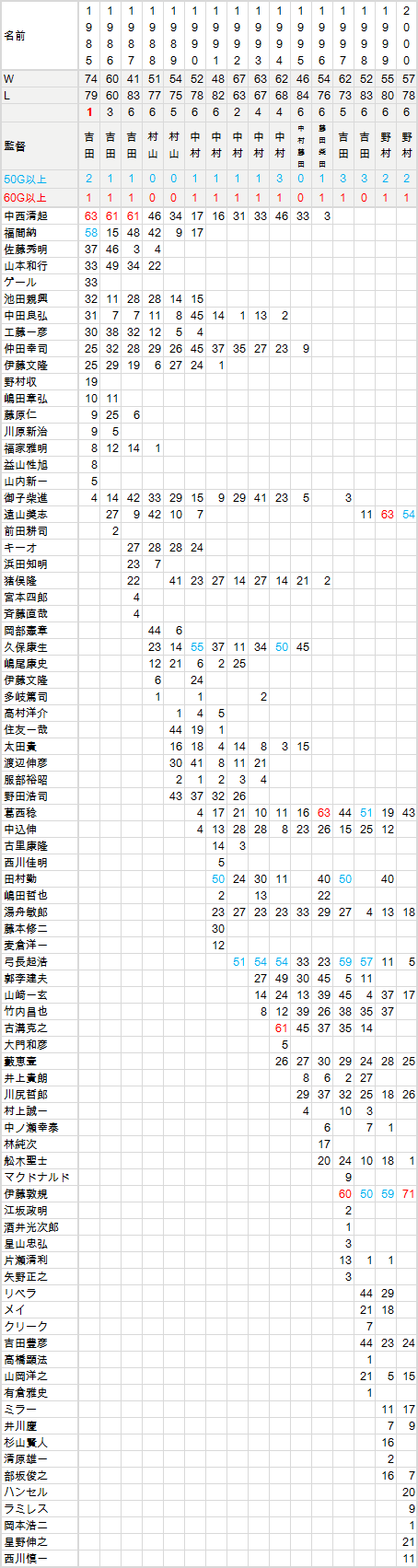
85年の優勝は強力打線によるものだが、山本和とともにクローザーに起用された新鋭中西清起と福間納の貢献も大きかった。この時期のリリーフ陣の中心は山本から中西に移行しつつあった。中西と福間は連投をいとわない剛腕の持ち主だった。
87年に最下位に転落すると村山実が2度目の監督に就任。注目すべきは成績は上がらなかったが、村山は50試合以上登板する投手を作らなかったのだ。投手を分散して起用していたのだ。
中村勝広監督の時代は、94年を除き毎年一人の投手が50試合以上登板。田村勤、弓長起浩そして古溝、久保という移籍組がその任を担った。
そして97年の再度の吉田監督時代、続く野村監督の時代に、セットアッパー、クローザーを重用する伝統が築かれていく。今に続く酷使の歴史は伊藤敦規、遠山奬志あたりから始まっていく。
こうして表を見ていくと、通算成績ではぱっとしないが弓長起浩、御子柴進のように黙々と投げていた投手がいることが改めて思い起こされる。ボリュームを気にしなければ、こういう投手も取り上げていくべきだと思う。
阪神で60試合以上登板した投手は創立から84年まではわずか延べ11人しかいなかったが、85年から2000年までで12人。そして21世紀に入ると一時期鳴りを潜めたのちに、その傾向に拍車がかかるのだ。以下、明日の午後。
「阪神の投手酷使」とややきついタイトルをつけた。最初はそこまで言うつもりはなかったのだが、調べていくうちに「酷使」という言葉が決して大げさではないと思えたのだ。
85年から2000年。50試合以上登板した投手を青字、60試合以上を赤字で表した。
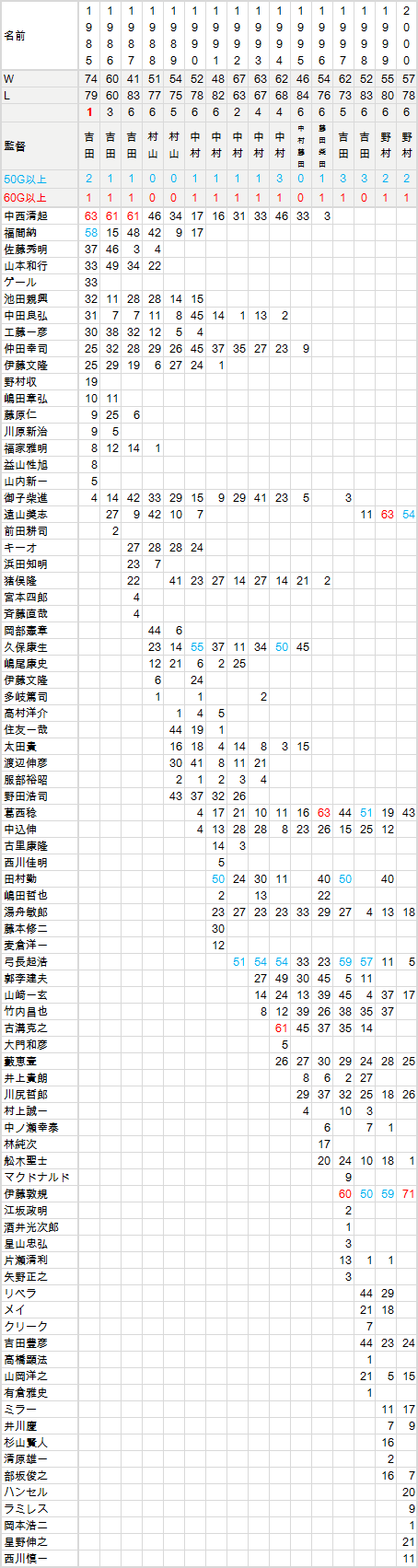
85年の優勝は強力打線によるものだが、山本和とともにクローザーに起用された新鋭中西清起と福間納の貢献も大きかった。この時期のリリーフ陣の中心は山本から中西に移行しつつあった。中西と福間は連投をいとわない剛腕の持ち主だった。
87年に最下位に転落すると村山実が2度目の監督に就任。注目すべきは成績は上がらなかったが、村山は50試合以上登板する投手を作らなかったのだ。投手を分散して起用していたのだ。
中村勝広監督の時代は、94年を除き毎年一人の投手が50試合以上登板。田村勤、弓長起浩そして古溝、久保という移籍組がその任を担った。
そして97年の再度の吉田監督時代、続く野村監督の時代に、セットアッパー、クローザーを重用する伝統が築かれていく。今に続く酷使の歴史は伊藤敦規、遠山奬志あたりから始まっていく。
こうして表を見ていくと、通算成績ではぱっとしないが弓長起浩、御子柴進のように黙々と投げていた投手がいることが改めて思い起こされる。ボリュームを気にしなければ、こういう投手も取り上げていくべきだと思う。
阪神で60試合以上登板した投手は創立から84年まではわずか延べ11人しかいなかったが、85年から2000年までで12人。そして21世紀に入ると一時期鳴りを潜めたのちに、その傾向に拍車がかかるのだ。以下、明日の午後。



